
当協会顧問の荘厳舜哉先生のひとりごと・・・
機知に富んだ楽しい話題がいっぱいです。
眠られぬ夜のために;『般若心経』を読む
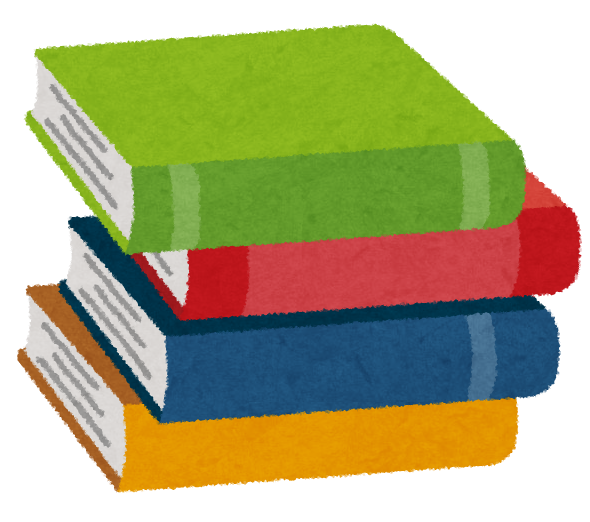
私はクリスチャンではありませんのでヒルティの、『眠られぬ夜のために』は読んだことがありませんが、ベッドの枕元には入眠用の雑多な本が積み重なっています。数えてみると枕元に6冊、ベッドの下に7冊、加えてエコノミストと東洋経済各1冊がありました。トラ姫様は寝ることがお仕事ですし、山の神様はものの5分で入眠されますが、77歳の老人はすぐには寝付けないのです。そこで本の出番になります。
本は時に入れ替わりますし雑多な内容ですが、今読んでいるのがB. Greeneの『時間の終わりまで』(講談社:本文524p)。これには相当手こずっています。高校時代、当時物理は3単位コースと5単位コースに別れていましたが、友だちに理系が多かったものですから無謀にも5単位クラスを選択しました。結果は一学期2、二学期も2、3学期にやっと3の評価をもらいましたが、こういう純粋?文系人間にとって、素粒子論の基礎にある数学理論を胃の腑に落とすのには時間がかかるのです。読み始めて半年、やっと第3章「宇宙の始まりとエントロピー」を読み終わり(わかったつもりになり)、第4章「情報と生命力」で奮戦中。
一方、軽いのは古今東西の箴言・名言・格言・迷言つきの『人生はニャンとかなる!』、『人生はもっとニャンとかなる!』です。ほとんどネコの顔を見るだけですので、もう10往復はしていると思います。ネコの顔は見飽きないのです。ワハハハハ!
で、ここからがお立ち会い!
灯台もと暗しの諺ではありませんが、亡父の30年で線香をあげようと今月12日朝、仏壇前の経机の引き出しを開けたら『般若心経』という8頁の小冊子が出てきました。今まで仏様の世話は山の神にお任せしていたので、引き出しを開けたこともなかったのですが、見つけた小冊子が面白い。要するに仏教でいう「知恵」とは何かを解説しているのです。私いつも仏教、特に禅は宗教ではなく哲学であると言っていますが、この小冊子を読んで改めて意を確たるものにした次第。
お釈迦様の教えの真髄は「色即是空 空即是色」にあるでしょう。色は、身体やそこに宿る生命を代表とする物質的なものですが、それはすなわち空(シューニャ)であり、空はまた色でもあるというのです。我々が生きている、つまり存在している確信の実体である五薀(物質・感覚・表象・意志・認識)ですら皆空。
また、解脱して道を修めれば此岸から彼岸にいくよ(『ブッダのことば』第五「彼岸に至る道の章」、中村元訳)とおっしゃっていますが、彼岸が天国であるとはおっしゃっていません。ですから解脱のためには自分で考え抜くよりしかたがない。我々が、“ある”ためにはこのように透徹した自己との対話を重視する仏教は、どう考えても宗教ではなく哲学であるというのが私の結論。
これ以上考えるとまた眠られぬ夜になります故に、頭を空にして眠りに入りましょう。トラ!頼むからそのワオ~ンというおたけびを止めておくれでないか!
(4月21日)
【ノーテンキ川柳】 空なるは シューニャのもじり 舜哉かな (字余り)
アズマヒキガエルのことなど

毎年4月第一週の月曜日に別荘を開けることにしており、1日から5日まで飯田に出かけておりました。今年は暖冬だったのでもうスミレがはびこっているかと手ぐすね引いて出かけたのですが空振り。その代わり、芝生はモグラに徹底的に荒らされていました。スミレに加え、今年は機動力を持つモグラが加わったことで、芝生戦線は点から面にと拡大しています。
ところでまた、ジャガーをディーラーに運び込まなければならないところでした。原因はアズマヒキガエルです。
私は寺で生まれ育ちましたので、殺生は大のお嫌い。山にいると小型動物に遭遇することが多いのですが、可能な限りsave their lifeを心がけています。セミが道路に落ちていれば近くの木の幹に預け、モグラが側溝に落ちてえらいこっちゃと慌てている時は、這い上がれるように足場を作ってやり、サワガニは手でつまんで避難を。というわけで、散歩をしていても結構忙しいのです。但し、ヤマカガシが道路を横切っている時にはその限りではありません。どちらかと言えば意図的に、車輪が彼らの上になるように運転するのですが、成果は確認できていません。
別荘がある沢城湖周辺には沢山のアズマヒキガエルが棲んでいます。春になるときゃつらが穴から這い出してくるので、注意をして運転しなければなりません。今回も3日に雨が降り、翌4日には配偶者を見つけようとウロウロしているヒキガエルに何匹も出会いました。不思議なことに、ヒキガエルも自然の環境で遭遇したときは結構機敏に行動し、大きくジャンプしたりするのですがなぜか道路上では動きが極端に鈍ります。いわゆるfreezeした状態になるのです。靴先でつついたくらいでは動きませんよ。試してみて下さい。
で、別荘のゴミ集積所の前を走っていると一匹、大きなのが道に座って?いました。そのままだと轢いてしまうかもしれませんので車を止め、側溝に避難させようと落ちていた木の枝できゃつをつつきましたが、全く動きません。二三度つついていたところ、視野の端で捉えていた車がバックしているではありませんか!あれ~、またかいなと慌てて戻り、乗り込んでギアをストップに切り替えましたが、ダイヤル式のギア操作がニュートラルの位置だったのです。お粗末な話ですが私はADHDですので、二度三度とこういう不注意を繰り返してしまいます。実はうっかりミスのボディ修理で保険会社から既に2度、合計400万の支払いを受けているのです。だから年間の車両保険料はなんと、385,470円。これ以上あがると、私の年金生活は破綻してしまいます。クワバラクワバラの天神さん。
(4月12日)
【粗忽川柳】 ガマ見ても あせらず点呼 ギア操作
北海道も観光公害の巻

京都はオーバー・ツーリズム対策として観光地のみに停車するバスを6月から走らせるそうですが、冬の北海道、ニセコや富良野周辺も大変混雑しているようです。特に富良野地域では雪で覆われた農地への観光客の侵入で、大変な迷惑が発生しているとか。ニセコやトマムはスキー客に限定されていますが、富良野は「映え」目的の写真撮影ですので迷惑なことでしょう。
私は単に「乗り鉄」ですので、そういう迷惑はかけません。ただ、積丹半島を回る長万部-倶知安間は一日4本ですので、ゆっくりした旅になります。という訳で朝は函館市電に乗って駅前から湯の川温泉往復。乗り鉄ですのでレールの上を走る乗り物には必ず乗車するのです。その後10:45分の北斗9号で函館を出発し、12:14分に長万部に着き、駅前食堂で温かい山菜蕎麦を食べた後、13:24分の倶知安行きに乗車しました。野生動物ウオッチングが目的ですから4人掛け座席窓側に座りました。少し遅れて若いオーストラリア人が二人、向かいの席に座りましたので久しぶりに英語で色々話しをしました。
スキーが目的であることはわかっていますが、どうして沢山のオーストラリア人が日本に来るのか尋ねたら、スキー場はメルボルン近辺に4つあるが雪は少ない。だからみんなニュージーランドか日本に行くのだとの返事でした。なるほどねぇ。オーストラリアは昨年の山火事でもわかるように、大変乾燥した気候ですから雪は期待できないのですなぁ。納得。余談ですが帰りの飛行機から見た日本列島は、分厚い雲で覆われていました。そりゃ雨も雪も降るわなぁ。
彼らは倶知安で降りていきましたが、私も小樽行きに乗り換え、再び4人掛けシート窓側に座りました。発車までに少し時間があったので駅のトイレを利用し、席に戻ってみると前に雪焼けした東南アジア人夫婦が座わっていました。ご多分に漏れず二人はスマホを操作していましたが、男性の方のスマホから耳障りな音が漏れてきてうるさくて仕方がありません。随分我慢していたのですがついに切れまして、Where are you come from?と聞いたらインドネシアとの返事が返ってきました。
でまぁ、There are other person on this trainと言いましたら奥さんが気づいて旦那に注意してくれました。ヒジャブは被っていませんでしたから恐らく中国系インドネシア人なのでしょう。ところで最近は京都でもマレーシアやインドネシア系の観光客を随分多く目にしますがインドネシアの経済成長率は非常に高く、人口も増加の一途。日本では65歳以上人口が29.1%ですが、対するインドネシアはたった6.5%、逆に生産年齢は67.3%といいますから経済が上り調子なのもよくわかります。人口は2030年には3億人を越えるそうです。
対する日本や中国、韓国などでは人口減が始まっています。韓国では合計特殊出生率が0.72と世界最低ですし、中国でも2023年新生児出生数は902万人と急激な落ち込みを見せています。どうやらアジアにおける経済ヘゲモニーは、日本・韓国・中国などからインド・東南アジア諸国に移行していくのでしょう。そうして日本はますますインバウンド消費に頼るようになるのでしょうが、増える一方の観光客に人口減の日本はどう対応するのでしょうかねえ。隣の町内には修学旅行生専用(?)の宿がありますので、私もインフレ対策を兼ねて、お運びさんや布団の上げ下ろしのアルバイトでも探しますか。姫様のトッピング費用を賄うためにも!
(3月30日)
【ボケ川柳】 足まろび ひっくり返るが 関の山 (詠み人:エゾタヌキ)
関西弁の野生動物たちの巻
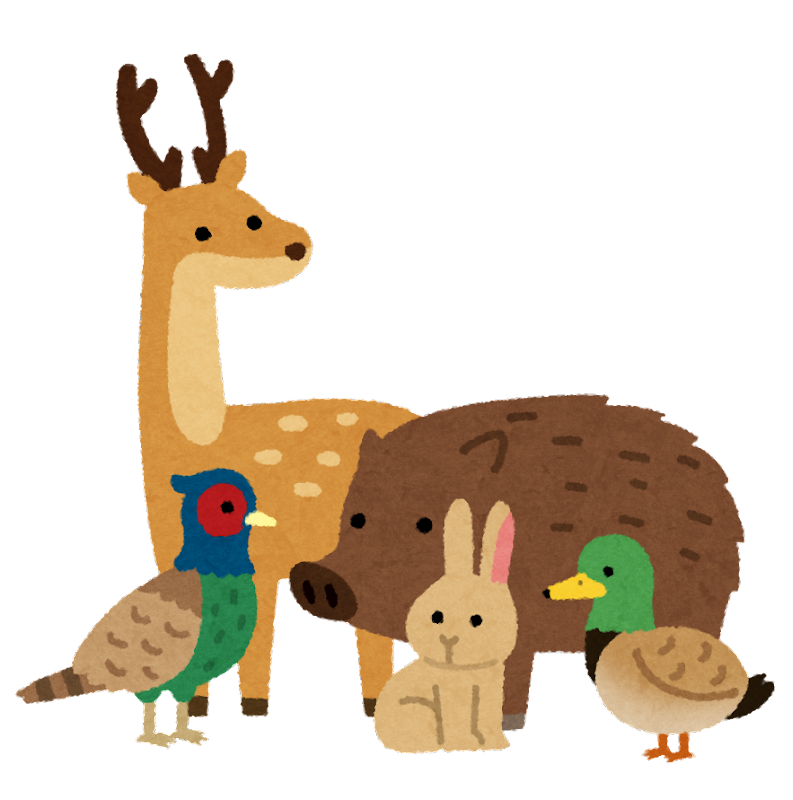
乗り鉄の私は旅と温泉が大好きで、北は利尻・礼文から南は西表島まで巡っていますが、西表島温泉(湯量減少で現在は閉鎖)に浸かりながらアカショウビンに出会った時は感激でした。ですからぐるり一周北海道の旅のもう一つの目的は、野生動物の姿を目にすることです。という訳で野生動物目撃チャンスが多い釧網本線や宗谷本線天塩川流域、それに函館本線山線(長万部―小樽)では、目を皿にしています。
今回の旅でも多くの野生動物を目撃しましたが、一番面白かったのが「えらいこっちゃ、見つかってしもた」と、まろぶ(転ぶ)ように走っていた天塩川流域のエゾタヌキです。このタヌキ、写真にも写っていました(やった!)がなぜか関西弁なのです。小樽市博物館には北前船に関する資料が展示されていますが、昔、蝦夷と関西は北前船でつながっていました。ですから関西弁のエゾタヌキは、察するところ淡路島の芝右衛門狸(日本三名狸)の末裔なのでしょう。じっとしていれば谷地坊主に見間違われるのに、走るから見つかってしまうのです。タヌキの淺知恵ですなぁ。
キタキツネは釧網本線と山線でそれぞれ一匹づつ目撃しました。もちろん彼ら(he and/or she)も関西弁です。網走近くで見かけたキタキツネは大村崑同様、「ああ、いそがし」と言いながら線路脇の斜面を駆け上がっていきましたし、山線のキタキツネは「またきてや」といって見送ってくれました。
天塩川流域には、ワシやワシや!と関西弁で自己主張をするオジロワシも沢山います。仲良く並んでいましたから恐らくつがいであろうと思いますが、これを含めて10羽以上を目撃しました。エゾシカは釧路湿原で最も多く目にしますが、天塩川流域にもいました。ただタンチョウは、今回の旅では全体で5羽しか目撃できませんでした。これはもちろん釧網本線です。前回の旅では線路の上にいた3~4羽を退かせるために連続で警笛を鳴らし、待避させていましたが、今回は雪原を優雅に歩いていました。
それにしても3月の天塩川は変化に富んでいます。瀞の部分は凍っていますが瀬の部分では氷が流れ、その変化には見飽きることがありません。一面が氷結している川は、北海道でしか見られないでしょう。逆に釧路湿原は、恐らく湧水のせいだと思いますが、全面氷結はしていないように思います。
まぁしかし、寒いの大好きなデニソワ人にとって銀世界は見飽きません。最終日の小樽は気温2度、風も随分と強かったですがブレザーだけで歩いていました。コートなどを着ていようものなら、少し歩いただけで汗が出てくるのです。薄着しているとよく不思議がられますが、私から言わせるとコートやダウン着用の上、まだマフラーグルグル巻の方がよほど不思議です。
ところで今回、山線の車内や小樽では沢山の外国人に会いましたし、小樽着の快速エアポートからは何百人という人たちが降りてきました。明らかに北海道にもオーバー・ツーリズムの波が押し寄せています。という訳で次回は人間の話です。
(3月24日)
【アツガリ~ノ川柳】 デニソワの 人は好みし 摂氏二度
再開、北海道一周の旅:ADHDでよかった!の巻

2020年はコロナ、2022年はロシアによるウクライナ侵略で中止していたぐるり一周北海道の旅を再開しました。千歳―釧路-網走―旭川―稚内―旭川―函館―小樽―千歳という経路、5泊6日の忙しい旅です。この時期京都では北山杉の花粉が猛威をふるいますので、北海道旅行は花粉症対策でもありますが。
ADHDの私は特に旅行の場合、分単位で計画を練りますので余裕の時間があまりないのですが、今回は本当に時間的余裕がゼロでした。理由は飛行機・列車の延着です。
13日、伊丹10:00発のANA773便に乗機しましたが新千歳空港が混雑しており、着陸が約10分遅れました。おおぞら5号釧路行きは南千歳12:25分発。この便にアクセスしているのは新千歳12:18分のエアポートですから、飛行機の到着時刻が予定通りであったとしても、JRの発車時刻までの余裕は28分。この28分には降機、移動、切符購入、弁当・飲み物購入に要する手間が含まれています。
ところが新千歳空港の混雑で着陸が10分遅れ、あの広い空港内を移動しながら18分でこの要件を満たすことはほぼ不可能。幸い座席番号は11Aですのでスムーズに到着ロビーへ出まして小走りで、まずはJRみどりの窓口まで。ここで北海道一周切符(7日間有効)と釧路行きおおぞら5号のグリーン車指定券を購入後(私の旅行目的はJR北海道の一冬50億円に達するという除雪費用援助ですから、一周切符に含まれている指定席引き換えは使いません)、弁当とビール購入のため地下階から二階まで引き返します。無論、エスカレータでは空いている右側を駆け上ります。
何とか弁当屋を見つけて購入するも、ビールは売っていないというので同じ階のコンビニまで走り、カゴにロング缶3本を放り込んでレジ待ちの列に並びましたが10人ほどが待っています。こらアカンと思ってビールの入ったカゴを空きカゴの上に重ね(御免なさい、棚に戻していたら乗り遅れるのです)、地下JR改札口まで走って飛び乗りました。発車までの余裕は10秒程度。
南千歳駅では自動販売機を探し、取りあえずお茶を一本確保して乗り込みましたが、座席に座ってから見ると何とこれが350mmではなく280mmのボトル。あるんですねぇ、こういうサイズが。という訳で朝7時に家を出て4時に釧路に着くまでの9時間、飲むことが出来たのは280mmのお茶だけ。でもこの時思ったのは、「ああ、ADHDでよかった!」なのです。つまりこういうせわしなさが苦にならない自分のキャラに感謝!なのです。山の神様同伴ではこうはいきませんが。
一度あることは二度あると言いますが、15日の旭川―稚内往復の旅でも、稚内到着がなんと同駅発車予定時刻。列車は稚内折り返しですから逃しはしませんが、車内清掃が終了次第発車というアナウンスで、元来は19分あるはずの滞在時間が8分になってしまいました。この8分間に勝手知った稚内駅構内(広くはありません)のコンビニでロング缶を2本買い、弁当屋さんでたった1つしか残っていなかった弁当を買い、改札に並びました。乗り込んで席について早速プシュ、一口ゴクンの後に思ったのがやはり、ADHDでよかった!ワハハハハ。
(3月21日)
【ADHD川柳】 時間なく 走り回って より楽し
つながりという幻想:心の氷山モデル

3月1日の日経朝刊13面に、「SNSがつなぎ、壊した」という面白い記事がありました。私はスマホを拒否していますので報道されているどのプラットフォームにもアクセスしたことはないのですが、利用している媒体によってユーザーの生活の満足感が異なるという記事です。
生活全般に対して最も満足感が高いのはLinkedinの利用者だそうです。私は名前を聞いたことがなかったのですが、このプラットホームは求人や調査に特化しており、ユーザーはビジネスパーソンとのことです。日本では300万人程が利用しているというネット情報でした。逆に、満足度が低いのはTik Tokのユーザーとのことです。記事にはユーザーの年齢層情報がなかったので私がネットで調べたところ、これがネット情報が信用できない部分ですが、依拠する何の根拠も示さずに中年男性が多いと記載されていました。Tic Tokは主にアパレル、美容、飲食などの情報プラットフォームとして利用されているようですので、私は興味・関心が移ろいやすく他者から影響を受けやすい若者が多いと思うのですが、意外でした。ただ、ここでフェイクの実体に触れたような気がしています。
ところで紙面には10のSNSプラットホームの名があげられていましたので、お読みになっていらっしゃらない方のために転載しておきます。ユーザーの満足度の高い順に、Linkedin、WhatsApp、Nextdoor、Facebook、Pinterest、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、Discord、TikTokです。皆さん、ご利用のSNSはありましたか?ちなみに山の神様と孫娘がつながっているLineは、9000万人のユーザーがいるそうですが、リストにはありませんでした。日本限定だからでしょうか?
面白いのは、「もしトラ」や「ほぼトラ」で社会の分断が拡大しつつあるアメリカでは、SNSが民主主義に悪影響を及ぼしているという意見が主流で(64%)あるのに対し、アジアではよい影響を及ぼしているとする意見の方が多数派であるという統計結果です。日本はよい影響と評価したのが57%、悪いという評価は23%でした。日本の方がまだ、社会の分断傾向に対して持ちこたえているということなのでしょうか。
閑話休題。人間を、「表面的にはつないだけれども深い部分で関係性を壊していったSNS」という主題に戻りましょう。フロイトは、人の心は氷山のようなものであり、見えている部分(意識・行動)はほんの僅かであってその下には顕在化していない潜在意識や、さらにその深層には無意識があり、総体は氷山のようなものであると考えていました。ですから我々が他者の、あるいは自分が自分の行動や動機を理解したと思ってもそれは表層に過ぎないというわけです。
ま、フロイトの話を始めると長くて七面倒くさくなりますのでここまでにして、自分という存在ですらわかりきっていないのですから、いいね!に頼るようなコミュニケーションが如何に表層的なものか、皆さんにはお分かり頂けると思っています。今回の能登半島地震でも登場しましたが、震災の度に強調される「つながり」という言葉、山の神様と一緒に暮らし始めて51年が過ぎようとしていますが二人の間の「つながり」、その正体は一体何なのでしょうかね
(3月3日:モモの節句)
【あきらめ川柳】 世の中は 虚像でつながる 社会かな
デニソワ人の嘆き

2月なのに、タオルを絞りながら朝の散歩をしています。皆さんお住まいのところもそうでしょうが京都でも日中気温が20度を超す日があり、ウグイスの初鳴きは20日でした。群馬では夏日も出現しています。昨年のCOP28(国連気候変動会議)では温暖化のティッピング・ポイント(臨界点)が警告されていましたが、どうやらこれを越えたのではないかと案じています。
この警鐘はまた、複雑化が増す一方の現代文明が崩壊する可能性を示唆するものでもあります。もちろん、5年や10年で崩壊するとは思いませんが、100年という単位で見ると危うさを感じるのは私だけでしょうか。
例をあげてみましょう。物流の危機です。これはなにも物流の2024年問題で揺らぐ日本国内に限った問題ではありません。もしトランプが再選されれば世界物流ネットワークの分断化が加速されるでしょうし、パレスチナ問題も紅海におけるフーシ派の船舶攻撃を誘発しています。ロシアのウクライナ侵略は穀物流通を分断しましたし、対するEUのロシアの石油・ガスに対する遮断も物流を妨げています。古代ミケーネ文明やヒッタイト文明が滅びたのは干ばつや地震などの天災に加え、物流システムが機能しなくなったからだという説がありますが、主食ですら自給できない日本は気候変動や物流遮断に対してもろい国なのです。
今から30年前、1995年に封切られたケビン・コスナー主演の「ウオーターワールド」という映画があります。南極と北極全ての氷が溶けてしまい、地球が文字通り水で覆われた未来を描いたSF映画ですが、人類の一部は既にエラ呼吸をする(ミュータント)ようになっており、伝説の「ドライ・ランド」を見つけたコスナーもその一人。荒筋はここまでにしますが、シュノーケリングでも深いところを見るとぞっとする高所恐怖症の私は、エラ呼吸をして海には住みたくありません。
それはさておき、実際に文明が崩壊する過程では、映画に描かれた暴力やイスラエルが攻撃を繰り返しているガザ地区のような人倫に背いたような事態が頻発することでしょう。歴史は繰り返すといいますが、アイスランドの火山が1000年ぶりの活動期に入ったと伝えられていますし、日本の西の島でも陸地が拡大し続けています。2011年の東日本に続き今年の元旦には能登で大地震が発生しました。地球のプレートは活動期に入っているのかも知れません。また気象庁の長期予報では、今年も昨年以上の高温の夏が警告されています。
物流で相互依存をしていた古代青銅器文明は、海の民(不詳)の侵略でほぼ同時期に滅亡しています。これには地球規模の環境変化(乾燥化)も関係しているようですが、もしトラが現実のものとなれば世界の分断は加速化するでしょう。私がお釈迦様と同じ80歳で入滅したいと願うのは、このような理由からなのです。合掌!
(2月23日)
【自虐川柳】 冬がなく 夏はびこりて 人枯れる (デニソワ人)
政治はFamily business

安倍派のパーティー券裏金問題に端を発した自民党の政治資金問題ですが、岸田派が派閥解散宣言をだしたら安倍派も二階派もアルゴリズム行進体操のように右ならえで笑えます(Eテレ、ピタゴラスイッチ参)。それにしても10年一日の如く、どうして日本の政治は変わらないのでしょうか。その理由は政治がFamily businessだからです。
人間のパーソナリティのベースには気質がありますが、気質は遺伝性の素因が強いとされています。いつもいうように人は社会的ヒト、つまりHomo Sociusですから社会との接触のあり方が重要です。例えば政治に向いている人は外向性で協調性が豊かな人ですが、結婚は基本、同じ社会的階層の中でまた似たもの同士でおこなわれます。故に、結果として政治に向いている家系というのが出来上がるのでしょう。
有名な家系として、安倍家、麻生家、岸家、岸田家、青木家、小渕家、林家などがありますが、三代続いているのは自民党系が多いようです。どうしてこうなるのかというと、政治には口利き、要するに許認可権がつきものです。ですから周りには当然、コバンザメが集まってきます。コバンザメは選挙の時に手足となって動きますが、サメからのおこぼれが期待できます。首相官邸で組閣遊びをした岸田のバカボンも、コバンザメたちに担ぎ上げられて4代目を目指すのかもしれません。こうして世襲政治が続きます。
でも、よく考えて下さい。もし政治家が、政治活動に関わる金を自分の懐から持ち出しているのであれば、いかに金持ちであったとしても三代も続けば破産してしまうでしょう。ところが現実にはそうはなっていないことは、今回のパーティー券キックバック問題でお分かりの通りです。もちろん他人の財布の中身はわかりませんのでこれは推測の域を出ませんが、政治の舞台にいるとむしろ越後屋からの献金で太っていくのではないでしょうか。だから私は彼らを政治家ではなく政治屋(Politian)と呼びます。政治はFamily Businessなのです。
どぶ板選挙という言葉があります。後援会(地盤)、看板(知名度)、カバン(資金)3拍子が揃わない場合は小まめに選挙区の住民と接触をはかり、自分の人となりをアピールする戦術です。これは相当手間暇がかかる面倒な戦術ですが国民は、そういう泥だらけの関係をなんとなく知っているものですから、自分は振るまい飯を食ったことがなくても、政治には金がかかるものだと納得しているような気がしてなりません。
先に述べたように、政治を志す人間には2種類があります。Statesman(政治家)とPolitianです。今のアメリカの混乱はPolitianのTrampがStatesmanであるかの如く、SNSを利用して発信する情報をエンタメとして楽しむ、非大卒大衆層の付和雷同にあります。
同じようなことが日本でも起きています。自民党議員の多くが、選挙の時に統一教会を利用することで当選してきた政治屋ですし、22年度の政治資金収支報告書金額欄を二重線で消した荻生田議員や、統一教会の推薦確認書に署名したかしていないか記憶がおぼろな、認知症の盛山文部科学大臣もその典型でしょう。蛇足ですが盛山大臣は灘中高・東大法卒の元官僚、岳父は第66代衆議院議長の田村元です。
22年度の政治資金報告書は収入総額から始まり翌年繰越額まで全て二重線が引かれた状態で届を出した荻生田議員、およびその報告書を、災害で領収書がなくなることもあるからとこれを認めた松本総務大臣。とにかく今の国会議員は議員の体をなしていません。だから何年経っても日本の政治には、デジャブ感が付きものなのだと思います。でも、一番の問題はこういった議員を許している日本の国民かもしれませんね。
以下、Eテレの『アルゴリズム行進』歌詞を引用し、この稿を終わります。いつまで同じ事を繰り返せば気が済むのでしょうね、日本人は。
一歩進んで 前ならえ/一歩進んで えらいひと/ひっくりかえって ぺこりんこ
横に歩いて きょろきょろ/ちょっとここらで 平およぎ/ちょっとしゃがんで 栗ひろい (以下、略)
(2月10日)
【イヤミ川柳】 また出たと 国民うんざり 貂の皮
トラ姫様 おかんむりの巻

今は吉田神社節分祭の最中で在宅していますが一月末には例年通り、熊本へ晩白柚の買い出しに行ってきました。但し、トラ姫様のお世話をしてくれていた教え子の都合がつかなくなり、去年から一泊が精一杯。今年は孫娘に世話を頼んで出かけました。
28日夕方5時半に帰宅し、山の神様が寝室にお入りになりましたが、下りてきて「お父さん、布団にウンコがしてあるよ」とおっしゃいました。お腹立ちだったのでしょうか、ニャンと二度目のウンコです。
ま、考えて見れば我が家はネコ本位制度。トラ姫様がおっしゃることは全て、羊(執事)がお手伝いします。姫様が3階のベランダに出るとおっしゃればドアを開けて待機。座布団が入用とおっしゃれば太ももにブランケットを巻いてテレビの前に。書斎に行くとおっしゃればこれまたあぐら姿勢でお迎えして、私が立ったら必ず暖まっている座布団を占拠なさるので、戻ってきたときは横に置いてある昔の食卓椅子に座って席をお譲りします。このように便利な羊がいないのですから大層ご不便をお感じになるのでしょう。でも、布団の上でウンコするのは堪忍してよ、ホンマ!!
臨時使用人と自称している孫娘の置き手紙には、「トッピングは食べはるものの(ここ、関西弁です)、“メインディッシュ”は残されてます。まったく贅沢なおネコ様です。(中略)おネコ様は主探しの旅に出ていて、ほとんどリビングにはいませんでした。力不足ってか!!?」と記されていました。
孫娘は同志社の国文に在学しているのですが、最後に短歌が詠まれていました。曰く、
“めぐりあひて ごはん食べるも そこそこに 雲がくれにし お猫様かな”
不思議ですね。孫は私が時々ブログを書いているのは知りませんし、ましてや川柳や狂歌を詠んでいるなど知る由もないのですが。末尾には、「1回5千円は 私がぜいたく病になるから、遠慮しておきます。代わりにミカン頂きました」と書かれていました。
(2月3日)
【シン・短歌】
時ながれ 一句詠むまご ここにあり 血のつながりぞ 不思議なるべし
雪が降りました
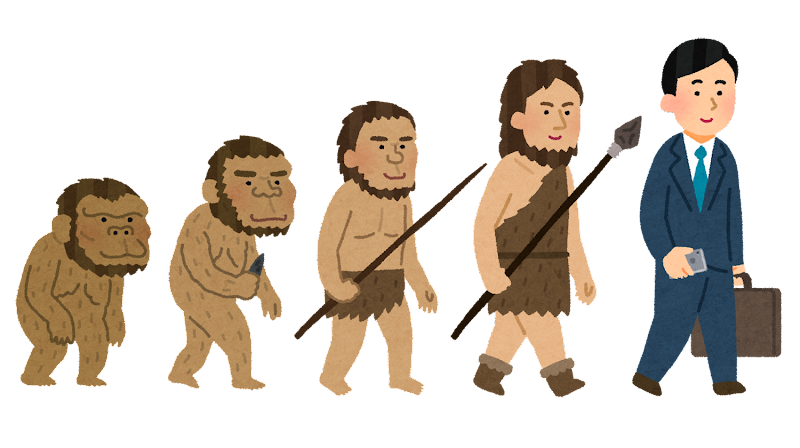
小雪がちらつく中、例のTシャツ散歩をしていたら出会ったイヌがじ~っと私を見つめているので、「不思議そうに見てますね」と飼い主のおばあさんに声かけしたら、「長袖、持ったはらへんのやろか?」と返答が帰ってきました。大笑い!こういうセンスは好きです。
日本人のルーツは複雑です。昨年末、NHKの番組{フロンティア}でその起源の一つとして、タイ南部の密林地帯に住む少数民族「マニ族」を紹介していましたが、現在では日本列島に渡来してきた人たちは幾つかのルートがあると考えられております。しかし渡来に至る前にも様々な交雑があるはずですし、同じルートをたどったとしても前期・後期では異なる可能性もありますから、結構複雑な混血で現在日本人が出来上がっていることは間違いありません。
前回、寒さに強い私は、シベリア中部に住んでいたデニソワ人(旧石器人)の遺伝子を継承している縄文人系列なのだろうと言いましたが、25日には1センチ弱の降雪がありました。雪に気がつかずにTシャツ散歩に出た時もありましたが(15日)、25日は裏庭にも積もっていましたので散歩は中止。トラ姫様が、ゴロンゴロンをするから三階のベランダに出るとおっしゃったのでお外に出ていただき、爺のお節介で少しだけ雪の上をお歩きになりました。然程寒いとはおっしゃいませんでしたが、それにしてもネコはどのような起源をもっているのでしょうか。
イエネコの起源はリビア山猫であるというのは定説ですが、ネズミをとりますから農耕の開始と共にエジプトやキプロスで飼育され、やがて船乗りネコが出現して世界に広がっていったのでしょう。童謡「雪」で「ネコはコタツで丸くなる」と歌われたものだからネコは一般的に寒いのが嫌いというイメージがありますが、岩合さんの「世界ネコ歩き」やモンゴルのマヌルネコの生態を見る限り、耐寒能力も結構ありそうです。
尻尾を小刻みに振ってネズミの注意をそらせて捕食する、モンゴル高原のマヌルネコの生態はNHK番組「ダーウインがきた」で放映されましたのでご覧になった方も多いと思いますが、雪が降っても平気です。ネコ好きの私は、彼らがいる旭山動物園にも会いに行きました。ネズミはとりませんがマンモスを捕っていたデニソワ人も、寒さには強いですよ。
(1月29日)
【ノーテンキ川柳】 あせ拭いて 小雪舞うなか 散歩する (デニソワ人)
遺伝子の不思議

2000年1月1日午前0時をもって禁煙しましたが、それまで35年間というもの、政府の財政に寄与するため?に喫煙していました。そのせいでしょうか、2020年に心臓大動脈2カ所に90%の血栓が見つかり、京大病院にて検査を受けましたが幸いなことにカテーテルを挿入することなく、毎月一度の定期チェックと服薬で済んでいます。私はおおよその死期が自分で判断できる癌を死因としたかったのですが、そういう訳で3年後の80歳、胸キュンの「いい日旅立ち」(曲:谷村新司、歌:山口百恵)を予定しています。
それはそれで良いのですが、1月の定期検診のためクリニックを訪れたところ、着膨れした年寄りの多いこと。とにかく2023年度は6人に一人が後期高齢者(16.1%)ですから、世の中、年寄りで満ちあふれています。当然、医療費は増加し、逆に経済力や生産性は低下する一方ですが、老人であふれている待合室でふと、中学生の時に集団鑑賞をした映画「楢山節考」(原作:深沢七郎)を思い出しました。古くから老人問題は存在したのです。
それはさておき、天気予報では寒い寒いと脅していますが京都はまだ氷は張っていませんし、私は例年通りTシャツで散歩しています。こんな私ですから逆に、これでもかとばかりに着ぶくれした人たちの健康を心配してしまいます。私のように寒さに強く暑さに弱い人間は今や絶滅危惧種ですが、どうして寒さに強い人と弱い人ができるのか、皆さん不思議に思われませんか?
2022年3月に、寒さに強い・弱いは出生後1年間の生活環境に依存するとの論文について触れましたが、当然、遺伝子もこれに関係してるはずなので、改めて文研を調べてみました。すると約30%の人が筋肉の瞬発力に関係する遺伝子変異をもたず、その代わりに持続的に筋緊張を高めて熱をつくり出し、寒さに耐えることが出来るそうなのです(Wyckelsma, et. al., AJHG. 108, #3)。
もう一つの可能性として、これはイヌイットの人たちや日本の縄文人などに、旧石器人のデニソワ人(シベリア中部デニソワ洞窟で見つかった旧人)の遺伝子が伝わっているといわれていますが、私もデニソワ人の遺伝子を継承しているのかもしれません。でも地球温暖化の今、こういう人間は絶滅危惧種でしょう。まぁこれは今の世、もっきの幸い優曇華の華でもありますが。
(1月20日)
【自虐川柳】 どこみても じじいとばばあの 令和かな (字余り)
馬齢を重ねて77年、前途多難な辰年
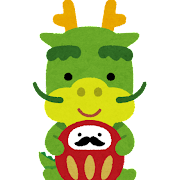
正月から能登半島の大地震やJALと海上保安庁機の衝突など、今年の幕開けも前途多難を予感させています。被災された方々には、心からのお見舞いを申し上げます。
株式相場の格言では卯跳ねて辰巳天井、今年も株価は上昇とのことですが、もしトランプが再選されるようなことになれば世界の混乱はますます増幅されるでしょうし、詐欺や他者操作を目的としたフェイク情報が一層増加しそうな予感がします。今回の地震でもすぐにフェイク情報で金を振り込ませる詐欺被害がでているとか。人間ってここまで悪くなれるものなのかと、あきれ返ってひっくりカエルです。
それはそうと私にとって今年は77回目の正月でした。信長時代の人間50年と比較すれば現在は人間100年の時代。65歳を定年の時間と考えれば、100年まで35年が残ります。この時間をどう生きるか、難しい課題です。ユングは「終わりが人生の目的」と言いますが、体力的に衰えていく中での35年はなかなかの時間です。またエリクソンは、老年期は「英知を統合していく時間」とポジティブに総括しますが、問題は体力の衰えです。精神一到何事か成らざらんで、老いても意思の問題ですから気力は何とかなるのですが、目や耳、5~60年といわれる歯の寿命はニャントもにゃりませんニャ。
正月には娘や息子家族が来ますし2日は例年5人ほどの来客もありますので、暮れの31日、朝8時から台所に立ちおせちを作り始めました。ところが今年は4時を過ぎた頃からだんだん腹が立ってきました。山の神様は飲みながらやらないから腹が立つのよと仰いますが、私は体力の衰えであると思っています。5時に終わって飲み始めたら、確かに機嫌は収まりましたが、ワハハ!
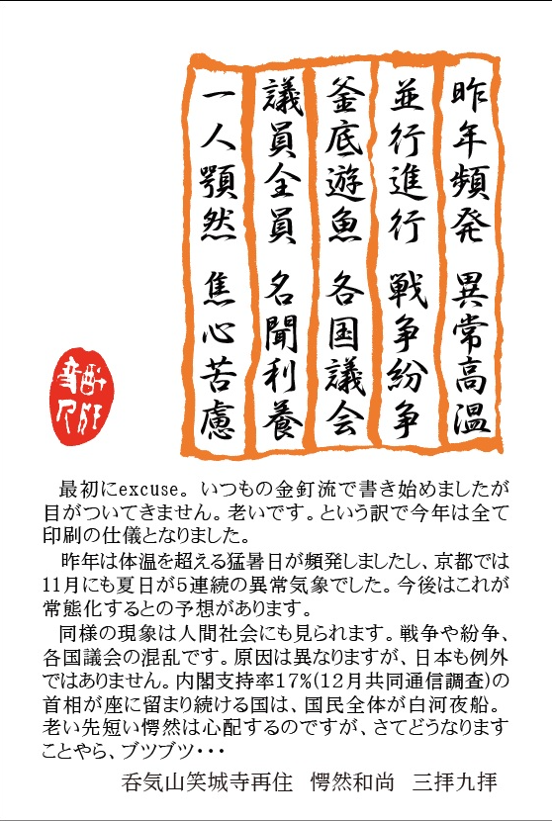
職業的発達段階論を提唱したスーパーは、65歳以後を「義務からの解放の時間」ととらえています。大学教員は通常、65歳とか68歳とかの定年後も特任教授として70歳まで勤務するのが普通なのですが、私の場合は理事長のご機嫌を損ねましたので延長がなく、お陰で義務から解放されました。大学院の学生がいましたので一年だけ非常勤で勤務し、その年に今の別荘を購入して、66歳から自然のまっただ中での涼風生活。今年も4月第一週月曜から別荘を開け、6月半ばから9月半ばまでは飯田高原にて過ごす予定です。
別荘の西側には小さな谷を挟んで杉林がありますので、秋分の日前後から2時半を過ぎると日が陰ってしまいます。こういう立地ですので夏の暑さは完全に防げるのですが、精神的にはやはり日照時間が長い方が明るく、秋風が吹き始めると京都に帰りたくなります。吉田の家は、ネコの額ではありますがナツメやヤマボウシが植わっている南向きの庭に加え、3階にサツキを植えたトラ姫様の庭がありますので大変明るく、気分も晴れるのです。
まぁこうやって今年も飯田-京都間を行ったり来たりしながら、「解放された時間」を楽しむつもりです。私の年賀状、添付しておきます。お笑い下さい。本年もよろしくお願いします。
(1月3日)
追記:昨年、虫歯で右上第二小臼歯をなくしたら味がよくわからなくなりました。そこには入れ歯が入っているのですが、下の第一第二大臼歯が弱っており、うまく噛めないのです。味覚はこういう些細なことでも変化してしまうことを実感しています。そういう次第でおせちの味にも自信がなくなり、来年からは家族以外の来客は受け入れないことにしました。これで腹も立たなくなるでしょう。ワハハハハ!
【ノーテンキ川柳】 ひねもすの 始まり終わり のたりかな
冬至の夜は温泉で

やっと冬が来ましたが、今年は猛暑の年でした。加えてハマスとイスラエル、ウクライナとロシアの戦いは終わりの姿が見えません。前者はハマスの奇襲攻撃に端を発したのですが、そこに至る長い伏線がありますし、イスラエルにしても第二次大戦後の建国の歴史やら何やらの入り組んだ伏線があるようです(NHK BS「青い募金箱:イスラエル建国の真実」参)。
私たちは単純にハマスとイスラエル両者の共存を望みますが、両者の間にはそれぞれの「神様」及び建国の歴史などが絡んでいるだけに、マイ・カミサマの日本人には理解しにくいことが多々あります。もう一つのウクライナとロシアの戦争は、一方的にロシアに非がありますが、彼我の国力の差からして守勢に回らざるを得ないウクライナが気の毒です。考えて見ればこの2つは共に、「イエス」を信仰する国なのですが。
ところで我が国では、もっと矮小な問題で国民が呆れかえっています。国会議員の裏金作りの手法が白日の下にさらされ、天下国家ではなく個人の利殖に走る議員の姿が赤裸々になりつつあります。これは選挙の際、手足に支払うお金であるとか言いますが、旧統一教会や創価学会、日蓮宗や霊友会、神道政治連盟など多くの宗教団体との癒着や組織票をあてこんだ自民党という党のもつ暗闇部分なのでしょう。マイ・カミサマの日本人には宗教という文脈の理解は苦手なのでしょうが、やはり今一度整理をしておく必要があるのではないかと、愕然は考えています。
考えるのには才気と元気に加え根気が必要ですが、ノーテンキの愕然も年が明ければ満77歳。評論家的思考はまだ可能ですが、だからどうすれば良いのかという大所高所を熟考するエネルギーはなくなりました。という訳で今年も、日本海側に大雪警報が出された22日、「冬至の日は温泉」の旅に出てきました。恒例になっている川棚温泉フグコースと唐戸市場買い出しの旅です。
仔細については昨年お話ししていますので割愛しますが、川棚温泉の温めのお湯にゆっくり浸かりながら一年を回顧する旅は、京都光華女子大学を退職した2012年からスタートし、今年で11年目。但し14年はハウステンボスにてロブスターを食べるクリスマス、翌15年は孫同伴のハウステンボスだったようですが、その孫も今や大学二年。ということはその分こちらが老いたということです。
世の中には苦しんでいる人たちも多くいるわけですが、浮世の憂さを忘れてお湯に浸かるのは老人の特権であると合理化しています。ウクライナやガザの人々、御免なさいネ。そういう次第ですのでこの年末は、川棚温泉を愛した自由律俳句の山頭火に倣い、へぼ川柳三題にて御免被ります。皆様、良いお年をお迎え下さい。加えて来年こそは世界に平和が訪れますように。ついでにトランプが大統領に再選されませんように。
(12月24日)
【反戦川柳】 戦うな 雪が一片 頬に落つ
【皮肉川柳】 我のみが 正義なりけり 今の世は
【下品川柳】 クソ溜めに トランプおちる 良き日かな
走ら(れ)なくなった師走の和尚

京都は12月に入っても最高気温が20度近い暖かい日々が続いています。例年よりも明らかに季節の進み方が遅いのですが、吉田山の散歩道にもやっと落ち葉が積もり、歩くとカサコソという音がするようになりました。しかし猛暑のせいでしょう、吉田山のコナラは実をつけませんでした。例年なら11月になりますと、絨毯を敷いたように沢山落ちていたのですが、今年は落ち葉のみ。もしクマさんがいたならお腹をすかせて大変だったろうなと思います。暖かいから冬眠も出来ませんしね。
ですからTシャツ一枚での散歩も楽ですし、汗もかきますのでタオルは必携の品。その代わり手袋は要りません。汗を拭うときに邪魔ですしね。ただ日の出が遅くなった分出発も遅くなり、子どもたちの通学時間に重なるようになり、追い越されることが増えました。中学生に追い越されると見る見る距離が離れていきますし、先日、久しぶりに銭湯に行って帰りがけ、腰の曲がったお婆さんに追い越されてしまいました。
飯田における夏の散歩では山の神様にも追い越されます。私と山の神様との間には体重で1.6倍ほどの差がありますから、歩行速度と体重の間には何らかの相関関係があると睨んでいるのですが、合理化ですかねこれは。調べてみると秒速1.6mの人は95歳定年、秒速0.8mは80歳定年とのことで、歩行速度が速いほど健康寿命は長いらしいです。95歳はしんどいので80歳(後3年3カ月)を目標に頑張ります。
ところで私はこれすべてカラスの仕業であると思うことにしていますが、拾っても拾っても吉田山界隈のゴミがなくなりません。最近では一週間に3~4回拾っているのですが、行く度に新しいゴミが落ちています。BB弾というのですか?子どもたちがオモチャの銃で撃ち合って遊ぶためのプラスチックの弾もあちこちに落ちていますし、相変わらずマスクも吸い殻も落ちています。無論、諸種包み紙、レシート、おしぼりなどナプキン類、箸袋に爪楊枝、ティッシュなど、一通りの家庭ゴミは落ちています。
ただ困るのはお酒のワンカップのガラス瓶とその蓋。酎ハイの空き缶なら、公園においてあるジュースの自動販売機の回収ボックスに投入できるのですが、ガラス瓶は無理です。カラスがラリーをするとも思えませんが、壊れたラケットや運動靴なども放置されています。ですからこういう類いは意を決して改めて拾いに行き、自宅で処理します。そういう訳で、お爺さんは決して暇を持て余すことはないのです。都会は忙しいですね。
(12月10日)
【ノーテンキ川柳】 師走だが 走れぬ和尚 牛歩かな
トラ姫様御不興の巻
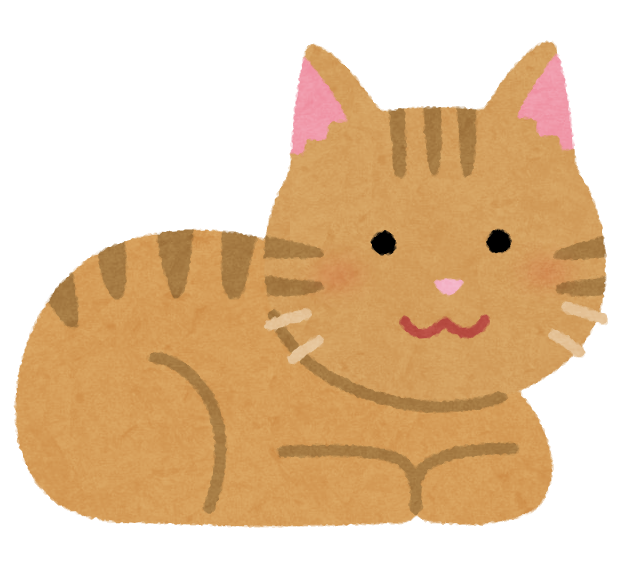
飯田高原は18日土曜日から雪になり、日曜朝には庭や木の枝に2~3センチほど積もっていました。当日、中津川駅で山の神様をピックアップするため下山しましたが幸い凍結はなく、無事帰宅しました。以前は勤労感謝の日を目処に閉めていましたが、最近は一週間早め第4週月曜日と決めています。しかし雪が降ったことはなく、前回のぼやきがリアルになりました。飯田は南信州ですので暖冬の年の方が降雪は多いようです。
ま、何はともあれ再び京都での日常が始まったのですが帰宅した月曜夕方、姫様のお出迎えがありません。おかしいなと思って二階の寝室に行きましたが姿が見えません。トラ、トラとよびますとニャンという声が、ベッドの下から返ってきました。これは初めての経験!わらわを放置してひつじはどこにいたのじゃ?ということでしょうか。まぁご機嫌斜めでした。すんません!ペコリ。
留守中のご飯とトイレ掃除を頼んでいた孫娘の報告では、ニャ~ニャ~(ひつじはどこじゃ?)と探していたそうです。私は6日間、お年寄り様におかれては一晩だけの留守だったのですが、急に冬が来ましたので「布団がいない」と、お困りだったのかも。
これには後日談があります。23日朝目覚めると布団の上に、ニャンとウンコよんこ(早口言葉初級編)。下のトイレまで下りるのが面倒だった?しかし私の布団の上にする必然性はないと思うのですが。姫様も人間年齢換算では68歳、年があけると72歳になります。エーザイが開発した、認知症の進行を遅らせる効果をもつレカネマブの処方対象になったとは思いたくないのですが、いやぁ~、マイッタ参った。以来、ご機嫌取りに終始しております。
しかし人もネコも老いには勝てません。今年の春先、右上第2小臼歯が虫歯でコロリと抜け落ち、左下第2、第3大臼歯を加えて義歯3本の状態なのですが、右下第3大臼歯(奥歯)がしっかりしていないので、強く噛むことが難しく、ステーキ肉をかみ切った後は丸呑み状態。歯がこういう状態になると味覚は随分と落ちるものですね。沢庵ポリポリの時代が懐かしい!食べ物というものは何度も咀嚼して始めて味がわかるのだということが、歯を失って始めてわかった次第。朝の散歩は未だにTシャツ1枚なので人からはお元気ですねと言われますが、歯の状態は外からは見えません。皆さんも歯は大切にしてくださいネ。
(11月28日)
【ボケ川柳】 下駄の歯の 欠けたる如し 食べにくさ
晩秋の沢城湖

ガザ地区やウクライナ情勢で、めっきり報道量が減った地球温暖化問題ですがその速度は速まる一方で、今年は夏日(25度以上)が出る日が3月に始まり11月までと、一年12カ月の3/4になってしまいました。世界気象機関(WMO)の発表によると(2023,11,8)来年度もエルニーニョ現象が継続し,今年よりも更に暑くなるそうです。汗かきの私にとっては最悪のニュースです。
まぁしかし死ぬまでは生きていなければならないということで、今年も別荘を閉めるために飯田にやってきました。真如堂の紅葉はまだ半分ほどが青いままですが、標高900mですので、さすがに落葉樹はほとんど葉を落としています。沢城湖のモミジもきれいな紅葉は終わり、葉が枯れた赤色です。修学院離宮の外土居に生えていた実生を持ち帰り、鉢で育てた後移植した庭のモミジも同様でした。
面白いのはオー・ヘンリーの『最後の一葉』ではありませんが、軒下にのびたエゴノキの枝です。軒にかかっていない場所の葉はすべて散っているにもかかわらず、軒で保護された葉は黄色くはなっていますが、僅かに緑を残した状態でしっかりとついたまま。庭にはウワミズザクラや白樺、檜などの大木も生えていますが、エゴノキやアブラチャン、コシアブラ、タラ、山椒、ソヨゴなど、皆さんは多分ご存じでない低灌木も沢山生えています。昔はエゴノキの若い実の皮を石鹸代りに使ったそうですし、アブラチャンの果実や樹皮の油を灯油代わりにしたとか。コシアブラやタラの芽は天ぷら材料ですが、私は天ぷらはあまり食べませんので味は知りません。トゲが厄介なタラの木は、浄化槽設置時に全て抜いてしまいました。
今朝(16日)の室温は4度6分でしたが、さすがの私も布団から出るのに躊躇しました。散歩中の5度は身体が温まってくるとなんていうことはないのですが、パジャマを着替えて石油ストーブをつけ、その前にへばりついたとしても温まるのに時間がかかりますからね。
朝食はヨーグルト2種類、バナナ・富有柿・ミカンのフルーツで済ませ、8時から落ち葉掃除を開始。前回で懲りていますので今回は無理な姿勢にならないように気をつけて、熊手でかき集めた枯れ葉を手で拾い、竹製の箕にほり込んで、お隣さんから縄文人とからかわれた石囲いの償却場で燃やします。乾いているようにみえても一枚めくると濡れ落ち葉ですから、これをきれいに燃やすのにはテクニックが必要で、玄関までのアプローチを片づけるのがやっと。明日は雨との予報なので、できた灰を庭木の根元に撒き終わったのが4時半でした。
まぁいつものことですが庭掃除は大変です。吉田のようにネコの額の広さなら簡単ですが、300坪は辛い!しかも、整骨院に通う必要が生じた斜面部分もありますからネ。という訳で、今日は雨を見ながらコーヒーを楽しんでいます。今、カケスが尾羽の白い部分を見せて飛んでいきました。昨日はヤマガラが数羽、遊びに来ていたのですが。
(11月18日)
【アツガリ~ノ川柳】 秋飛ばし 突然の冬 ほっとする
慈悲の心と善の綱

ガザではハマスを滅亡させるというイスラエルの強い決意の下、爆撃によって一般市民や子どもたちが死に追いやられています。またレバノンに拠点を置くヒズボラが対イスラエル戦への参戦を明示し、戦争の拡大が憂慮されています。どうしてこういう事態に至るのか、マイ・カミサマをもつ日本人の多くには理解しにくいと思いますが、基本にユダヤ教徒とイスラーム教徒の宗教対立があることは皆さんがご承知の通りです。でもどうして、二つの宗教は対立するのでしょうか。
以下はマイ解釈ですので宗教学的に正しいかどうかはわかりませんが、ユダヤ教とイスラーム教がそれぞれ神であると明言するヤハウエ(ユダヤ教)とアッラー(イスラーム教)は、名前は異なるものの同じ「唯一神」です。神が2つあれば、唯一神ではありませんから当然ですが。だから素人解釈ですが、それぞれの信仰の根源にある預言者モーセとムハンマドの言葉(律法)に対する解釈の違いが、二つの宗教の創始につながったと思っています。
加えて、絶対神を主張する最大勢力としてキリスト教があります。このブログをお読み頂いている皆様方のなかにも、キリストが神(イエス)の子であり神そのものである(三位一体説)と信じていらっしゃる方も当然いらっしゃると思いますが、イエスも唯一神ですから、そうすると論理的には三者の「神」は同じということになります。でもそれぞれの立場からすれば、相手が信じる神は異端なのでしょう。三面鏡に同じ神が写っているのですが、見ている面によって異なった像が顕現されているのだろうと、私は思っています。
ただ「唯一神」の困ったところは、自分たちの信じる神が絶対でありお前たちの信じている神は異端であるから、これを滅ぼすのは聖戦であるとして戦争を引き起こすことです。イスラームに対する十字軍がそうでしたし、あるいは同じキリスト教徒でありながらカトリックとプロテスタント間で戦われ、800万人以上の死者を出した三十年戦争、イスラーム教のスンニ派とシーア派の対立など、宗教が原因で発生した戦争は枚挙にいとまがありません。その点、日本人の主流である(と、私は思っています)マイ・カミサマの場合、どのカミサマがより効率的に願いを叶えてくれるかですから、戦争にはならないのがいいですね。まぁとにかく、一刻も早くこの戦いが収束して欲しいものです。
閑話休題 私の朝の散歩コースは吉田山界隈ですが、紅葉の名所として知られている天台宗の真正極楽寺(通称、真如堂)と、浄土宗大本山金戒光明寺が含まれています。共にご本尊は阿弥陀如来ですが真如堂のそれは「うなずきの弥陀」と呼ばれており、女人禁制であった比叡山から女性救済のために京の街に下山された有り難い弥陀であるとか。11月15日は「お十夜」のご開帳日であり、10月末からご本尊に結ばれた白い綱が境内に設置されています。
綱は「善の綱」と称されておりご本尊様の右手につながっているので、これを握って「南無阿弥陀仏」と唱えれば死者への回向ができますと書かれた紙がぶら下がっています。ですから仏教徒として育った私には「盲亀の浮木優曇華の花」。このコンビニエンスなツールを使って朝の散歩の途中、31年前に旅立った母親と28年前に旅立った父親の冥福を念じています。
前にも書きましたように私は、神は人類の発明であると思っていますので神頼みはしませんが、人々に慈悲の心が育てば世の中の争いごとはなくなると思っています。だから善の綱を握りながら南無阿弥陀仏を唱えています。私は臨済宗南禅寺派の末寺で育ちましたので、本当は南無釈迦牟尼仏と唱えるべきなのでしょうが、ま、南無阿弥陀仏でもいいでしょう。
ところで皆さんはイギリスの獣医、James Heriot先生の話をお読みになったことはありますか。確か『ヘリオット先生奮戦記』だったと思いますが、“all creatures must be love”(生きとし生けるもの、みな愛おし)という言葉があります。これは仏教でいう慈悲の心と同じではないでしょうか。もしネタニヤフやプーチンに慈悲の心があれば、今の二つの戦争は起こっていなかったと思いますが、二人とも私のようなノーテンキ型単細胞ではなく権謀術数型でしょうから、共に10年戦争になるのかも知れません。
近未来、AIが人類さえいなければ地球は平和になるという結論を出さないことを願うばかりです。
(11月5日)
【ノーテンキ川柳】 願い事 頼むカミサマ みな違い
今年もジョウビタキがきました
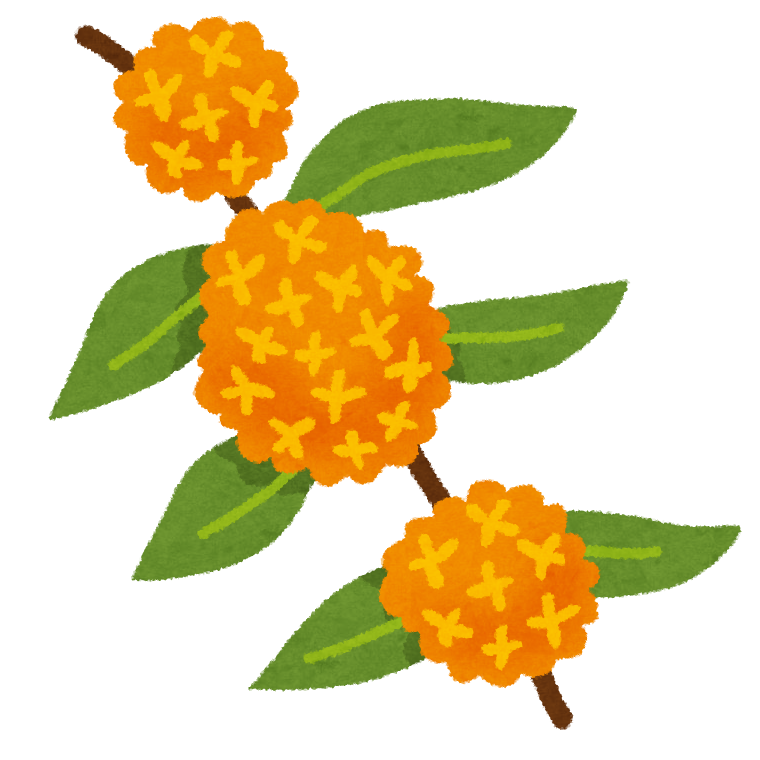
23日朝、吉田山を散歩していたらジョウビタキに会いました。お腹が茶色で黒の羽の後部に白の斑点をもつジョウビタキは、非常にわかりやすい冬鳥ですので、皆さんもご存じかと思います。最近では、日本国内での繁殖例も確認されているとか。渡りは基本、食べ物を求めてのはずですが、ジョウビタキの主食は虫。地球温暖化は、ジョウビタキの主食になる虫の生息環境を変えたのでしょうか。それともジョウビタキが怠けものになり、「ま、いいか」で通年滞在になったのでしょうかねぇ。
ところで皆さんのお住まいの地域では、今年は金木犀の香りがしましたか?毎朝の私の散歩コースには少なからぬ金木犀の木があるのですが、香りを意識したのは前日夜から午前3時頃まで雨だった今月15日の朝のみでした。木の真下を通って鼻先まで枝をたぐり寄せても香りを感じないのです。今年の夏の異常高温と少雨の影響で、木が弱っているのではないかと思います。
ネコの額の裏庭には二羽ニワトリはいませんが、コウヤマキともみじ、ナツメに加え、オオグミを引き抜いた後に植えたヤマボウシがあります。このヤマボウシの根元にはミョウガが沢山生えており、毎年、味噌漬けをつくっていましたが、今年飯田から帰宅してみるとミョウガは枯れており全滅。植えてから3年しか経たないヤマボウシも葉が傷んだ状態でした。今夏、7月の京都は38度越えが4連続日、8月も4日あったようですので裏庭は干ばつでやられたようです。自宅前の駐車場に置いたプランター類は、アルバイトで孫に水やりを頼んでいますし、3階の庭は給水装置で毎朝灌水していますので無事ですが。
ただ、8月末頃のように思いますが息子から電話がかかってきて、川端署から3階の給水装置が壊れているのではないかという連絡がきたとの話。散水音が途絶えないので水が漏れているのではないかと、お隣さんが川端署に連絡をして頂いたようで大助かり。隣近所とは、常日頃から仲良くしておくものだということを実感させられた次第です。
しかし日本の警察は素晴らしいですね。中京区にある息子宅の電話番号を探して、連絡してくれるのですから。お話ししましたように荘厳という名字は日本でわが家だけ。田中や山田、佐藤などの名字は数があるでしょうから、連絡がつくかどうか。その代わり悪いことも出来ませんが。ワハハハハ!
外出時は今週まで半袖シャツでしたが来週からは長袖になりそうな温度です。帰京以来どこにも出かけていませんので来週にでも長浜に行き、「翼果楼」の鯖そうめんでも食べに行ってこようかと思っています。そういえば先週お昼、孫が来たときに鴨せいろ(鴨汁蕎麦)をつくったら、残った出汁を持って帰りました。美味しいと感激していましたから、私の料理の腕も上がったかな?
(10月28日)
【ノーテンキ川柳】 孫が来て 味を褒めたと えびす顔
ガザでは大変なことが起きています

皆さん既にご存じのように、ウクライナだけではなくパレスチナのガザ地区でも戦争(といってもいいでしょう)が始まり、町が破壊され沢山の難民が出ています。ガザは東西10キロ南北40キロの区域でほぼ種子島の大きさ、東京都区部の面積比で約6割と見積もられていますが、ここに220万の人が住みその半数が北部地区から南部地区への移動を強いられているとか。
私は常々、万物の創造者「神」は人類の最大の発明であると断言していますが、ユダヤ・キリスト教徒であれイズラ~ム教徒であれ、神は唯一無二の存在。でもその神に対する解釈が、信じる宗教によって異なるのだと思います。解釈のあり方はお互い譲れないものなのでしょうが、もし「神」がいるのなら互いの間の争いを止めさせて欲しいと願います。しかし過去も含めて現実には争いがなくなることはありませんでしたし、今後ともないでしょう。ということは三段論法的に、神はいないということになるのですが、はて?
ご存じのようにインドを含め東南アジアは多神教文化ですし、慈悲を重視する仏教には十字軍やジェノサイドのような一方的な暴力が成立する要素はないと思います。でもどうしてインドや東南アジアには一神教が成立しなかったのでしょうか。私はその理由は、モンスーン気候という風土にあると考えています。地中海気候のように空気が乾燥していると、空から誰かに見下ろされているという気持ちになるのでしょうが、アジアのように高温多湿な環境では見下ろされている感は成立しなかったのでしょう。
だけれども洋の東西を問わず、人間誰しも困ったときの神頼みで、特に日本人は古くからマイ・カミサマに様々なお願いをしていたのだろうと思います。だから日本には、八百万の神様がいらっしゃる訳です。このような土着の多神教文化と、後に日本に渡来してきた個人の「悟り」を重要視する仏教を精神的背景にもつ多くの日本人には、名前こそ異なるものの同じ神の下にある、イズラ~ム教徒とユダヤ・キリスト教徒の争いを理解することは非常に難しいと思います。少なくとも私にはわかりません。ですから争いを止めなさいと言っても、それが出来ない理由がわかっていないのですから、課題はトートロジーになってしまいます。
私の友だちにキリスト教徒がいます。彼によると教会の神父さんから毎日、「イスラエルのために祈って下さい」というメールが届くそうですが、私にとってこのキリスト者のロジックは理解できません。私は同志社大学で学びましたので教養の必須科目として、正確な科目名は忘れましたが、宗教学がありましたし聖書は一通り読みました。
で、今更なのですが幾つかの言葉を覚えています。その一つに『マタイ伝』第5章30説の「右の頬を打たれたら左の頬を差し出しなさい」があります。真意を調べてみますとこれは巷間で流布している解釈、つまり悪に対しても非暴力・無抵抗を貫きなさいということではなさそうです。イエスのこの言葉は、アウグスチヌスの解釈によると肉体的な「善きもの」を犠牲にしても霊的な「善きもの」を守りなさいという意味だとか(林 明弘、2002.川崎医療福祉学会誌)。肉体を否定しても実体のない霊に忠実であれというのですから、慈悲もヘチマもないことになります。
輪廻転生があるとは思っていませんが、死ねば皆仏と思っている私にとって(善人であっても悪人であっても、死は平等)、どうも一神教の考え方は馴染めません。私は、人間は人間であり矛盾をかかえた存在であると思っていますし、内省によって矛盾を少なくする、つまり難しいですが「悟り」に至るのがあるべき人間の理想であろうと思っています。万人に等しく死は訪れますので、別に神様は必要ではないのです。
こういうノーテンキ人間ですから、10月12日日経朝刊総合1面記事に藤井聡太さんの八冠達成記事がでたとき、これが総合1面を飾るほどの内容かと思いましたがその後思い直しました。つまり八冠がトップニュースになるということは、日本が平和であることの証なのです。だけど最近の北朝鮮やロシアの動き、あるいは習近平語録の学習が重視されている中国の政治動向などを考えると、いつまでノーテンキでいられることか少々不安です。こういう深い所に不安を抱え込んだままでは、愕然、悟りには行き着けそうにありません。人間という動物には困ったものですなぁ。という訳で、杜甫が二人です(トホホ)。
(10月15日)
【ノーテンキ川柳】 八冠が 紙面に踊る 平和かな
草木が起きる寅の刻

マツタケが顔を出していないかと28日木曜から飯田に来ていますが、長野県も今年の夏は猛暑で雨が降らず、北信の野尻湖では水不足で観光船の発着ができなくなったほど。マツタケの生育には8月に降る適度な雨が必要なのですが、そういう訳で多分ダメだろうなと思いながらの飯田ですが、思わぬことが起きてしまいました。筋・筋膜性腰痛です。
地球温暖化が原因でしょうか、南信の山は猛暑でカラカラに乾いていて雑茸を含めてほぼ全滅のようです。でも、せっかく来たのだから落ち葉でも燃やしておこうと、駐車場から玄関まで15段の低いアプローチに落ちている葉っぱを拾い集めていました。アプローチに落ちる葉っぱ常に踏まれるため砂利が食い込み、私の美的感覚?から見れば汚いのです。アプローチはカーブしていますし段によって高さが異なり、加えて両横からシダの葉っぱが出ていますからしゃがむ姿勢に無理が出るのでしょうね。姿勢変化に伴って腰回りの筋肉が引きつり、『この素晴らしき世界』ではなく跛行状態の『聖者が街にやってくる』になった次第。
え?なんのこっちゃ?私はルイ・アームストロングがしゃがれ声で歌う上記の歌が大好きなのですが、彼の愛称がサッチモ。というわけで、にっちもさっちも行かなくなったという昭和のギャグです。ワハハハハ。
去年は、アプローチにとりつく前の高さ21センチ5段の階段を踏み外して顔から地面に着地し、その時に横腹をすりむいて一か月ほど、特に就寝時と夜中のトイレと起床時に激痛が走って往生したという話をしたことがありましたが、山の生活にはこういう不便があります。「ノーテンキ川柳」で、厄災から逃れるためには二本足が大事だよと言いましたが、筋・筋膜性腰痛ではその二本足が使えません。姿勢や体位を変化させようとする時の痛さは、経験したことがない人にはわからないでしょうが激痛が走り、固まってしまいます。
そういう次第なので3日の起床は午前4時10分。丑の刻から寅の刻に変わって1時間ほど経った頃に目覚め、達磨大師の七転び八起きで起き上がり、ネット検索で整骨院を探して予約し、10時から診断を受けました。結果は骨ではなく、大腰筋・小腰筋・腸骨筋・脊柱起立筋などの腰回りの筋肉痛らしく、筋肉が炎症を起こしているので冷やしなさいという指示です。接骨院は柔道整体師の業務ですが医師ではないため、診断名が出せないのでしょうか、はっきりとした診断名はありませんでした。
ま、しかしこれで原因がわかりました。症状は左側の方がきついのです。散歩をしていていつも会う別荘地の住人に言われたことがあります。私の歩行は跛行、要するにびっこを引いて歩いているという指摘です。原因は左ひざ関節の痛みです。だから左右両方の筋肉に平等に負荷がかかるのではなく、左側筋肉にかかっているようです。
私、中学時代は京都府大会に400mリレー選手として出場した100m走のスプリンターでした。自己記録は確か13秒2だったように記憶しています。顧問は体育の専門ではなく職業科の先生で、うさぎ跳びやら足のどこだったか忘れましたが縄でくくり、もう片方は木に括りつけて縄が切れるまで足を上げ続けろなど、まぁ原始的なトレーニングをさせられ、膝関節を壊しました。その時のひざの故障が今回の事態の遠因なのです。なるほど、納得。
歩くのも大事ですが、その前にストレッチをしておくことが必要なのです。しかし協調運動障害傾向の私に、うまくできるかなぁ・・・?
(10月5日)
【ノーテンキ川柳】 筋肉が 固まる朝は ナマケモノ
注:表題はトラ姫様とは無関係です。要するに腰回りの筋肉痛で、体位変化に伴う痛みで二度寝ができずに朝4時前に目覚めたというだけの事。江戸時代の時刻表示を使ったら寅の刻になりました。
暑さ寒さも彼岸まで
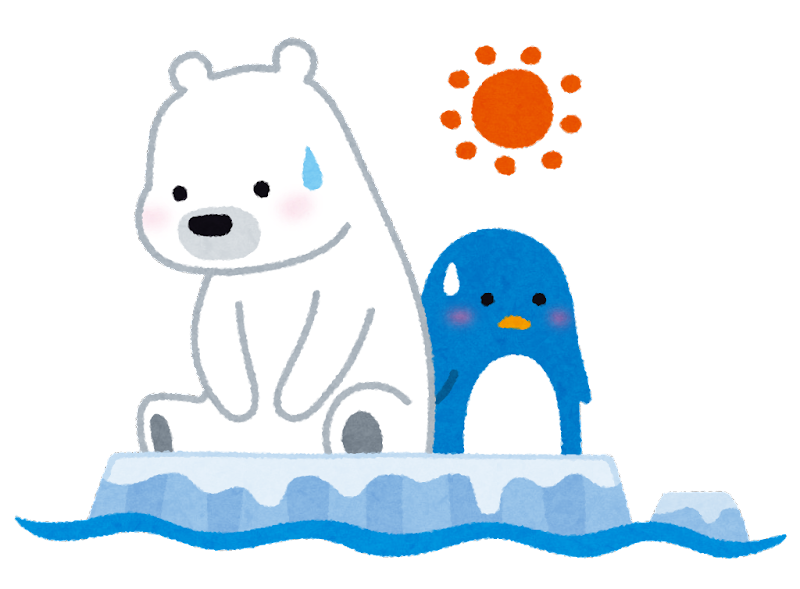
お彼岸の日、朝の京都は曇っていましたので楽に墓参りをすることが出来ました。10日に帰宅して以来、無論エアコンは入れますが夜が寝苦しく、15年以上処方を受けていなかった睡眠薬をもらって入眠していました。しかし彼岸を境に夏と秋の空気が入れ替わり、やっと薬を飲まずとも入眠出来るようになりました。私、暑さには徹底的に弱いのです。
グテーレス事務総長が「地球沸騰化」という言葉を使いましたが、皆さんご存じのように北極圏の永久凍土が解け始めており、大量のメタンガスが放出されています。メタンガスの温室効果は二酸化炭素の25倍なので、これがどんどん出始めると地球温暖化は幾何級数的に加速されてしまいます。自動車をEV化しようと何をしようと、恐らく間に合いません。北極圏のほとんどはロシアとアメリカ領ですがロシアは戦争を始めたし、アメリカも民主党と共和党の政争で、メタンを回収してエネルギー源として利用する事など、全く話題にも上っていません。
ところで産業や生活から出てくる二酸化炭素の国別排出ランキングは1位が中国(31%)、2位がアメリカ(14%)、3位インド(7%)、4位ロシア(5%)で5位が日本(2%)です。排出量ランキングの1,3,4位がBRICS加盟国ですが、この地政学的合従連衡組織では地球環境問題は議論されていません。2024年1月にはサウジやUAEなどが加わり11カ国の組織になるようですが、人口比ではこっちが優位だぜという資源国の集まりで、G7に対抗することだけを目的とした、いわば烏合の衆。ですからBRICS+αに地球環境改善や国際紛争、人権などに対する提言を期待することは無理です。
考えて見ると今は、個人も国もそれぞれが言いたい放題やりたい放題で、共同歩調や共通理解は歯牙にもかけられません。そこで私を悩ませる暑さの原因、つまり二酸化炭素排出量を例としてもう少し具体的に、現在を支配するこのmeism(勝手主義)を考えてみましょう。
中国の人口(14億2590万)は日本(1億2330万)の11.6倍。ですから日本を基準とした中国の二酸化炭素排出量が23%前後ならわかりますが、31%で1.5倍の排出量です。自分の国の原子力発電所からは福島の処理水の8倍のトリチウムを排出しながらイチャモンをつけてくる国ですから、日本も中国に対して地球環境対策をしっかりやれというべきだと思いますが、政府は何も言いません。ダーキシよ、トリチウム問題に過敏な中国の方の不安を払拭するために、我が国が開発した濃度低減技術を貴国の原子力発電所に無償で提供しましょうと、それを言わんで委員会!!!
暑さ寒さも彼岸までから随分話が脱線しましたが、言いたいことは地球環境悪化によって日本も随分住みにくくなったということです。酷暑だけではなく、これに付随して至る所で線状降水帯が発生していますし、気圧変化に連動しているといわれる南海トラフ大地震や首都直下地震、富士山噴火など近未来の厄災を想定すれば、予算をがぶ飲みしている大阪万博や、東京の大手町に390mのタワービルを建てている場合ではないような気がするのですが、これは「杞憂」でしょうか?
まぁ私は最悪の事態を予想して、身を守る手段だけは考えています。幸い、東京や大阪へ行く用事は無くなりましたので帰宅難民にはならずにすみそうですし、地震や津波に巻き込まれることも避けられそうです。無論、京都だって決して安心は出来ません。だからいざ鎌倉の時、私は飯田に逃げます。飯田―京都は約230キロ。毎朝2時間の散歩は伊達ではありません。その気で歩けば一日40キロとは言いませんが、30キロ程度は歩けるでしょうし、ヒッチハイクも可能かも。
ニャンですと?爺さんの場合、ヒッチハイクは無理!う~ん、そういう可能性もありますが世の中、軽トラに乗せてくれる親切な人がいらっしゃるかもしれません。問題はトラ姫様ですが、これはまぁ息子に預けていきましょう。で、落ち着いたら三顧の礼でお迎えに。ニャニ?三顧の礼は意味が違う?まぁそう固いことをおっしゃらずに、爺さんのノーテンキ話としてお聞き捨て下さい。
(9月27日)
【ノーテンキ川柳】 厄災を よける手段は 足二本
猛暑日残酷物語

京都に帰って来て早一週間経ちましたが、夏はまだまだ続いています。いやはや、恐れ入谷の鬼子母神。昨日9月16日の京都は36度4分の猛暑日でした。日課にしています朝の散歩ですが、そういう温度ですから4時過ぎに起床して夜明け前に出発し、7時前後に帰宅します。
本日も4時45分に出発しましたが家を出た時の空はまだ暗闇で、東の空には明けの明星が光っていました。星を見ながら吉田山の坂を越え、竹中稲荷(ローカルな話でメンゴメンゴ)参道から大文字山を見ると、山の稜線がうっすら夜明け色に染まりつつあります(AM4:53)。
それから坂を下りてまた上ってくると丁度5時。大文字山にかかっている雲の形が見え始めます。また坂を下りて上ってくると5時7分。ここでタオルの汗を絞って大文字山を見ると雲の形がはっきりとしていますし、山の稜線の木の形も見えます。一日の始まりです。この頃になりますと散歩をしているお爺さんに会いますが、お婆さんには会いません。無論6時を過ぎますと、時に犬の散歩をさせているお婆さんにも会いますが、5時台には会わないのです。恐らくお婆さんは家事で忙しいのでしょうし、暗い時間帯には心理的抵抗があるのだろうと思います。
5時半頃までは吉田山の東側斜面の坂道や真如堂・黒谷金戒光明寺などを巡回していますが、5時半を過ぎると吉田山西斜面、つまり山道の方を歩きます。これには朝日を避ける意味もあります。私、夏も冬も散歩は原則Tシャツ一枚ですので、冬は朝日があたると肌がほんのり温もって太陽の恩恵を感じますが、汗が頭と両腕から噴き出している夏はいけません。道中、15分程度でタオルを絞るのですが、そうすると石畳に汗の池が!
いや、大げさに言っているのではないのですよ、本当に石の窪みに汗が溜まるのです。これを散歩の間に何回繰り返しますかねぇ。帰宅前にはTシャツからしたたり落ちた汗で、ズボンの膝上まで濡れています。よく皆さん、帽子を被って散歩なさいますが、帽子なんて被った日には頭の汗が拭けません。ですから私は、タオルを頭の上に乗せた温泉入湯スタイルで散歩しています。禿げ隠しにもなりますしね、ワハハハハ。
まぁそんな状態ですので帰宅したらすぐ水風呂に入り、手桶に汲んだ水を頭から10回ほどかぶります。水風呂で身体を洗うときのタオルは、散歩時に頭の上に乗せていたものを使いますので、水が白く濁ります。どれくらいの汗か、この表現でお分かり頂けると思いますが、汗には身体の老廃物が相当に含まれていることを実感させられます。毎日これだけ汗をかくのですが、体重は一向に減りません。成人の場合、身体組織の60%~65%が水、年寄りの場合は50%~55%といわれますが、水分補給をしないと熱中症になりますしね、
やれやれ。
水風呂から上がるとポッカのダブルレモンという炭酸水500ccを一気飲み。トラの頭をひとなぜしておいてコーヒーと新聞タイム。読み終わるこれで大体8時になっています。起床してから4時間が、あっという間にたってしまったという感じですね。老人の非生産性がよくわかります。まぁ年寄りが働かなければならない社会というのも如何なものかと思いますので、こんなものでしょう。
ハイ、お後がよろしいようで!
(2023年9月17日)
【酷暑川柳】 立秋に 水風呂使い 汗しずめ
喜寿のクラス会

本日10日午前、吉田に帰宅しました。9日にはトラ姫様を乗せて中央西線中津川駅へ、その後新幹線で京都まで。京都の滞在時間は約1時間で自宅には上がらず、そのままタクシーで京都駅に引き返すという忙しい帰宅でした。という訳で姫様は、グリーン車に乗る回数が最も頻回なおネコ様であろうと推察しております。年2回、10年ですからね。但し料金は特急しなの号を含め、一回290円ですが。
ところで9月1日に、綾部温泉二王館というところで中学校のクラス会があったので、飯田から車で参加しました。片道300キロの旅でしたが覆面パトからの、「運転手さん、スピード注意ね!」という警告は受けませんでした。
表題のとおり喜寿の集まりなので、ま、華やかさは全くありませんし、では枯れ木の集まりかというとそうでもありません。“雀百まで踊り忘れず”で、ライフサイクル論でいう老年期はまた脳天気の時代。社会的責務から解放され自分の趣味や関心に従って気ままに時間を使うことができる時でもあります。私を含め町に出ている連中は、テニスや絵画、彫刻など趣味中心に生活している模様。田舎に残っている少数派は少数派で、地域社会の各種アクティビティで活躍しているようです。斜め前に座っていた女性は9haの田んぼを耕作しているので、今は毎日が稲刈りだとぼやいていましたが。
最近、「なぜヒトだけが老いるのか」(小林武彦、講談社現代新書)という本を読みましたが、要するに「お婆さん仮説」*¹を各色のオブラートで包んであるだけで、目新しい仮説の展開はありませんでした。いずれにしても「all creatures must be die」で、老いも死も避けることはできませんが、私思うに、肉体的に衰えていく“老い”には精神的なメリットがあります。無論、デメリットの方が多いという見方も成り立ちますが。以下、私のケースです。
荘厳という名字のいわれについてはお話しする機会があるかと思いますが、日本で我が家だけですし、舜哉という文字の名前も見かけたことはありません。これだけ目立つとひっそり生きるのは難しいし、埋没を避けようとすると一匹オオカミ的にならざるを得ません。私の座右の銘は従って、独立自尊です。
他から指図されることなく、独立自尊で生涯を貫こうとすれば研究者の道は理想でした。でもこれは後からわかったことですが、研究というのは組織プレーだと思います。でまぁ、私が赴任した大学には心理学科がありませんでしたので、実証研究をするためにはまず実験室(観察室)を大学内に作る必要がありました。幸いであったことは大学側がこれを認めてくれたことです。
この話は稿を改めることにして、本論に戻ります。独立自尊の研究者の道を歩んできたのですが、定年退職した時、もうこれで論文を書くための作業をしなくてもいいのだと、心底ほっとしました。最後の5年間は心理学科に勤務しましたが、お話ししたようにそれまでは心理学科のない大学勤務でしたから研究費を集めてこなければなりません。これは基本、科学研究費の助成金をとることで実現します。私がfirst authorで獲得した科研費は、生涯で総額5000万円になりましたが、これを貰わなかったら研究室の維持ができません。しかし科研費を貰うと申請課題の研究をしなければならない。要するに“イタチごっこ”だった訳です。
退職して研究室を維持する必要がなくなったらもう、科研費申請の必要もなければ溜まったデータ処理のあれこれを考える必要もなくなったことに、心底ほっとした次第。その後は全ての時間は自分のことに使えますから毎夏、飯田の別荘で過ごしていますし、12~3月を除いて飯田―京都を行ったり来たりの生活です。
飯田では朝2~3時間散歩をして季節の移り変わりを楽しみ、時には道路にいるアズマヒキガエル、モグラやサワガニ、アゲハの幼虫やナナフシ、セミなどのレスキューをしています。ま、時には離れザルからマウントを受けることもありますが。
帰宅後はベランダでコーヒを飲み、すぐそばまで来る野鳥を観察したり風で緑が揺れるのをぼんやり見ていたり、3時を過ぎれば温泉に。後、買い物と料理もありますから結構忙しくしています。要するにこういう生産性ゼロの日々は、“余禄の人生”(深沢七郎)なのですが、これが楽しい。何もすることがないということの素晴らしさは、若いときには味わえません。老いることのメリット、お分かり頂けましたか?
皆さんも定年退職後は肩から荷をおろし、田舎に「いいいじゅ~」をしましょう。
(9月10日)
【ふるび短歌】 事はなく ただ淡々と 時が過ぎ 木の葉の色の 変わる楽しみ
注1 「お婆さん仮説」 なぜ、人類の女性だけに閉経という現象があるのかを、包括適応度(遺伝子を共有する個体数の最大化)の観点から説明する仮説。つまり自分が生涯にわたって子どもを生み続けるよりも、自分の娘や息子のヘルパーに回った方が、生き残る血縁個体数が増加すると説明する。
アキアカネが飛ぶ頃
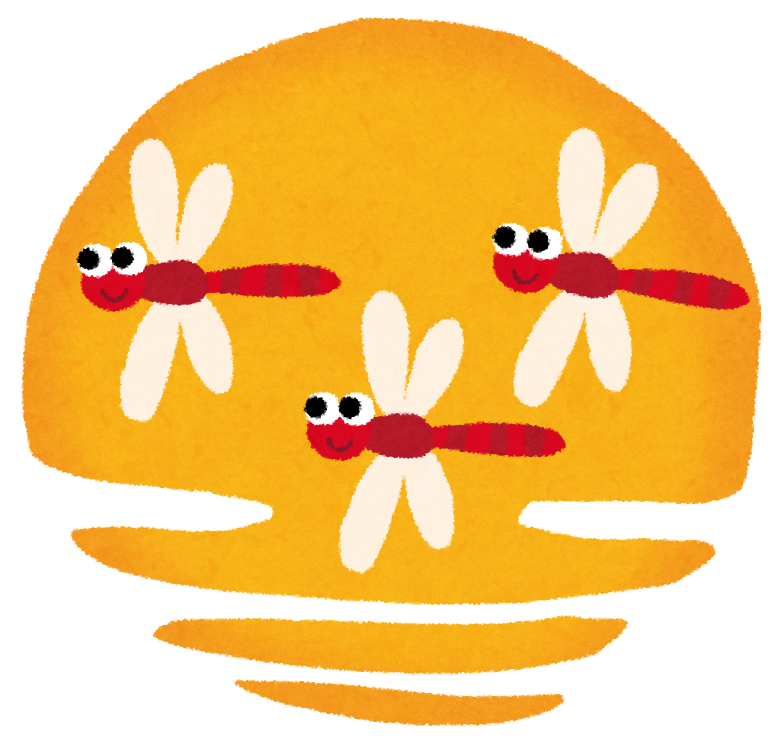
京都では体温越えの気温が連続したという今年の夏ですが、ここ飯田高原では最高が29度でした。今の季節、別荘地から林の中を下りていきますと棚田や果樹園の上をアキアカネが飛び交っています。毎年の事ですが私はこの時期、何となくけだるく物憂い感覚に陥ります。夏の終わりに生じるこの感覚を、私はアンニュイ(ennui)と形容しますが、思い起こせば子どもの頃からアンニュイを感じていたような気がします。
子ども期のこの感覚には、日照時間が関係していたのではないかと思います。夏休みが終わる8月末は、日暮れが早くなって遊ぶ時間が短くなりますからね。でも、サンデー毎日の老年期、どうして夏の終わりにアンニュイを感じるのでしょうか。私は行動科学者の端くれですから、ユングのように年老いたからだとは結論しません。そこでこのことについて内省してみました。
内省などと難しい言葉を使いましたがとどのつまりこの感覚は、退職して夏場の別荘生活を送るようになってからだと気づきました。夏が終われば自動的に帰京のカウントダウンが始まりますので、しまうための準備が色々必要なのです。現役時代ですと夏が終われば後期が始まり、毎日が忙しかったのでそもそもアンニュイ感など感じている暇はありませんでした。
では、何がアンニュイ感につながっているのでしょうか。例えば“食べる”という行為です。帰京のカウントダウンが始まると、食べることが結構面倒になるのです。“もったいない”世代の私にとって、食品を廃棄することは考えられません。要するに今ある食材を利用しながら新しい材料も購入し、日々の献立を考えながら2週間ほどでゼロにもっていく、そのことがけだるさにつながるのです。
山の神様と一緒に帰宅すれば簡単なのですが、一日でも長く飯田にいたい私と、コーラス婆の会が再会される山の神とは、どうしてもスケジュールが一致しません。という訳で、冷蔵庫のお片づけは2段階になります。第一段階は清涼飲料水などの飲みもの整理から始まります。
ここ飯田でも、9月初めまではまだ真夏日が継続するようですが、30度を割り込むようになりますと清涼飲料水を飲みたいという欲求は急速に低減します。今年は、梅干しと赤しそ味の「Ume Soda Red」(伊藤園)にはまってしまい、買い置きがしてあります。確かに強烈な酸味で、暑さを吹き飛ばしてくれる味でしたが、これを計画的に飲んでしまわねばなりません。
私は京都人なので、夏は必ずどぼ漬け(ぬか漬け)を作ります。この中身も計画的に考えておかねばなりません。水ナスは皮が柔らかいので比較的早くつかりますが、普通のナスは時間がかかります。キュウリやシマ瓜は2日目あたりがおいしいと思っていますが、ローテーションも必要。それやこれやで野菜の個数管理がなかなか厄介なのです。130円ほどのキュウリ一袋に、下手すれば5~6本入っていますからね。
姫様のトイレには2種類の紙砂とヒノキのチップを混合して使っています。この残量やカリカリさんの残量、各種トッピング残量も考えておかねばなりません。まぁ、こういう様々な段取りを考えていかなければならないのが夏の終わり。面倒でしょう?アンニュイの原因、わかって頂けましたか?ところで私はアンニュイを本来の、「けだるい・もの憂い・憂鬱」という意味で使っていますが、最近の日本語ではアンニュイは誉め言葉なんですってね。儚げでかつミステリアスな雰囲気をもつ女性を形容する言葉らしいですが、アンニュイ系男子もいるそうです。ジェンダーレスの時代ですねぇ。
昔は日焼けして色黒、活発で弾けるような笑顔の男子がもてたような気がするのですが。私?ワハハハハ、昭和は遠くなりにけり!
(8月30日)
【ヘボ川柳】 アカネ舞い 葛の花咲き 夏終わる
トラ姫様、お隠れの巻

トラ姫様に留守番をお願いし、お年寄り様と二人で中里介山の小説「大菩薩峠」で有名な大菩薩山の登り口にある裂石温泉雲峰荘に行ってきました。山梨県にはなぜか冷泉が多く、夏に訪れるには最適なのです。飯田から180キロですので、諏訪湖SAで休憩時間をとっても3時間ほどで着きます。
この裂石という地名には謂れがありまして、今を去ること1300年ほど前、天平17年6月17日(745年)、大菩薩山一帯に霊雲があらわれたその夜、にわかに大地が振動して大石が真っ二つに裂け、その割れ目から萩の大木が出現したとのことで、行基上人がそれを発見し云々と伝えられているとか。役に立たないものの代表として「ウドの大木」という表現がありますが、行基上人はその萩の大木を切り出し、三体の十一面観音像を彫ったのだとか。ウドは役立たずですが萩は袖垣の素材。風流ですよ。
17日、繊細なおネコ様ですので様子がおかしいと感じるのでしょう。部屋の片隅で固まっていましたが、カリカリを補給し鰹節をトッピングして12時40分に出発。翌日12時に帰宅したら追加したカリカリはほとんど手つかず状態で、トッピングの部分だけがなくなっていました。こういう状態ですので、一泊留守にするのが限界。雷が鳴ると押し入れの布団の後ろに隠れますので、押し入れを開けなければなりませんしねぇ。斯くして我が家のネコ本位制度は続きます。
しかし、迷走台風の6号と列島横断台風7号がいなくなって、やはり山の空気は変わりました。京都や大阪は36度を超えているようですが、山では27度が最高。やはり値打ちがあります。セミの声もミンミンゼミからツクツクボウシに変わってきましたし、萩や葛が咲き始めています。アケビの実も大分大きくなってきました。10月に松茸を買いに来ますので、その頃には二つに割れているかもしれません。京都に持ち帰り、吉田山に種をばら撒きましょう。吉田山は里山ですが、なぜかアケビが生えていないのです。
という訳で20年後の秋、もし吉田山にアケビが実ったら、それは愕然和尚の仕事であると思って下さい。ワハハハハ!
(8月20日)
【ネコ川柳】 くわばらの 天神様は 押し入れに
夏風邪をひきました
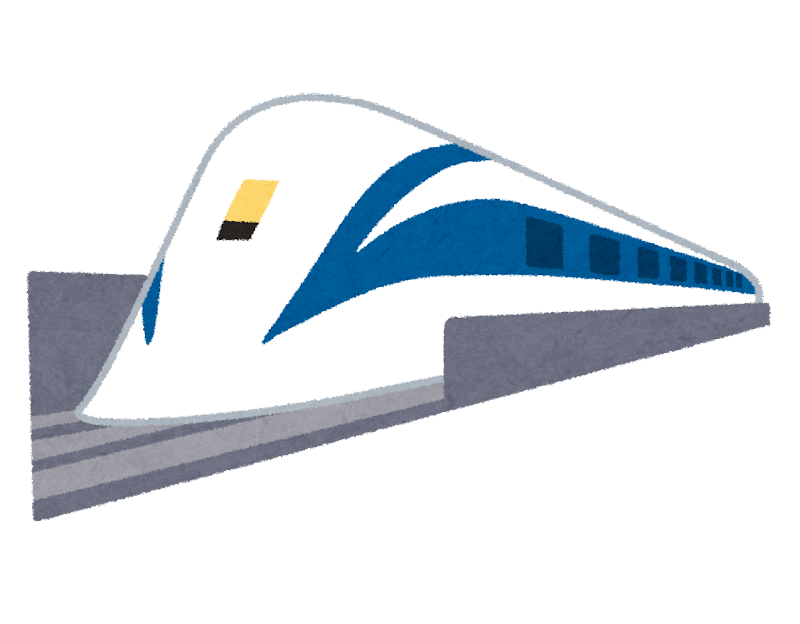
既に立秋を過ぎ、お盆の時期になりました。若い頃はお盆は一番忙しい季節で、朝から衣を着て棚経の檀家廻り。でも田舎でしたし、今ほどは暑くなかったのでまだ耐えられました。国連のグテーレス事務総長は7月27日、世界各地で頻発している高温を地球沸騰化の時代に入ったと形容しましたが、同月26日の世相放談に書いたように、温暖化は既にティッピング・ポイントを超えたのかも知れません。
この原稿を書いているのは13日ですが、12日の京都は38.9度だったとか。飯田市は測候所のある市街地で35度でしたが、山の上では28.8度で29度には届きませんでした。市街地と我が家の間には標高差もありますが6~7度の温度差があるからです。
寝室は谷に面しており、夜間も窓を開けておきますが、先日、朝起きたら鼻水がズルズル、咳がコンコン。夏風邪を引いてしまいました。昨夜と今朝の温度差はわずかに1.5度でしたが、5度近い温度差があった時の寝冷えです。そこで3日続けてカイゲンを服用し、今朝は完全復調です。
で、今回の放談で何が言いたいのかというと、自然災害が多発する地球沸騰化の時代には、生活拠点が2カ所必要なのではないかということです。今、東京では麻布台ヒルズとかに地上330mの高層ビルが建ち、54~64階はマンションになるそうですが、私なら絶対買いません。無論、買おうと思っても買えませんが、しかしそんな所に住んで一体どうするのでしょうか?遊園地のバイキングでも怖い高所恐怖症の私には、絶対考えられない生活です。
そんな不自然な所に住むよりも、そりゃまぁ、時にはサルにマウントされたりもしますが、自然豊かな田舎に移住するほうがいいような気がしますが、如何なものでしょうかねぇ。しかも飯田にはリニアが止まりますからね。静岡県のお代官、川勝ちゃんがいちゃもんをつけてきますので、工事は大幅に遅れていますが、やがては開通するでしょう。という訳で、私がリニアを利用できるかどうかは「微妙~」なのですが、開通すれば京都―飯田間は、新幹線名古屋乗り換え時間を含めても1時間少々になりそうです。
NHKに「いいいじゅ~!!」という番組があります。都会を脱出して地方に移り住んだ人や家族を取材した番組ですが、私は時宜を得た企画であると思っています。東京や大阪のような大都市で、時間に追われながらの生活を送るよりは、飯田のような地方都市や山・漁村に移住し、仕事はリモートでという生活の方がいいと思うのは、私だけでしょうか。尤も、前を走る枯れ葉マークの軽には手を焼きますが。
ところで今初めて知りましたが、75歳以上は枯れ葉マークをつけることが義務化されていたのですね。「お爺さん、義務化されていますので付けていない場合は罰金です」と言われれば払いましょう。しかし絶対につけません。枯れ葉マークを付けたジャガーFペイス(KEI NISHIKORI Edition)というのは様にならないというか、冗談でしかないような気がします。ワハハハハ。
(8月14日)
【ボケ川柳】 ドンキーの 頑固爺さん 枯れ葉なし
世界人形劇フェスタ
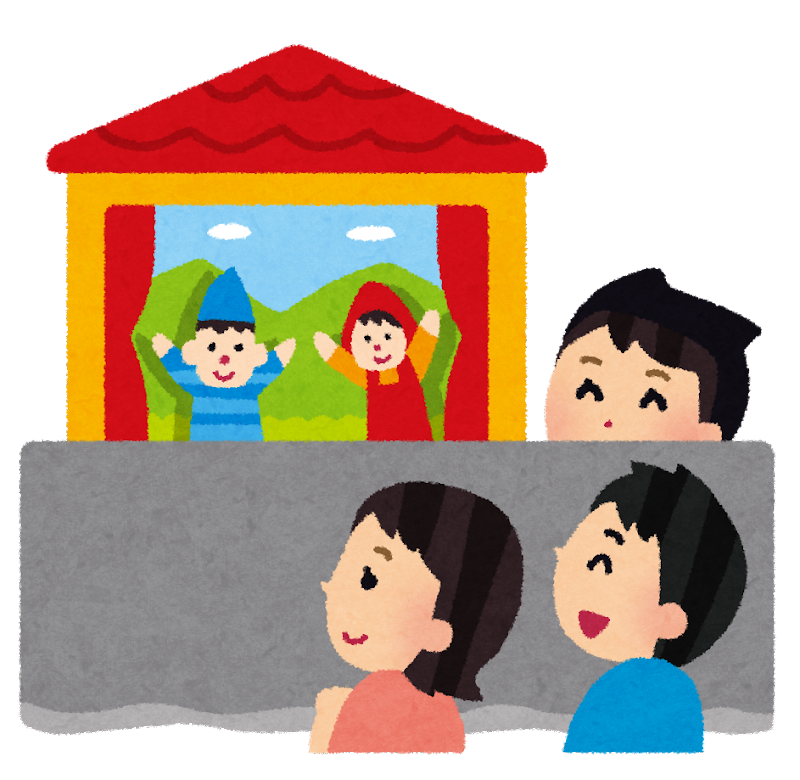
8月に入り、山はセミしぐれでにぎやかです。湿気も大分抜けて、朝から強い太陽の光が差し込むようになりました。トラ姫様はさっそく日光浴。この間は部屋に入ってきたシオカラトンボと格闘されておりました。庭ではアサギマダラが飛んでいますしミスジチョウも優雅に、ヒラリヒラリと滑空しています。
山はこのような状態ですが、丘の上(市街地)では8月3日から恒例の世界人形劇フェスタが、コロナ前と同じ規模で始まりました。6日のフィナーレまでに各所で約360の公演(参加劇団数230、コロナ前2019年330劇団)があり、韓国や台湾など海外劇団の参加もあります。観覧にはおとな・こども(3歳未満を除く)に関わらず1枚700円のワッペンが必要ですが、加えて有料観覧もあります(45本)。会場間は無料バスが運行されていますが、屋根着きオープン型なので、汗かきの私には無理!自宅は標高900mなので涼しいのですが、丘の上は日中35度ほどになるからです。
という訳で毎年、広い駐車場があり冷房が効いている文化会館での観劇にしていますが、今年は3つの有料劇を鑑賞しました。順に、「河の童―かわのわっぱー(デフ・パペットシアター・ひとみ)」、「チト みどりのゆびをもつ少年(人形劇団むすび座)」、「エルマーとりゅう(人形劇団プーク)」です。秀逸だったのはむすび座の「チト」です。
今、ロシアがウクライナに戦争を仕掛け、我々はその悲惨さを再認識させられている最中ですが、この劇はフランス人でナチスに対するレジスタンスに参加し、戦後文化大臣になったモーリス・ドリュリオンの原作との事。つまり反戦劇です。上演時間は115分ですから粗筋は割愛させていただきますが、いくつか要点だけ。
チトという名の少年は、親指をあてた所に花を咲かせるという超能力を神様から授かっているのですが、学校では授業が始まると寝てしまい、退学させられてしまいます。いわば発達障害で通常級では学べない少年なのです。
両親はチトを二人の家庭教師にあずけ、植物などの生物学と物理や工学などの知識を学ばせようとします。そこでヒゲさんという生物担当の先生から腐葉土に種をまくことを教えてもらうのですが、チトが指で土にさわるとそこに花が咲くのです。神様がチトに超能力を与えていたのですね。
チトのお父さんは武器製造会社を経営し、町の人たちはそこで働いているのですが、南の2つの国の間に国境付近の石油採掘をめぐって戦争が起きようとしていました。当然、2つの国からはチトのお父さんの会社に武器の注文が入り、それが出荷されようとする前夜、チトは準備されている武器の点検をしました。かみなりさんという物理・工学担当の先生からそれを聞いたお父さんは、いい後継ぎだと大喜び。
やがて戦争がはじまり、2つの国に送られた戦車や大砲が火を噴きましたがなんと、お互いが相手に対して弾を打てばそれは花に変わり、戦車や戦闘機はつる草に覆われる始末。チトが武器に触ったので花の種が植え付けられたのです。という訳で、実際には戦争は始まりませんでした。お父さんは武器工場の信用が失墜したと嘆きましたが平和の方がいいと気づき、工場を種苗工場に切り替えて、町の人たちも引き続き工場で働くことができましたとさ。
劇で主張されているのは、植物は互いが争わず平和共存しているよということです。ロシアの人たちにも早く、心の中に花を咲かせてほしいですね。
(8月7日)
【飯田川柳】 年一度 人が濃くなる 丘の夏
盛夏がきました

7月22日に関東甲信地方の梅雨明けが宣言され、いよいよ夏本番です。しかし今の所(26日現在)、山の上は朝の温度が20~22度程度で昼間の最高気温は29度。30度超えはありません。天気予報で飯田の気温表示が出ますがそれは測候所がある丘の上(飯田市街地)の温度。標高900mのこの辺と比較すると5~6度、天竜川川筋とは7~8度の違いがあります。
家の右横には谷川が流れておりますので室内にいても、吹き上げてくる涼風のおかげで汗も出ません。昨年は30度の日が2日ありましたがエルニーニョの今年は、だけどもう少し増えるかもしれませんね。世界各地で45度とか50度の気温が観測され、既にティッピング・ポイント(tipping point:転換点)を迎えたとする見方もあるようですが、世界はどうなるのでしょう?シベリア・北極海に広がるツンドラ地帯を多く抱えるロシアも、戦争なんかしている場合ではないと思うのですが、反戦の声は全く上がってきませんね。
ところでご心配をかけましたトラ姫様はすっかり回復され、毎朝、庭先の散歩を楽しんでいらっしゃいます。朝は雨戸をあけると待ちかねたようにベランダにお出ましになりますが、裏庭にはにわにわとりもいませんのでお出ましにはならず、時々カナヘビどんやビッキの大将が姿を見せる前庭の散歩を楽しんでいらっしゃいます。自閉症傾向が強い姫様は、どういう基準かわかりませんが、自分で決めた境界をしっかりと守りますので、爺も安心して放任しています。
姫様同様、私も朝の散歩を楽しんでいますが先日、一匹のはぐれザルに遇いました。恐らく3~4歳のオスではないかと思います。サルは基本人間を避け、出会うとブッシュに姿を隠しますので、人間がいるよと知らせるために「ホォ~イ、おはよう」と声掛けをしておきました。ところが彼奴が横切っていた箇所を通るとニャンと、モミジの木に登って私が近づくのを待ち受けているではありませんか!威嚇の木ゆすりこそしませんでしたが、私を睨みつけマウント行動をとっています。
サルになめられたのは初めてですが、私ももうお爺さんですのでケンカをしても勝ち目はありませんし、彼奴等の犬歯は人間の指一本くらい簡単に切り落とすといわれています。ですからそれ以上目線を合わせないようにして散歩を続けました。若さには負けます。ワハハハハ。
(7月26日)
【老いの川柳】 サルにまで マウントされる 始末かな
朝なのにひるとは、これ如何に

京都の祇園祭は蒸し暑さが半端ではありませんが、人の集まりも半端ではありません。暑いの大嫌いで人混みも嫌いな愕然は、トラ姫様のお供をして既に信濃の国は山の中。18日にはお年寄り様も国入りなさいます。トラ姫様は布団が来るとお喜びの様子です。
恐らく寝相が悪いのでしょう、姫は私の布団には絶対に来ません。昔、メイ(別名、院長先生)とアメリカから移住してきたウエンディという二匹がいた時は、メイが山の神の布団の上で休む時はウエンディが私の布団の上で休み、不思議に一か月ほどたつと交代していましたので寝相だけではない気もしますが、とにかく私は給食係兼トイレ掃除係から昇格しません。変ですね!
ところで今年も梅雨の線状降水帯が九州や山陰などで大きな被害を出しましたし、今は秋田県で被害が出ているようですが、幸い飯田では何事もなく無事でした。という訳で、姫様が4時過ぎに起床されますので私もおつき合いして起床。5時過ぎには散歩に出ます。
7月5日でしたでしょうか、およそ2時間半(日によって1時間から3時間まで巾があります)の散歩を終え、Tシャツやタオルを洗濯機に放り込み、ふと足元を見ると麻のズボン下(昔風に言うとステテコ)左裾に血がついています。右には変化はありませんがよく見るとスリッパが血だらけでぐっしょり濡れているではありませんか!蛭にやられたのです。場所は右足裏土踏まずから約1センチ上の部分です。
あわててバンドエイドを張ったのですが、動脈血栓をもつ私は血液サラサラ成分薬を服用していますので小さなやつではどうにもなりません。耳に羽虫が飛び込んだ時やハチに刺された時など、なにかとお世話になっているお隣さん(MD)に駆け込み、大きなやつを張って頂いたのですが、これもすぐに血だらけ。結局、止血するためには強い圧をかける必要があり、手当をしていただきました。いつも言いますが、田舎暮らしで持つべきものは医者の隣人。お世話になりました、ペコリ!
しかしスニーカーを履き、靴下を着用しているにもかかわらずきゃつはどこから侵入したのでしょう。また、脱いだスニーカーを調べましたが当然、きゃつはお腹いっぱいと離脱していますので姿はなし。MDの話によりますと昔は天竜川をはさみ右岸(飯田市街地側)にはいなかったらしいのですが、南アルプスに続く左岸にはいたとのことで、10~15年ほど前にシカが右岸に運んできたとの事です。
翌々日、芝生のスミレ退治をして家に上がり、ウッドデッキで長靴を脱いでふと見ると、長靴のへりできゃつがシャクトリムシ運動をしているではありませんか。この野郎とティッシュでつまみ上げハサミで一刀両断。ふとリビングの床を見るともう一匹がムンノムンノとこれまたシャクトリムシ運動。当然こいつも問答無用の一刀両断。仏に帰依している身ではありますが、二匹の蛭を殺生しました。
それにしても回行中の阿闍梨の血を吸ったやつは、いったいどこへ消えたのでしょうね。吸われた部分には今も小さな突起が残っており、時々、かゆいのですが。
(7月16日)
【ヘボ川柳】 やれ切るな ヒルがペコペコ お辞儀する
夏の生活が始まりました

コーラスの会がまだ夏休みに入っていませんので、お年寄り様が飯田にお越しになるのは7月半ばになりますが、トラ姫様は6月24日に新幹線と中央西線というルートでお国入りなさいました。しかし相変わらず、「拉致される」という訴えが無くならないのが羊(執事)の悩み。車の中でも拉致コールの連発ですのでせめてもの対策としてジャガー(ネコ科)に乗っていますが、今年は中津川から飯田大瀬木城までは至って静かでした。しかしまぁ、姫さまにおかれましても信州飯田で迎えられる10年目の夏です。という訳で早めの、
♪暑中お見舞い申し上げます(キャンディーズ)
といっても、この文章をお読み頂いている方々で、キャンディーズという女性歌手グループをご存じの方はどれくらいいらっしゃるのでしょうか?なにせ羊は来年喜寿ですから、また死語辞典を紐とかせるかも知れませんが、メンゴメンゴ。
ご心配をおかけしましたが姫様のご攪乱、お隣のお医者さんのご意見では恐らくウイルスが引き起こした症状だったのだろうとのこと。整腸のためでしょうか、姫様は雲鼓の前にどえらい勢いで部屋中を駆け回られますが、この「雲鼓体操」が復活しております。後ろ足よろよろバタンはどこへやらで、ホント、安心しました。今はネコちぐらの上で丸まっていらっしゃいますが、シッポの先が微妙に動いていますので、まぁウトウト状態。おっと、今シッポの動きが止まりました。
姫様をお迎えする前に庭の掃除を済ませておきたいと思っていましたが、結局6月一杯を必要としました。なにせ山ですので春に草刈り・草引きをした部分も6月には元の木阿弥。庭の手入れは気温がまだ低い午前中にしますので、今回も結局10日ほどを要しました。
しかしよくしたもので、手をいれた部分はやはりきれいです。で、終わったと思ってもまたひと月もすれば元の木阿弥。ですから飯田にいる限り常にどこかしら、手入れをしなければなりません。京都にいればすることがないと無聊をかこつのですが、さて、どちらが幸せなのでしょうか?
今年はまだ、芝生に「肥し」撒いといたでという悪いタヌキは出てきていません。そういえば居候の青大将はどうしたのかな?去年は脱皮した皮を玄関のデッキに残していたのですが。庭をきれいにしておくと、隠れるところがないからヘビがいなくなると地元の方はおっしゃいますが、はて?宿代をとると脅したつもりもないのですが。
そういえばビッキの親方の姿もまだ見かけていませんし、カナヘビどんもまだ見ていません。今朝は雨でしたのでサワガニどんが軒下にいましたが、常に日々新たな飯田の毎日です。そうそう、街灯が邪魔をしますがホタルもいますよ。
(6月30日)
【ヘボ川柳】 どうぶつの 顔みてわかる 季節かな
トラ姫様、ふらつき歩きの巻

原因は未だ判明していませんが、去る6月6日早朝からトラ姫様のお身体に変調が生じています。
朝4時、トラ姫様が「バタッ」と大きな音を立てて寝室に戻ってらっしゃいました。あれ?っと思いましたが二度寝。起床後、バナナとヨーグルト、納豆などの朝食を食べておりましたらリビングにお越しになった姫様のご様子がヘン!後ろ足が不安定で、もつれたような歩き方なのです。どうやら階段の辺りでは転倒されたご様子。9時になるのを待ってすぐに、かかりつけの動物病院へ電話して診察予約を取りました。
病院では触診、血液検査とレントゲン撮影を受けましたが獣医師にも原因はつかめぬ様子で、痛み止めを処方しておきますと言われて帰宅しました。粉薬は飲ませるのが非常に困難ですから、飲ませてはおりません。姫様の現下の様子をネット検索にかけたところ、一番可能性として疑わしいのは脳腫瘍ですが、これはfMRI検査をしなければわかりません。という訳でまだ何とも言えませんが、しばらく様子見をしています。ネット情報だと2週間くらいで安定的状態に戻ることもあるそうなので。
ところでネコのレントゲン写真は初めて見ましたが、哺乳類が爬虫類(恐竜)から進化してきたことがよくわかりました。尻尾の骨がずらりと並んでいるところは恐竜の骨格標本にそっくりです。哺乳類の尻尾は、爬虫類時代と同じく身体のバランスとるために必須の組織なのでしょうね。ネコやイヌの尻尾は、他にも感情表現に使われるようですが。
見渡してみれば地球上に現存する多くの生物には、ヘビのようにどこまでが胴体でどこからが尻尾なのかわからない奴もいますが、魚類も含めて多くの種に尻尾があります。ところが唯一、ヒト科霊長類だけは尻尾をなくしましたが、その理由は直立二足歩行という移動方法にあるようです。直立してカンガルーのように尻尾が下がっていたら、これは歩きにくいでしょうね。
普段私は、吉田山山岳救助隊訓練と称して約2時間強、真冬でもTシャツ1枚で吉田山上ル下ルの散歩をしておりますが、2月末から4月初めまでは花粉症で訓練をサボっていました。そうするとてきめんに負の効果が生じ、糖尿の傾向が出てきたことはお話ししましたが、桑の青汁を飲んだところ効果てきめん。2カ月ほどの間に血糖値は163から100(基準値70-109)、HbA1cは6.3から6.0(基準値4.6-6.2)へと、劇的に改善しました。
という次第で、尻尾が生えていないことを感謝しながら鋭意、山岳救助隊訓練をやっております。え?でもお腹がタヌキだから尻尾はズボンの中に隠しているのだろうって?確かに肥満(肥満度1)ではありますが、BMIは26.8ですから普通体重の基準値25未満をわずか1.8上回っているだけです。来年の内臓脂肪測定時には基準値以内に収めることを、固く決意しております。
という訳で姫様の現状ですが、時々ふらっとされますが最初のように「バタン」と倒れることはなくなりましたし、足のふらつきも改善されてきたように見えます。目力の強い姫様は寡黙で、食事の時だけは羊(執事)の目じっと睨んできますが元々口数が少ない自閉症ネコ。異種間(ネコミュニケーション)の意思疎通は難かしいですねぇ。
(6月18日)
【ネコ川柳】 これ羊(執事) わかったかいと 姫シッポ
生きた化石のひとりごと:少子化とスマホの関係を疑う

6月3日日経朝刊の一面には「出生率1.26、経済活力に危機」という見出しと共に、2015年までの出生数が100万人を超えていたのに比較し、23万人も減少したという現実が報道されていました。見開き3面には「少子化 見えぬ反転」という文字が躍っています。
これに対する政府の対策ですが、岸田内閣は異次元の少子化対策を講じるとかで、現在支給されている児童手当を15000円に増額し、所得制限を撤廃し18歳迄支給し、多子(第3子以降)を対称とした手当(A学院大卒の某議員によるとこれは「てとう」と読むらしいですが)を3万円に増額した上で、これも18歳迄支給するそうです(24年から)。大学・大学院の費用も負担軽減が検討されているそうですが、内容はまだ見えません。
乳幼児保育を含め、大学・大学院までの教育に関わる基本経費は無料にするべきというのが私の従来からの主張ですが、この問題はさておき、お金を出せば子どもは増えるのでしょうか?結婚したら子どもを持つべきと考える女性が2015年にはまだ67%あったのに対し、2021年には37%に減少しているにも関わらずですよ。金をばらまけばこどもが増えるという政府案は邪道ですし、何よりも姑息です。
武田信玄は「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」という言葉を残しました。国をつくり支えるのは人ですよ。だから金をばらまいて人を集めましょうとは教えていません。信頼があって初めて人は集まりますと教えているのです。幼保を含め教育に関する費用は原則無料にして人を創っていく、これが政府に対して信頼を集める本道ではないでしょうか。社説では「克服の道筋も財源も見えない」と書かれていますが、財源は消費税を当てればいいと思います。将来の日本国を創っていくためなら、消費税増税に対して老人も文句は言いますまい。
ところで識者は様々な理由をあげますが、どうして日本人は、子どもを産み・育てなくなったのでしょうか。以下、私の独断と偏見ですがスマホ普及率と出生率の間には何らかの関係があるのではと疑っています。
私は統計に弱いので両者の関係を統計的に論じることはできませんが、スマホ元年とも言える2010年のスマホ普及率は4.4%です。ところが翌11年に21.1%に急増し、15年には51.1%になり2022年には94%に達しました。
翻って出生率は、2010年が1.39で2022年が1.26ですから率にして0.13%の減少に過ぎないという見方も出来ますが、実際の数で見れば2010年には107万1305人が生まれたのに対し2015年は100万5721人、2022年は79万9728人なのです。スマホ普及率が50%を越えた15年からみると20万6000人ほど少なくなっています。この数字をみると、私がスマホと出生率の間に何らかの因果関係があるのではないかと疑う理由がご理解いただけるのではないかと思います。
バスの中などでスマホ操作をしている若者を見ていると、あっと言う間に画面がコロコロと変化し、瞬時で内容の要不要を判断し次のアプリを操作する様子に唖然呆然、愕然和尚。こういう若者たちですから子育てのような、時間をかけて結果を“待つ”という作業は苦手なのではないかと疑ってしまうのです。本は読まないし新聞・雑誌も読まない。バラエティは観てもテレビのニュースは観ない。でもスマホだけは常時操作する現代の若者の行動について、私の読みが外れていることを願うばかりです。
(6月10日)
【憂き世川柳】 情報と 子どもの数が 天秤に
梅雨入りしました
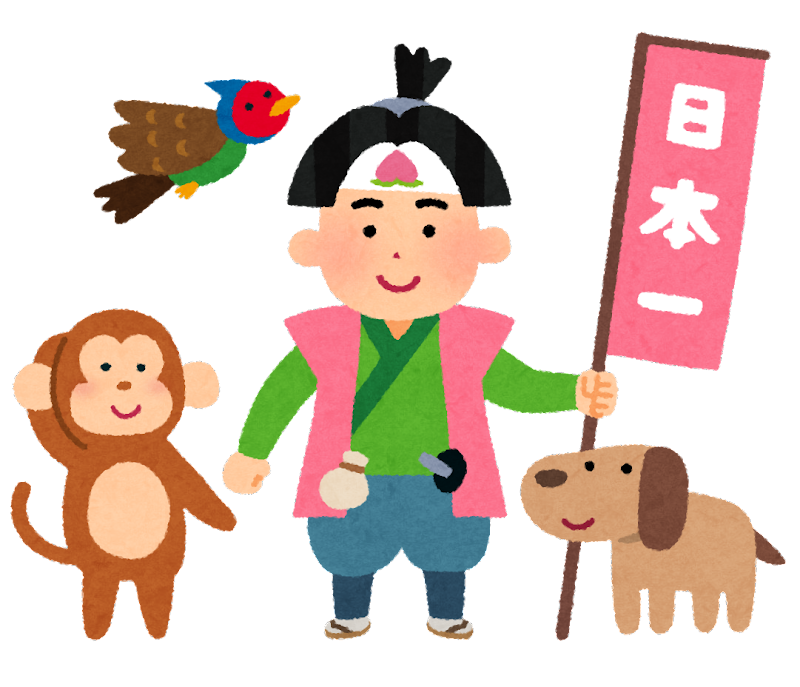
台風2号が発生していたからでしょうか、今年の梅雨入りは例年になく早く、中四国や近畿・東海などは5月29日に梅雨入り宣言がなされました。梅雨入り前に芝生のスミレ退治をと飯田入りしていた私は、お陰で大忙し。29日は全国的に強い雨でしたが26-28,30-31の4日でほぼ抜き終わり、最後は台風の影響を受ける前の6月1日午前で何とか終わらせました。
スミレに関しては既に何度もぼやいていますのでこれ以上ぼやきませんが、14歳の女流棋士中邑菫ちゃんは応援していますし、野原のスミレも可愛いと思うのですが、芝生に生えるスミレだけは憎たらしいこと限りなし。差別はいけません?ごもっともではありますが、これは経験者でないとわからないと思います。しかしまぁ、今回は動物たちのお話。
血液検査の結果、糖尿病の兆候が出ていると指摘され、糖質制限と運動推奨を受けていますので、飯田では朝5時過ぎから2時間強の散歩に出ます。これも何度かお話ししていますが、山の中ですので散歩の途中で様々な動物に会います。27日の散歩では今年初めてサルに会いました。山の斜面にいたサルは私が気づいたのを確認し、「ヒュ~イ」という声を残して木立の中に消えていきましたが、それから歩いて1分後、今度はキジの奥さんがお一人で歩いてらっしゃるのに出会いました。これでイヌにあうと桃太郎の三題噺になりますが、この日は会いませんでした。
今回の一週間の滞在で、モグラの葬式?を二度とりおこないました。 散歩していると道の真ん中に息絶えたモグラが見つかるのです。そのままにしておくと車にひかれそうで、既に死んでいるのだからどうでもいいと言われそうですが、その度に木の枝で道の端に転がして落ち葉をかけ、南無阿弥陀仏を唱えて今度生まれ変わってくる時はネコにしなさいねとアドバイスをしました。ネコほど誰にも束縛されず自由奔放に生活できるペットは他にいませんから、私は常々おネコ様を羨ましく思っているのです。
トラ姫様は私と老妻を人とは思わず召し使いと思ってらっしゃるようで、やれウンチが出たチッコがでた、片付けろと夜中でも起こされます。今も書斎に来て「ニャ~」となき、階段を降りていかれたのでついていくと、シッコがでておりました。山の神は時々噛みつかれるようで、「もう、イヤ」とおっしゃっております。ネコに生まれるとこのように人間をこき使うことができますし、まぁ自由奔放この上なし。イヌに生まれ変わるとリードに繋がれ自由がありませんし、時には熊やイノシシと喧嘩をしなくてはなりません。
何ですと?お風呂に入ってトリミングをし、いろんな服を着て歩けるからイヌがいい!なるほど。しかし100年前とは言いませんが70年前、日本にそんなイヌ、いましたか?私は「give me a freedom」派ですので、生まれ変わるときはネコにと願っております。皆さんならイヌかネコ、どちらを選ばれますか。え?人間でないとイヤだ?何も考える必要が無いネコの方がラクだと思いますがねぇ。
(6月3日)
【ノーテンキ川柳】 主不在 スミレはびこる 芝生かな
齢を重ねるということ

5月5日から12日まで、芝生のスミレ退治に飯田に出かけておりました。京都吉田の、市道と敷地の境界に生えるアリアケスミレは残すのですが、別荘の芝生に生えるスミレは天敵。放置しようものならたちまち芝生をあばた模様に変えてしまいますから、徹底して引き抜く必要があります。しかしゴボウ根のスミレは実に引きにくいのです。
引き抜くには草引き用フィットグリップの先を根の下に差し込んで、ぐいっと持ち上げるように引っかける必要がありますが、花丈と同じ長さだけ根を張っていますのでなかなか難しい。時には根元で切れてしまうことも多く、難儀です。花時の4月から5月初めにかけて抜いておかないと種をつけ、これがパチンとはじけて飛び散ったら最後、エライことなのです。
そういう訳で飯田には4月から既に3回、計18日滞在し、落ち葉を燃やしたりミチタネツケバナやスミレ退治をして夏に備えていますが、冒頭に書きましたように一旦帰宅しました。高速バス乗り場までは毎回タクシーを利用するのですが着く直前、別荘に携帯電話を置き忘れてきたことに気がつきました。引き返していたらバスに乗り遅れますので、「ま、いいか」と今日までケイタイのない生活ですが不便は全くありません。社会との接点が少なくなっていますから、身内からも含め電話がかかってくることがほぼないのです。
社会との接触頻度と暇は正比例の関係にあります。同様に、お酒を飲む機会も正比例します。お陰様で禁酒日はうなぎ登りで、昨年は211日、率にして57.8%でした。「斗酒猶辞せず」と李白を気取っていた昔が懐かしい!しかし、32.5度の夏日になった17日は、午後1時から3時にかけての暑い盛りに外出する用件があり、帰宅してすぐに「飲むぞ!」と宣言。糖質ゼロのビールを一缶飲み干しました。斗酒は望むベクもありませんが無論一缶では終わりません。翌18日も31.5度でしたし、刺身用のミンククジラや桜エビなど、珍しい物を見つけましたので2日を飲酒日にしました。で、ここからが今回のテーマにつながる話です。前置きが長くなり、スンマセン!
吉田にいる限り、天気が良かろうが悪かろうが何もする事が無いのですがしらふの19日にふと、過去の京都の気温を調べてみようという気になったのです。こんな暇なことを思いつくのは、することがない後期高齢者の爺さんならではのことでしょう。現役の主婦でいらっしゃる山の神は炊事・洗濯・掃除に買いものなど、構忙しくしてらっしゃるようですが。
私が京都に住み始めたのは18歳、1965年の4月でした。先に書きましたように今月は、久しぶりにビールが飲みたいという気分が喚起された夏日もありましたので、過去58年間京都市の5月の最高気温を調べてみました。気象庁がデータを開示していますから調べは簡単ですが、そもそもこんな暇なことを思いつくくらい、なんにも仙人は京都では無聊を託っているとお考え下さい。
私もdata scientistsの端くれでしたので、全てに対してevidence basedを重視しています。しかし統計に限っては、いつ、あるいは何を基準にするかによって結果が異なることを前提に、以下の話をお聞き下さい。
で、とりあえず私が京都市に住んだ58年という時間を前半・後半に分け、1994年までと1995年以後それぞれ29年間の5月の、気温30度以上の日数を比較してみました。そうすると前半が32日、後半が75日で統計にかけるまでもなく1995年以後は30度を超す日が以前の2倍以上になる事がわかりました。また、最高気温が20度に達しなかった日の比較では、94年までが27日、95年以後が22日で、やはり前半29年間の方が多く(低温)なっています。5月一月だけをとってみてもこの有様ですから冬や夏を比較すれば、地球温暖化はもっと顕著に具体化されているのでしょう。北極の氷が、溶けるわけです。
ケイタイがなくても何の不便も感じなかったり、ふと思い立ってこういうデータ遊びをしたりも、所詮暇だからできること。世の中には私のようにすることがなくて困っている爺さんたちも多いはずなので、こういう爺を集めて何か生産的なことはできませんかねぇ。昔の数え方なら私も今年は喜寿。今更起業でもないでしょうが爺さんたちは皆さん元船頭さん。「船頭多くして船山に上る」の例えもありますから座礁が目に見えている?なるほど、ごもっとも!お後がよろしいようで。
(5月24日)
【阿呆川柳】 集めても 爺のふんどし 帆にならず
予備軍招集令状

既にぼやいたように今年はスギ花粉の飛散量が多く、マスク嫌いの私は3月、ほとんど散歩をしていませんでした。それだけでもないと思いますが血液検査の結果、ついに糖尿病予備軍に招集されてしまいました。2年前の3月は血糖値が102と基準値(70~109)の範囲に収まっていたのですが、今年は163にジャンプしてしまったのです。当然、インスリンの指標であるHbA1c NGSP値(基準値4.6~6.2)は6.3と0.1オーバー。
という訳で、4月に結果の通知を受けて以来、毎日2時間を目処に「吉田山上ル下ル(あがる・さがると読みます)」のタヌキ捜索隊訓練を(数年前、吉田山散歩中に野生タヌキのカップルを発見しました)、飯田では別荘地・里山トレイルをしています。新緑のこの時期は、散歩しながら季節の節目を強く感じさせられています。
私、若い頃は春が一番好きな季節でした。西行ではありませんが、「願わくは花の下にて春死なん その如月の望月の頃」と思ったものです。しかし花粉症の今、春は最も嫌いな季節になってしまいました。でも5月ともなると杉・檜の花粉も飛ばなくなり、楠の若葉が燃えるように初夏をアピールしてきます。早朝なら汗もあまりかきませんから、この季節は大好きです。
ところで皆さん、桑はご存じですね。これを食んで蚕は蛹になり、繭から生糸がとれるので、 昔の信州では養蚕が盛んでした。ですから飯田の散歩コースには桑の古木が何本かあります。丹波の田舎育ちの私もその子ども期、6月半ば頃に熟し始める桑の実を食べました。歯も口の中も真っ黒になりますが、友だちとお互いに見せ合って楽しんだ記憶があります。ところで桑の実だけでなく葉っぱも食用になること、皆さんご存じですか?私は今回、初めて知りました。
1月に晩白柚を買い出しに行った時、偶然立ち寄った霧島市の道の駅で「桑青汁」という商品を見つけました。桑の葉の粉末です。効能書きを読むと血糖値の上昇を抑え、加えてコレステロールや血圧上昇も抑制すると書かれており、何となく“よさげ”に思い購入しました。その後4月に血液検査結果を見た時に閃きました。これや!!!、という訳で飯田に来る前に10パック(1包2g、計150包)を発注し、飯田でも毎日お湯に溶かして食事時に飲用しています。
昨日朝、散歩途中で犬を連れたご近所さん(定住の方)とお会いしました。するとその方から「顔が痩せましたね」と声をかけられました。加えて「お腹もへこんだし」といわれ、桑の青汁を飲んでいることを伝えましたが、もう効果が出たのかしら?実は今回飯田に来た時、いつもの温泉で体重計に乗った時の針が66.6Kgを指したのです。指摘を受けた日の体重は65.7Kgでした。65キロ台というのは例年なら8月の終わり、ぼつぼつ京都に帰るかという頃の体重なのです。ダイエットをしたわけでも何でもなく、単に桑の青汁を飲んだだけなのですよ。
ただ、かっこ悪い副作用もあります。散歩から帰宅後、ネット検索してみると桑青汁には利尿効果があるそうで、頻回にトイレに通うことになるのです。心理学はevidence basedを重視しますが、身をもって実験をしてしまいました。
私の朝食はいつもならバナナ1本とヨーグルト2種類なのですが、フード・ロスを避けようと、2日前に炊いたタケノコご飯の残りを、桑青汁をお茶代わりにして食べました。その後散歩に出たのですが、家を出て10分ほど経った時、「ミミズもオケラも皆、ゴメン」状態になったのです。
これ、皆さんには何のことかお分かりにならないでしょうね。昔、昭和の男の子が立ちションをするまえに唱えた呪文です。ミミズにションベンをかけるとおちんちんが腫れるが、こう言って謝っておけば無事だと先輩から習いました。散歩のコースはたまに車が通りますが基本、人には会いませんし車からは死角になる箇所も多いので、2時間20分の散歩中に、「ミミズもオケラも」の呪文を5回も唱えました。いつもならせいぜい1回なのですが。
山の神様がご一緒の場合は遠くに離れたうえで、「あなたはイヌか?」と嫌味を言われるのですが背に腹は代えられません。吉田山コースには公衆トイレが4カ所あるので(吉田山、金戒光明寺<京都守護職会津藩本陣>、真正極楽寺真如堂<三井家菩提寺>、馬場児童公園)不便は全くないのですが。散歩の途中リスやサル、シカ、ウリ坊、オコジョ、モグラ、コジュケイ、キジ、アズマヒキガエル、サワガニ、カタツムリ、青大将、ヤマカガシ、ジムグリ(順不同)に出会う自然豊かな飯田高原には、そういう施設はありません。見栄えのする姿ではありませんが、カ・カ・カンニンな!
(5月12日)
【言い訳川柳】 健康は ミミズとオケラの 散歩から
はびこるスマホゾンビとマスクマン

山の神様の3Gガラケーが使えなくなるということで、5Gの1円スマホに乗り換えました。1円という価格設定はよくわかりませんが、画面保護のフィルムとかケース、充電器で1万円弱支払いました。私のガラケー回線は4Gなので当面サービスは継続されるとのこと。スマホへの切り替えを中止しましたので何とかガラケーで終焉を迎えられそうです。孫からは化石といわれていますが、スマホに操られるゾンビよりましでしょう。
でも今回、巷間言われている日本の生産性の低さを実感しました。当然予約を取ってでかけたのですが、NTTドコモの窓口で購入手続きをするだけで2時間半かかったのです。これだけの時間を要しながらスマホをどのように使用するかについての説明は一切なし。マニュアルも何もないのでスマホ教室を受講する以外、操作方法を知る手がかりはありません。問題はここから更に泥沼化します。
一番早いスマホ教室が二日後の10時から2時間ということで、お出かけになった山の神様にご帰宅後話を聞くと、電話のかけ方も教えてもらえなかったとのこと。ポカン?と、私の口は開いたまま。そんなもの、質問すればいいやないかと申しましたが、それが山の神にはできません。という次第で何を聞いていたのやら私にはさっぱりわかりませんが、電話をかけられなければ何の役にもたちません。しかたがないので孫に教えてもらうことにしました。
日曜日、東京行きの新幹線に乗っていると山の神から電話がかかってきました。私が車内にいる時間であることは知っているはずだがとデッキから返信すると、電話の使用方法がわかったということを伝えておきたかったとのことでした。しかしまぁ、スマホに搭載されている様々な機能はおそらく使わないままになりそうです。装備されている多くの機能の使い方がわからないままということは、街ですれ違うスマホゾンビにならずに済みそうなので、カマ爺としては一安心です。ゾンビと一緒に暮らすのは嫌ですからね。
しかし街中、右を見ても左を見ても皆さんスマホ・ウオーキングで横断歩道を渡るときもスマホをやっています。私はガラケーですから歩きスマホからどのような情報が得られるのか、まったく想像もつきませんが、皆さん、必要だから歩きスマホをしていらっしゃるのでしょうな。しかしこの人たち、一体全体、自分でものごとを考えることがあるのだろうかと、つい疑ってしまいます。やれやれ!
5月8日からはコロナも、季節性インフルエンザ同様、感染症の中の5類分類になり、マスク着用は個人の判断になりますが、歩きスマホとマスクマンがあふれている日本は、一体どこへ向かうのでしょうか。折しも新聞はその見出しに、『人口減 縮む国力、2070年3割減8700万人』など危機感を煽っていますが(日経2023/04/27)、スマホゾンビやマスクマンにイノベーションを期待することはできないでしょう。この問題、76歳の後期高齢者が何を言っても蟷螂の斧ではありますが、それでも日本の将来を案じます。
(4月28日)
【イヤミ川柳】 カオナシの みんな右向く マスクマン
やっぱりヘンだよ 日本人

4月13日朝のNHKニュースが世界競争力ランキングについて報道していましたが、日本はマレーシアやタイに追い抜かれて34位とのことでした。かってアメリカの社会学者、エズラ・ヴォーゲルに『Japan as Number One; Lessons for America』(1979)と褒められ、実際に1989-1992年までは世界第一位の競争力を誇ったのですが、2000年前後からイノベーションが起こらず守り一辺倒になりました。民の力が落ちたのです。
原因は様々あると思いますが、13日に注目した記事がもう一つ。日本人のマスク着用率です。同日の日経朝刊では2面に「マスク着用なお9割:小売りや製造“推奨”目立つ」という見出しがあり、例えばイオンでは50万人の社員がその対象であるとか。三菱重工や日本製鉄では対人距離1mが確保出来ない場合は着用義務とのことですが、事業所内では当然人とのすれ違いが発生するはずですので、この基準だと着用せざるを得ません。実際、京都市バスの中でも今なおほぼ全員がマスクマンですが、二つのニュースに共通するものがあります。それは日本の“忖度文化”です。
私は同志社大学に学びました。恩師は、学長・総長・理事長を歴任されました故松山義則先生ですが、「同志社精神」を学ぶ機会を沢山与えられました。禅僧であった父からは、私たちは仏飯を頂いているのだから人々に感謝しなさいと教えられましたが、松山先生からは「良心とは何か」を学んだような気がします。同志社は「民」によって創設された大学だから、「官」と同じである必要はないし、むしろ「民」の良心を大切にしなさい、つまり独立自尊の心を大切にして自分の道を歩みなさいとの教えです。
ところで面白い発見がありました。第三段落を書いているときにふと、「同志社」「民という意識」という2つのキーワードでネット検索をかけたら4番目に「同志社教育をどう考えるか」という項目が出てきました。これを開いたとき、Before and after何ということでしょう!私の名前が出てきたではありませんか。大学3年の時の「教育懇談会」(1968年11月18日)で、他の3人の方とディベートをした時の発言要旨です。座談会には住谷総長、秦理事長他、約30名の教職員の方々がご出席のようでした。全文5000字を越えていますので要約することはできませんが、21歳の“私”が忽然と現れたのです。
よく、「雀百まで踊り忘れず」といいますが21歳当時の私が、人間にとって一番大切なものは「自由:freedom」であると確信していたこと、またその自由であることを保証するのが「良心:conscience」だと思っていたことです。そこでの私の発言は、長くなりますので部分要約になりますが、「新島先生というのは非常にリベラリストでかつラディカリストであり、・・・自由への希求であったと思う。(中略)人間が人間として完全に解放される時代というのは、あるいは永遠にやってこないかもしれないが、常に社会体制、時代状況のなかで、流動をおこしていく以外に、新しいものを形成する方法はないのではないかと思う。」
とまぁ、今の私が考えていること寸分変わりません。こういう私ですので一番嫌いな生き方は忖度ですし、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という集団への同調です。しかしまぁ、「皆さん、怖いですねぇネットは。アーカイブ化されたものはなくならないのですねぇ。ではまた来週お会いしましょう、サヨナラ サヨナラ」(淀川長治)。
私のマスク嫌いは、こうして55年の歴史をもつのです。ワハハハハ!
(4月15日)
【おとぼけ川柳】 日本人 “推し”は全員 マスクマン
With マスク、Withoutマスク
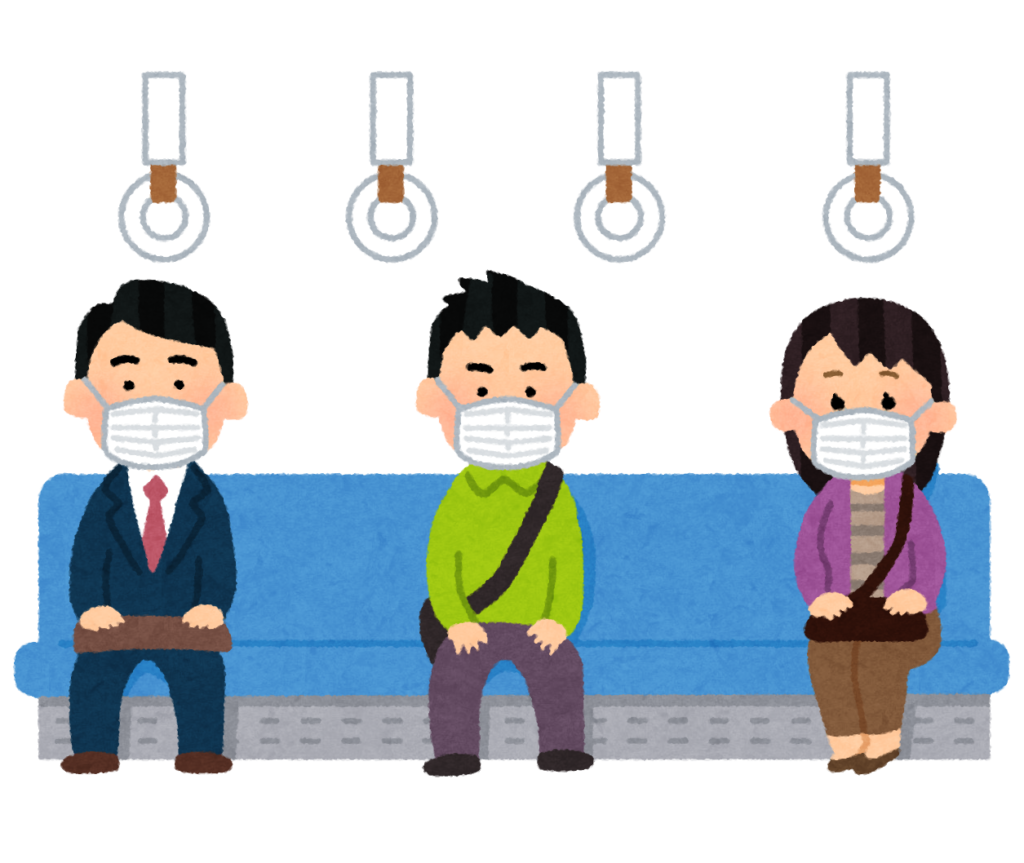
いつも私を運んでくれる学院大時代の教え子たちの車に乗せてもらい4月3日に飯田に来たのですが、到着後「先生、車のキーを」といわれてはじめて、キーを自宅に置いたまま出てきたことに気づきました。アホですねん、ボケてまんねん、トホホでんねん。
仕方がないので積んできた荷物だけ降ろしてUターン。翌4日、京都駅から新幹線で名古屋まで出て中央高速バスに乗り換え、その後タクシーで昼前に別荘につきました。で、今回は表題の話とプラスα。
近衛通から206号系統に乗り京都駅まで行きましたが季節柄、7名の外国人観光客が同じバスに乗車していました。彼らは全員がノー・マスク。比べて日本人は、私を除いて乗車している老若男女全員がマスク姿。確かにこの春、政府が満員電車やバスのような公共交通機関を利用する際には着用が望ましいとは告示していますが、マスク着用基準がゆるくなった今ですら全員着用というのは、ここがヘンだよ、日本人。
私の友人、高野陽太郎氏は、日本人は個人主義であるという論調を張っていますが、マスクマンの集団を見る限り、集団主義構成要素である同調性の強さが示唆されているように思われます。でも、昨今話題になっているガーシーとか立花孝志なんていう連中の言動を見る限り、日本的個人主義(つまりは勝手主義)全盛時代のようにも思えるし、恐らく日本の社会が大きく揺らいでいるのでしょう。それとも日本人は病的なまでに、疾病に対する恐怖心の持ち主なのでしょうか。
個人主義・集団主義というのは社会心理学の大きなテーマなのですが、スペクトラムな現代社会では、恐らくこういう二項対立的な概念自体が問題なのでしょうね。私自身は行動の基準として、それが時として他者と同じ行動につながることがあるとしても、自分の判断を重視しますので個人主義だと思っていますが。
まぁそれにしても、金を払ってもガーシーとやらのインスタグラムを見たいという人たちがいることにも驚きです。SNSという言葉、およびその内容は理解しているつもりですが、どうしてそこまで他者とつながっていたいのか、あるいは情報を共有したいのか、私にはわかりませんし理解できません。トランプのような奴に利用されるだけのような気がするのですが。
まぁ私は生涯ガラケーで、生きた化石として残された時間を過ごすつもりです。3Gの電波利用が終了になるお年寄り様は1円スマホに乗り換えて悪戦苦闘していらっしゃいますが幸い私は既に4Gに乗り換えてありますので、死ぬまで大丈夫と踏んでいます。本日電話で話したところスマホは放棄して、5G携帯に乗り換えるとか。
でもどうして電波の波長が3rd Generation(世代)とか4th、あるいは5th Generationのように変化していくのか、私には理解できていません。この問題だけではなく最近は、世の中の動きで理解できないことばかりが増えました。お迎えの来る日が待ち望まれます。ワハハハハ。
(4月8日)
【ボケたんか】 石川や 浜の真砂は尽きるとも 世に仙人の 悩み尽きまじ
トラ姫様、エリザベスになる

トラ姫様に異変が生じました。姫が左手を舐めているときふと気がついたのですが、爪の間から血がにじんでいます。これは一大事とかかりつけの動物病院に運び込んだところ、二本の爪が肉球に食い込んでいるではありませんか。ネコの爪の先は木に登るときに引っかかりやすいように曲がっていますから、これが伸びて食い込んだのですね。時々切ってはいたのですが。
ネットで調べると決して珍しいケースではなく、老齢になると多くなるとか。姫様は2010年6月20日父の日にわが家に来ましたが、恐らく4月生まれなので人間の年齢換算ではもうすぐ68歳。16歳半まで生きたメイ(通称・院長先生)も、デラウエアの自宅発フィラデルフィアーサンフランシスコー大阪、実質20時間以上のフライトで日本に帰化したウエンディ(死亡時年齢不詳)も、今までのネコは家の出入りは自由でしたから爪も自然に研がれていたようですが、京都市の条例を順守して姫様は外には出していません。若い頃は爪とぎの段ボールがすぐにボロボロになりましたが、そう言えばテーブル下の絨毯でとぐ回数もめっきり減ったような気がします。これからは爺が気をつけ、時々爪切りをして差し上げましょう。
そういう次第で肉球に食い込んだ2本の爪を切ってもらい、消毒して軟膏をたっぷり塗って貰って包帯とガード装着。加えて首にエリザベスを巻いた姿で帰宅です。ガードを巻いた左手はうまく地面をとらえられませんので三本足歩行でまぁその格好は、可哀想ではありますがやはり、プッ! 度量が広く小事にこだわらない姫様ですので、私の笑いは無視して今は書斎のカーテン裏に隠れてくつろいでいらっしゃいます。ここは来客などがあって落ち着かない時の姫様の隠れ場所なのです。
以上は27日の話ですが、翌28日はこの春初めてのきれいな青空でしたので山の神様と花見に出かけました。賀茂川の堤防敷を歩いて途中植物園に入園、その後は上賀茂橋経由北大路バスターミナルというコースです。ターミナルにあるSCは、コロナで出かけていなかった間に北大路ビブレからイオンモールに名称変更されていましたが、ここで姫様用のタタミイワシと焼きぎすを購入しバスを待っているときに、書斎のドアを閉めて出てきたことに気がつきました。普段なら姫様は、片手を伸ばして立ち上がり上手にドアを開けるのですが左手が使いにくい状態の今、もしかしてお困りではないかと気が気ではありませんでした。
帰宅してすぐに2階の書斎に上がってみたら既にドアは開いていて、一安心。下に降りると姫はダイニングでガードされた左手を舐めていらっしゃいました。そこで焼きぎすの頭と骨を外して身を差し上げ、メンゴメンゴ(死語辞典)。目力が強い姫様は寡黙ですのでニャンとも仰いませんが、まぁ包帯が外れる土曜日までは我慢して頂きましょう。
蛇足:エリザベスの発音は、正しくは/i/イリザベス/θ/です。
【ネコ川柳】 包帯を 手に巻くネコは エリザベス
(3月30日)
津軽鉄道ストーブ列車の旅

症状をお持ちの方はお分かりでしょうが、今年の花粉の飛散量はただものではありませんでした。私はマスクをしていてもその下からしたたり落ちてくる「花」水が厄介なので、マスク無しでティッシュを押し当てて歩いていました。目のかゆみもひどく、夜中に起きて目を洗浄する始末。ところで、「あったらいいな」のCMで有名なXX製薬の洗眼液は、私には効きませんでした。
例年3月第一週には花粉の飛び交う京都を離れ北海道一周の旅に出ているのですが、今年は4月から高校生になる孫を連れての津軽鉄道ストーブ列車の旅を計画していました。吉田神社大元宮お賽銭100円の効果があったのでしょうか、偏差値78の高校を含め4校全てに合格したのですが、旅の日程が入学予定校の制服採寸の日と重なってしまって、吉幾三フアンの孫は津軽の旅を断念。キャンセルが効かない格安航空券利用なので急遽山の神様を抜擢し、私の教え子にトラ姫様の世話を頼んで五能線と津軽鉄道の旅に出ました。
五能線は、シーズンにはリゾートしらかみが運行されますが普段は一日5本。五所川原―深浦間の営業係数は4852円、深浦―能代間は2364円だとか。こういう赤字路線ですから2022年8月の豪雨被害で復旧が間に合うかどうか心配でしたが昨年暮れに全線復旧。海岸線の景色を楽しみにしていた孫には残念でしたが、やれやれの旅でした。
初日の宿は海岸の露天風呂で有名な黄金崎の不老不死温泉で、日本海に沈んでいく夕日を眺めることができました。前回は大雨で露天風呂自体が閉鎖されていたのですが。しかし雲間に見え隠れするオレンジの夕日は、本当に妖しいくらいきれいでした。立花隆が臨死体験を語った中で、まぶしい光以外なにも見えない世界に進んでいくと話していたのを読んだ記憶があるのですが、正にその臨死体験を彷彿とさせる、沈み行く太陽が放つ妖しいオレンジ色の光には、生命の最後の輝きのような「なにか」がありました。
翌日は五所川原まで戻り津軽鉄道のストーブ車両に乗り込みました。しかし2台の石炭ストーブが燃えている車内は暑く、私は缶ビールだけ購入してガラガラの一般車へ移動しました。五所川原―津軽中里間のダイヤは一日12本(他に、金木―津軽中里間2本)ですが、観光用ストーブ車両をのぞけば4~5人しか乗車していません。これは大赤字だろうと思い運転席横に移動して、保線員のまなざしでレールと枕木を眺めていました。
案の定、コンクリート枕木はきちんとしていましたが栗の枕木は最悪で、レールを固定している犬釘は外れているような状態で、赤字額の大きさを象徴しているかのように見えました。五能線は観光路線として復活したようですが、皆さん、津軽鉄道もいつ廃線になるかわかりません。走っている間に乗りに行きましょう!
【乗り鉄川柳】 いつまでも あると思うな 鉄路かな
(3月24日)
啓蟄
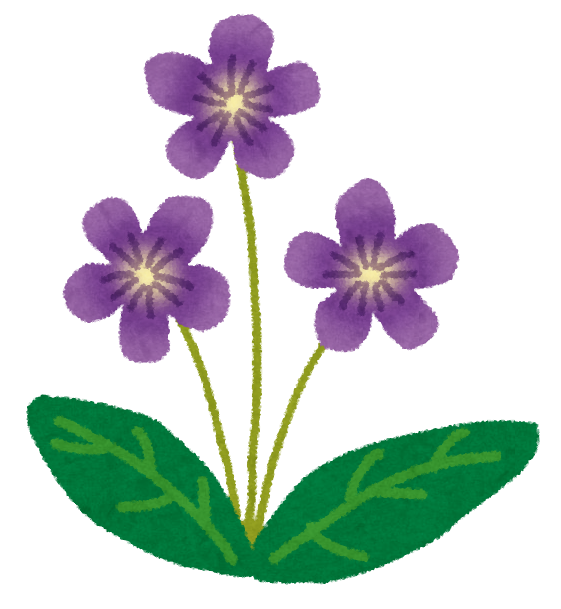
この稿を書いている3月6日は二十四節気の一つ、啓蟄で季節は大分春めいてきました。東京の四ツ谷駅線路脇には可憐な紫色のスミレが咲いていましたが、6日は私がこの世界にデビューした日でもあります。しかし76年が過ぎた今、経年劣化が進行して油切れ寸前。歩いていて老若男女に追い越されるのは日常茶飯事で、逆の追い越しは激減。同じ歩幅で歩いていると前に行く人が女性であっても離されていきます。先日など私が追い越した、恐らく1・2年生に見える小学生に追い抜かれてしまいました。きゃつらは道草しているからと安心しきっていたのですが、不覚!
地層は地球の年齢。夏の住まいの飯田市に隣接する大鹿村には日本列島を東西に走る中央構造線が露出している箇所があり、そこへ行くと地層が示す時間軸がよく分かりますが、地質学では新たに「人新世:アントロポセン(Anthroprocene)」という地層が認められました。この地層にはプラスチックや放射性物質、コンクリートなどが含まれているそうですが、人類の経済活動の痕跡が残る地層が新たに出来つつあるのです。
人類の経済活動は二酸化炭素等のガスを排出し、これが地球の温暖化につながっていることは広く知られた事実ですが、70年前に比較すると桜の開花も随分と早くなりました。東京の今年の開花予想は3月20日だとか。昔は4月の小学校入学式の頃が五分咲き程度だったように記憶していますが、今は葉桜の頃が入学式?満開の桜はピカピカの一年生という形容に相応しく思えますが、葉っぱが開いたピカピカはないような気がします。という訳で今年の夏も猛暑になるとか。先が思いやられます。
いつもお話ししていますように私は暑いの大嫌い人間。だから冬が短くなると悲しいのです。夏は全身から汗が出ますからね。一般的に高温多湿のアジア系は乾燥・寒冷地のヨーロッパ系に比較して汗をかきやすいといわれますが、私は暖房もろくに無かった頃の、しかも雪深い丹後半島に生まれましたので汗腺の数は少ないはず。つまり汗をかきにくいはずなのですが、はて、面妖な?
この問題をネットで調べるとフィリピン人の汗腺数は280万個、日本人は230万、ロシア人は190万とのことですが私にフィリピン人の血が混ざっているとは思えません。飯田から山一つ越えた上松は、長野県の郷土の英雄御嶽海の出生地ですが、彼のお母さんはフィリピンのご出身。汗かきであるかどうか、関取と比較しても問題にならないような気がしますので、これはもう笑うしかない。という訳で、今回も終わりはワハハハハ。
【へぼ川柳】 ごまかして 笑うひたいに あせ滲み
(3月6日、新幹線車内にて)
マンサクの花が終わりました
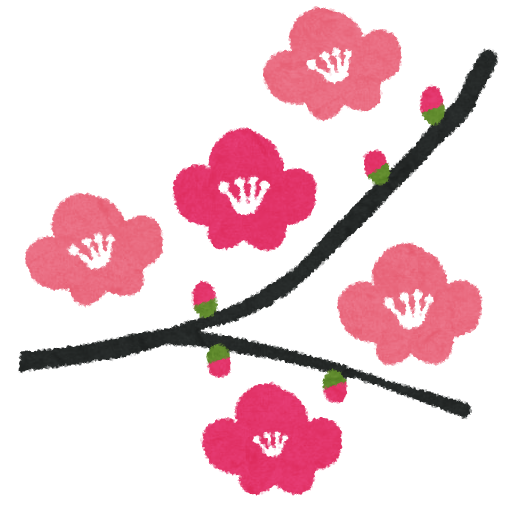
しばらくお休みをしている間に3月になり、マンサクの花も終わり河津桜が咲き始めました。相変わらずTシャツ一枚での散歩をしていますが、冬場は朝ではなく午後からにしています。先週は気温が下がって雪が降った日もありましたが、それでも時々は額の汗をタオルで拭きながら歩いているので、行き会う方から“寒くないですか?”と不思議がられます。この間は“心臓がお強いのですね”といわれてしまいました。私は自分に心の準備が出来ていない場合非常に緊張しますので、自分ではノミの心臓と思っているのですが。意味が違う?な~んちゃって(ヒゲ爺)。
ところで一部の自閉症の人は感覚が鋭すぎて衣服やお風呂、あるいはシャワーなどの皮膚へ加わる刺激が苦手の場合も多いようですが、私のTシャツ散歩は汗をかきたくないというそれだけ。でも冬場のTシャツ散歩には、これはやってみなければ分かりませんが、利点があります。肌が露出しているので太陽の光が身体を包み込んでくれる、そのほんわりした暖かさが幸せ感をもたらしてくれるのです。夏場の太陽は敵で、陽が落ちると幸せになるのですから人間、勝手なものです。このような些細なことでも幸せ感を感じられる人生に感謝!前回お話しした、月面仏の生き方です。
散歩をしていると草木に目が行きます。花は受粉を助けてくれる昆虫を呼び寄せるために蜜や花粉を用意しますが、それだけではなく花弁や香りなど、人をも引きつける様々なアフォーダンス機能をもっています。アフォーダンスという言葉は生態学心理学のギブソン(Gibson, J. J.)が提唱した概念ですが、人(有機体)と環境の間にはこれをつなぐ意味あるいは価値がア・プリオリに存在し、行為が自動的に誘発されていることを示唆しています。だから散歩をしていると自然に草木、中でも花に一番目が行くのでしょう。
散歩のコースには様々な花が咲きますが、早春の花といわれる梅は南側斜面では正月から咲いていますし、ボケやユキヤナギの花も1月には既に枝の所々に開花していますので、春の近づきを知らせる花としては面白くありません。その点マンサクとロウバイは狂い咲きのような例外のない、春への時系列を実直に示しているように思います。
3月に入るとコブシの芽も大分膨らんできましたし、気温も上がってきましたのですぐに桜が開花するでしょう。しかし最近では、桜が咲いても昔ほど感動しなくなりました。昔は私も西行法師のように「願わくは花の下にて春死なん」と思っておりましたが。感動が薄れてきた原因は、どんどんひどくなる黄砂のせいのような気がします。春は朧で霞がかかるのは昔からでしょうが特にここ十数年、PM2.5を含む黄砂の飛来量が増え、青空がなくなってきました。中国大陸の乾燥化が進行しているのですね。青空がなくなると桜に対する感動も薄れます。
宇宙船地球号では全てのものが繋がっています。ロシアのウクライナ侵略も街を壊しているだけではなく、自然環境も破壊しています。これが温暖化を加速させていると思うのは、牽強付会でしょうか。一日も早い停戦とウクライナからのロシアの撤収を望みます。
【ボケ川柳】 黄砂かな いや花粉かも はなずるり
(3月1日)
日面仏 月面仏

プーチン・ロシアがしかけた侵略戦争によりウクライナでは日常的に市民が死んでいきますが、今度はトルコとシリアを大地震が襲いました。シリア北部はアサド政権の支配が及んでいないところらしく詳細な死傷者数は不明ですが、両国併せて4万人を越える死者と報道されています。まずはこれらの国々で、非業の最期を遂げられた方々のご冥福をお祈り致します。
このような現実を目の前にすると、カゲロウほどではないにしても人の一生のはかなさを考えさせられますが人間も動物。いつかは終わりが来ます。後期高齢者の私は既にカウントダウンが始まっていますが平穏の内に、静かに終わりたいものです。
表題は「にちめんぶつ がちめんぶつ」と読みますが唐時代の禅僧、馬祖大師の臨終の言葉であるとか。Webでこれを検索すると臨済禅・黄檗禅公式サイトの「臨黄ネット」が出てきますので、詳しくはそちらをお読み下さい。ただ今回、なぜ私がこの言葉を取り上げたのかその意図は、就寝前に「ああ、今日も特筆すべき何事もなく終わった」と思える日々は「善き哉」と思うからです。それはストレスがない今の私の境遇を示唆します。
現役時代、ストレスと飲酒量は正の相関関係にありました。『じゃりン子チエ』と『うる星やつら』が寝る前の愛読書であったことは先週お話ししましたが、酒を飲まないと寝付けない日々も多々ありました。但し私、意志は強い方(だと思っています)で、飲まないと決めたら一滴も飲みません。週一日を禁酒日としたのが30歳を過ぎた頃でしょうか、これが徐々に増え3年前の禁酒日は175日、一昨年は192日、昨年は211日でした。Progressiveでしょう?
しかし若い頃はよく飲みました。土佐藩15代藩主山内容堂候は「鯨海酔候」を名乗っていたとのことですが、私もその昔、酒なら一升、ウイスキーなら一本、ビールなら1ダースと豪語していました。私淑しておりました大阪大学名誉教授の糸魚川直祐先生は若い時、友人たちと飲んだビール瓶を部屋の周囲に並べて一周するまで飲んだとか仰っておりましたが、さすが一人でそれは無理!しかし6軒くらいはしごをした時期もありました。
私の友だちが店を訪ね、和尚はと問うと“今、お帰りになりました”の繰り返しで、とうとう追いつけなかったという都市伝説も残っています。友人も結局は、はしごをしているわけですが。最近では真夏にサウナ浴をした日でも500ミリを3~4本飲めば、それ以上は欲しくなくなりました。ハイボール2杯くらいは追加ですが、ま、これはご愛嬌。でも、若いときほど飲めなくなりました。老いですね。
トラ姫様には、“俺より先に 死んではいけない”と『関白宣言』がしてありますが、人には自分のロウソクの灯がいつ消えるか分かりません。だからストレスから解放された今、月面仏の一日が終わった無事を感謝することの繰り返しで、人生はそれ以上のものでも以下のものでもないと思っています。1800歳の日面仏も、考えて見れば65万7千回の一日が無事であったということで、無事がなければそれは続きません。それ故に無事は、何物にも代えがたい有り難いものなのです。
追記:必須の言葉を忘れていました。ウクライナに一日も早い平和がくることを希求します!
(2月19日)
ネコミュニケーション
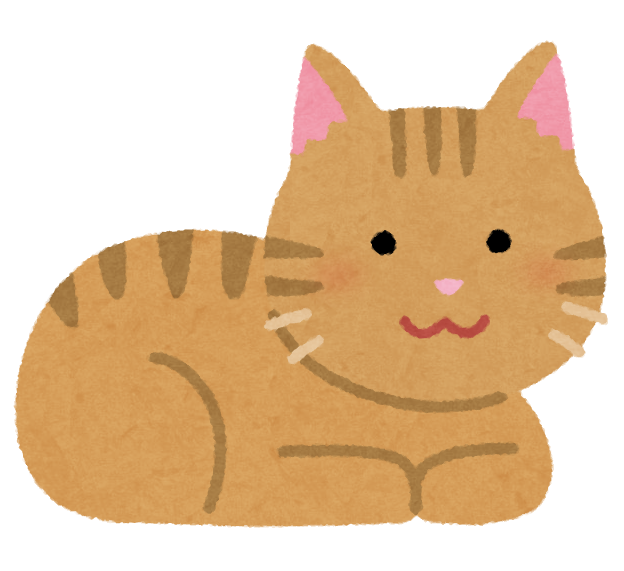
わが家には今は懐かしい昭和のギャグ漫画、はるき悦己の『じゃりン子チエ』と高橋留美子の『うる星やつら』が全巻揃っています。共に、当時小学生だった子どもが友だちから借りてきたものを読んではまってしまい、以来発売と同時に買うようになりました。今でこそストレスもなくなりましたが昔は講義の下準備(本務校3科目、他に京大・奈良女・京都教育などの非常勤先4科目)や科学研究費助成による母子愛着研究、データ整理に論文執筆とそれこそストレスだらけ。ベッドに入ってもなかなか寝付けない日も多く、この2つのギャグ漫画は寝る前のリラクセーションにうってつけだったのです。で、今回は『じゃりン子チエ』の話。
非常に濃いキャラの持ち主が掛け合い漫才的に登場する『じゃりン子チエ』ですが、桜が咲く頃になると主要キャラのジュニアという名のネコがノイローゼになります。春のノイローゼという設定はネコの発情期が下敷きになっているでしょうが、私は作者の花粉症もこれに影響しているのではと思っています。ま、それはともあれ漫画には、ノイローゼになったジュニアへの堅気屋のおやじ(百合根光三;飼い主)の叱咤激励ニャニャ語会話が出てきます。とうぜん( )書きで翻訳されていますが。
岩合光昭さんは「いい子だねぇ」としか言いませんが、堅気屋の親父はかなりのネコ語ボキャブラリーの持ち主。見習って私も、冬場限定ですがトラ姫様と毎朝ニャニャ語会話をしています。姫は自閉症ネコですから自ら「ニャァ」と話しかけてくることは非常に希です。発語は少ないのですがその分「目力」が強いので、何か欲しいときは私が気がつくまでじ~っと見上げてらっしゃいますし、時には手が出てきます。「食べるか?」と問いかけると舌を出してつばを飲み込むこともあります。喉が動くのですよ、リアルにゴクリと。
こんな自閉症ネコのトラですが、状況に応じた様々な「ニャァ」があります。一声の短いニャ、降参の小声のニャ、小さい声で反復のニャニャ、面倒げなニャ~ァ、普通のニャン、激レアな身体を擦り付けての甘えのグニャァ、トッピング催促のンニャなど、10数種類に近いでしょうか。毎朝、リビングから書斎に上がるとき、私が「トラ、ニャニャ!」と話しかけると姫様も「ニャ~」とお応えになりドアを出るまではゆっくり、出たら階段を駆け上がって書斎の前で待ちます。またその時のお気分によって何度もニャニャと言わなければならないこともありますし、まだ水を飲んでいないとかもう少しグパン(ご飯のこと)を食べてからとか、理由を付けてご自分の食卓の方へと途中で方向が変化することもありますが。
冬場は起床後にエアコンをつけておきますから入室後は机に飛び上がってプリンターの上に乗り、私が椅子に座るとあぐらの上に移動して、顎が膝と足裏が交差した窪み?部分に置かれます。くつろいだ格好なのです。しかし私も、同じ姿勢をしていると私も足が痛くなりますから立ち上がろうと思うその時、何かを感じるんでしょうね、間髪入れずに先に立って横の木製椅子に移動します。で、私が帰ってくると先ほどまで私が座っていた書斎椅子で丸くなっていらっしゃいますので、私が木製椅子に座って仕事をすることになります。
こうして今日も、『ネコと爺ちゃん』【ねこマキ(ミューズワーク)】の生活が続きます。
【ネコ川柳】 トラだけが テッサもらうと 孫がすね
(2月12日)
追儺式

私が住まいする吉田の地名は、御所の鬼門にあたる東北を守るために建立された吉田神社に起因しますが、元々は藤原氏の氏神社であったそうです。鎌倉以後は卜部氏(後の吉田氏)が代々神職を務め、江戸時代には全国の神職の任命権(神道裁許状)が与えられたとかで歴史があるのですがなにせ鬼門ですから鬼に縁が深く、節分は参拝者で大賑わい(二日で数十万人)。2・3両日は交通局が臨時バスを出しますし、京大正門前の東一条通と参道両側(一部複式)に、数えたことはありませんがびっしりと露店が並びます。広報によるとその数800店とのこと。今年歩いてみた感触では2百数十程度?家の前の通りも裏参道に通じていますので、時に大元宮からのお参り帰りの人たちの声がします。
私は寺に生まれ育ったので神社にお参りする習慣はありませんが、吉田に居を構えましたので吉田神社の氏子ということになり、寄付をしています。郷に入っては郷に従えで理屈はこねません。だからお祓いをしますのでお越し下さいという案内が届き、いつも山の神が去年のお札を納めるついでにお祓いを受けていらっしゃいます。「イワシの頭も信心から」で、信仰心がある人はない人よりも長寿であることが確認されていますので、寅さんの啖呵売ではありませんが「結構毛だらけネコ灰だらけ」。毎年露店をひやかしています。
鬼は2日の夕方6時から出てきます。宅でも子どもが小さいときは鬼の出勤時間に併せて出かけましたが、子どもは怖がりますね。鬼もサービスで、子どもの前に「ウオー」と吠え声のド迫力で顔をさらします。私の教え子に、隣町の岡崎で育ち毎年お参りをしている身長180、体重100キロの大男がいますが、この男でも心の芯から怖かったと回想しています。
節分当日の3日は夜11時から、消防の管理の下、集まったお札やしめ縄を燃やす火炉祭がおこなわれ、翌4日朝は煙の臭いが辺りに立ちこめています。これも若かった時は見物にいったものですが、今年は76歳。もう昔の元気はありません。晦日庵川道屋のれん会が出している年越し蕎麦を楽しみにしていますが、テントで覆うからでしょうか、今年は出店されていませんでした。
重要文化財指定に指定されている大元宮は3ケ日が解放され、ぐるりと一周すると全国の式内社にお参りしたことになる便利なシステムになっています。祭られている各国の神社は式内社とのことですが、寺育ちの私には何のことかわかりません。調べたところによると式内社というのは、平安時代中期の『延喜式神名帳』に記載されている社で、全国に2861社あるんだとか。しかし国によって、その数に随分違いがあります。例えば京都は山城国(122社)、丹波国(71社)、丹後国(65社)が祭られており、そこにお賽銭を供えて自分の鎮守様に願い事が出来ます。便利ですよ。
この、祭られている式内社が一番少ないのが薩摩で2社、次いで伊勢神宮の志摩と厳島神社の安芸がそれぞれ3社、筑後、肥前、肥後、日向はそれぞれ4社、長門と上総はそれぞれ5社が祭られています。さすが畿内は多く、大和と伊勢はそれぞれ286と253社、近江は155社、また神様の本場?出雲は122社です。陸奥は100社が祭られていますが、鎌倉時代日本の北は出羽と陸奥国しかなかったからでしょうね。ちなみに出羽国は8社です。
文字が生活の中に入ってくるのが弥生時代後期ですが、宗教はまだ渡来していません。私が習った仏教伝来年は「仏は午後に百済から(552年)」でしたが今は「仏さまゴミ払いして上機嫌(538年)」だとか。だから仏教伝来以前は恐らくしめ縄のような結界を張った、天地の森羅万象八百万が信仰の対象となっていたのでしょう。最近の見解では稲作の起源は縄文時代後晩期(約3~4千年前、佐賀・菜畑遺跡)に遡れるそうですから(農林水産省)、しめ縄は縄文時代にはもうあったんじゃないかな?ま、一神教の信仰と違って八百万の神は融通無碍、平和なものです。私も孫の高校合格をお願いしておきました。
【節分川柳】 百円で 願いがかなう 大元宮
(2月4日)
次元の異なる子ども政策・・・、はて?

第211回通常国会が始まり、岸田総理が施政方針演説を行いました。日本の国政を俯瞰するわけですから荒っぽい筋にならざるを得ませんが、相変わらず言葉だけが踊っています。安倍さんもそうでしたが岸田さんも「三本」がお好き。安倍さんは長州でしたから毛利元就の「三本の矢」の話は恐らく子どもの頃によく聞かされていたのではないかと思いますが、岸田さんの地元は安芸。矢が柱になって飛び出してきました。「また出たと、坊主びっくり貂の皮」です。
「新しい資本主義」も何のことかよく分かりませんでしたが、今回は「次元が異なる少子化対策」とのことです。昔、「言語明瞭意味不明」と言われた竹下登という総理大臣がいましたが、岸田さんも言葉明瞭なれどもそのつながりが今一。思うに岸田さんはおそらくその少年時代、アイザック・アシモフやR. ハインラインなどのSFに傾倒されていたのでしょう、「新しい」とか「次元」とか、変化を示唆する言葉がお好きのようです。しかし高校時代の物理(5単位)は最高で3しかとれなかった文系人間の愕然は、次元なんていわれるとすぐに宇宙船エンタープライズのワープ航法を思い出し、ついていけません。
で、その三本の柱の一本が最重要政策と位置づけられる少子化対策ですが、これにもまた3つの基本的方向性があるそうで、その一つが「出世払い型の奨学金制度」。先のコロナ対策では「雇用調整助成金」、「事業再構築補助金」、「緊急雇用助成金」など数多くの助成金がばら撒かれ、返済されないものも数多いとか。なにせ経産省のキャリア官僚からして「家賃支援給付金」と「持続化給付金」併せて1500万円をだまし取ったくらいですから、驚くべき金額のばらまきと詐欺的ごまかしが行われたはずです。MMT理論に従えば幾らお札を刷っても国家は破綻しないらしいですが、こういう施策の元では詐欺師が増えて民度が劣悪化することは防げません。
そこで岸田さん、「反省だけならサルでも出来る」と言われたくなかったのでしょう、三本柱の目玉として18歳の若者を借金漬けにし、貸してやったんだから子どもで返せと、お代官様や越後屋も思いつかなかった「出世払い型の奨学金制度」を出してきました。確かに次元が異なると言われればその通り。一度も国会に出席しないユーチューバーや年金保険料を数十年に亘り未納していた輩たちが国会議員になり、議員報酬として年5183万8千円の支払いを受けているという歪んだ「次元」、ニャントかニャリませんかねぇ。
少子化の原因は決して単純ではなく、多くの要因が複雑に絡み合っていますのでブログのような短い文章で論じることは出来ませんが、教育費の高騰も一つの原因であることは確かです。親の給料は下がる一方で子どもへの教育投資は嵩む一方。DXかクラウドか知りませんが、高等教育を受けていないと良い就職口がない?らしいのです。私は問題の根源は、画一化されていた日本の義務教育にあるような気がしていますが、これについては稿を改めます。
ただ皆さん先刻ご存じのように、スエーデンやデンマークなど7カ国では大学授業料は無料です。財政赤字のギリシャが無料というのには驚かされますが、有名大学に入学するためには塾?でそれなりの勉強をしなければなりませんので、教育費全体が無料というのではなさそう。でも、これは日本の大学授業料を考える場合のヒントになります。私はかねてから、私立大学で学んでも国公立大学の授業料相当分は国家が負担し、残る学費を学生負担とするべきだと主張しています。
調べたところによると現在の国立大学の初年度納入金は平均で817,800円であるとか。私は1966年に同志社大学文学部文化学科心理学専攻に入学しましたが初年度納入金が10万円程度だったと思います。二年次以後の学費は諸経費込みで6万円台だったのでしょうか、国立との学費差は生活実感から見る限りそれほど大きくなかったと思います。当時私はなぜか特別奨学生でしたが、学生運動で(安田講堂籠城事件が起こったのは2年次)2回生の時にとった単位が僅か8単位。という次第で3回生の時は単位不足により奨学金一年休止でしたが、月額8千円(内5千円分は返還義務のない貸与)もらっていました。当時のアルバイト代は単純事務系だったら時給80~100円の範囲だったでしょう。
ところで私学にはそれぞれに建学の精神があるわけで、仏教やキリスト教など、その背景に宗教を背負った大学も数多くありますし、関西では企業がバックボーンの大学も幾つかあります。最近では京都学園大学が日本電産の永守さんを受け入れ注目されていますが、入学希望者はそれぞれの私学の特徴を調べた上で入学を決定していると思います。なぜか寺の息子であった私は同志社に進みましたが。ワハハハハ。
ですから全くの無料を主張するものではありませんが、例えば母校同志社大学心理学部の場合、調べたところによれば初年度納入金は1,304,000円(2年次生1,208,000円)です。もし独法大学授業料分82万を無償給付すれば差額は426,200円(2年次以後約39万円)になります。これなら頑張れば何とかなる金額でしょう。ところが岸田案は金は貸すが将来返してねという訳ですから、同志社の心理に進んだ場合、仮に学費の全額を出世払い型無利子奨学金助成を受けたとしたら4年間の総額4,616,000が借金になり、これを20年で返済するならば毎月19,233円が必要になります。
奨学金が幾ら貸与されるのか知りませんが、結婚して家族を持てば生活費も入用ですからこれは大変でしょう。よってこどもは産まないということになりませんか?岸田さんの施策はこのように、確かに次元が異なる少子化対策なのです。
ダーキシ、若者を借金漬けにしようとするお前はなに考えとるんじゃ。国に尽くすのなら国会議員歳費を半分返納し、ちと古いがお国に対して“滅私奉公”しなされ。
喝!
(1月29日)
アンディ・ウオーホル展とルートヴィッヒ美術館展
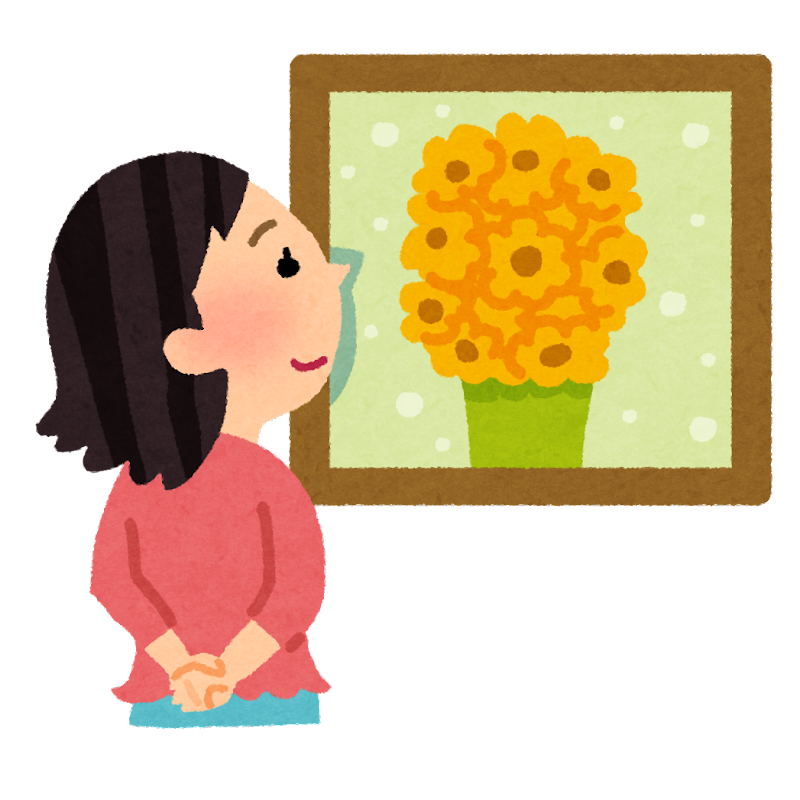
夏は庭の芝生に雲鼓をしていくタヌキ、トラ姫様を驚かすヒキガエル、どうやら天井裏に下宿しているらしい2mほどの青大将、ブルーベリーを食べに来るスズメバチやきれいな声でさえずりを聞かせてくれるシジュウカラ、エナガなど、家の周りは生命にあふれています。散歩をしているとサルやシカ、オコジョにテン、昨年はうり坊まで出てきてこんにちはの生活環境ですが、冬は“文化”が色濃い環境になります。自宅は左京区吉田ですので京都大学が町内に、隣の町が岡崎ですから動物園や平安神宮、国立近代美術館、京都市京セラ美術館、ロームシアター京都、市立図書館などがある文教地区なのです。という訳で今回は芸術のお話し。
12日木曜日、よく晴れた暖かい日だったのでアンディ・ウオーホル展とルートヴィッヒ美術館展に行ってきました。京セラ美術館と近代美術館は平安神宮の大鳥居をまたいで対面位置にありますから、まずは京セラ美術館のウオーホル展から。ウオーホルはアメリカにいたときにメトロポリタン美術館によく行きましたので何度も見ていますが、当然解説はついていません。という訳で今回初めて彼が性的マイノリティであったことを知りましたが、彼のシルクスクリーンの作品を見ながらあることに気づかされました。彼の心の中にある“禅的”なものです。単純さの中に複雑性の調和を追求する禅同様、ウオーホルも単純の中の複雑を追求したのではないかと思ったのです。
余談ですが「無」とは、森羅万象が融合し究極に安定した状態、つまりゼロなのではないでしょうか。だから「無」の反対は「有」。隻手の音声、あるいはビッグバン理論ですね。
彼は1956年に初めて京都を含む日本を旅したそうですが、日本食大好き人間になり生涯NYのレストランSASAKIに通ったとか。また、600個ものタイムカプセルを作りその中に様々な思い出の品を閉じ込めたそうですが、SASAKIからの請求書も何枚か展示されていました。ま、それはそれとして私が気になったのは展示場に記されてあった以下の言葉です。
I don’t believe in it (death), because you’re not around to know that it’s happened. I can’t say anything about it because I am not prepared for it.
(私は死を信じません。だって(私に質問している)あなたは、それが起こったことを知るときにはそこにいないのですから(私が死んだと言えますか?)。私は、死に対する準備をしていないので(これ以上)なにも言えません。異訳)
蛇足ですが当日私がチケットの裏にボールペンでメモし始めたら係の方が飛んできて、「館内ではボールペンは使用できません。鉛筆をお貸ししますのでこれをお使い下さい」ということでした。筆記具に関するこの規則、皆さんご存じでしたか?
ウオーホルは東方正教会の信者だったとのことですが、死を語る彼の言葉にはキリスト教の“救い”の思想が見当たりません。死というものをごく自然に、「人間でも動物でも永遠はないよ。その時が来たら旅立つだけさ。旅立ちがどのようなものであるかは、帰ってきた人がいないからなんとも言えないね」といっているかのように思うのは、深読みのしすぎでしょうか。
ところでなぜ私がそこまで深読みをするのか、理由は葛飾北斎にあります。北斎がゴッホやゴーギャン、ルノアールなどの近代美術に大きな影響を与えたことはよく知られていますが、ウオーホルの作品の中にも北斎の波を模したスケッチがありました。私は高校時代の美術教育以上の知識をもっていませんが、西洋の“美”に対する意識は印象派を境として大きく変わったと思っています。素人考えですが、印象派以前の“美”はシンメトリーにありました。ダ・ヴィンチの最後の晩餐の人物配置は一つの典型でしょう。フェルメールの人物画もそうです。これを打ち砕いたのが北斎で、印象派以後はシンメトリーにこだわらず、画家が受けた印象を心象風景として表現するようになったと思っています。
という訳でシルクスクリーンを意図的にずらして表現するウオーホルは、心の中に発生する揺らぎをアンシンメトリーで、つまり先に述べたように複雑性の融合を、シンプルだけどもぼやけた線で表現しようとしたのではなかろうかと思うのです。
皆さんもリュクサンブール宮殿の庭はご存じでしょう。同時に嵐山天龍寺の庭もご存じだと思います。前者はシンメトリーを、後者はアンシンメトリーを基本に設計されています。私はこの日本人の美的感覚を「おかめ・ひょっとこ文化」と形容していますが、自然の中にはシンメトリーとアンシンメトリーが共存しています。例えば木とその葉です。
木は葉っぱで太陽の光を集めなくてはなりませんからその枝は決してシンメトリーな姿にはなりませんが、葉っぱは基本シンメトリックです。しかし草木が生えている山や川、あるいは岩や谷はその形成の過程からしてそもそも対称ではあり得ません。このように考えるとシンメトリーな美というのは人間の手によって造られた人工の美であることが分かります。だから個を重視するようになった近代以後、哲学的に言えば“我”を発見したデカルト以後ということになりましょうが、印象派以後の画家たちは自然に存在するアンシンメトリーを心象風景として表現するようになったと思っています。
12日は加えてピカソやロシア・アバンギャルド、あるいはウオーホルに代表されるポップアートの名品を集めたルートヴィッヒ美術館展も鑑賞しましたが、美術館のはしごはお勧めできません。疲れます。
という訳で〆は、三条白河「枡冨」の「かもせいろ大盛り」でした。蕎麦はのどごし、つるりと胃の腑に収まりますが愕然の話は収まりが悪いかも知れません。にも関わらずここまでお付き合いいただき、有り難うございました。ペコリ!
胃もたれが起きていませんように。合掌
(1月22日)
おせちも家庭の味

前回は、おせちの話を書こうと思って一茶の句を思いついたらトントントンと目出たくない話になってしまい、申し訳ない。そこで閑話休題。
皆さんのお宅もそうでしょうが各家庭の味はそれぞれ微妙に異なります。いわゆるお袋の味ですね。わが家も創設以来51年になりますので、今では女房の料理が一番美味しいと思うようになりましたが、最初からそうだった訳ではありません。なにせ北大路魯山人か吉田中大路の愕然和尚かといわれるくらいですので、ここまで来るにはバトルがありました。それぞれ異なった味が刷り込まれた夫婦の舌の間で小競り合いが繰り広げられ、やがて天下統一に至るのですが、我が家では決着まで7年かかりました。
一番、時間を要したのは吸い物の味です。お年寄り様が私に味見を要求せず、ハマグリの吸い物を食卓に並べるようになったのが結婚後7年目でした。映画「7年目の浮気」は、地下鉄から吹き上がってきた風でマリリン・モンローのスカートがまくれ上がるシーンで有名ですが、当初はラブラブだった二人も7年も経つとお互い?がマンネリ化して、浮気心の一つも芽生えますよという話です。でもこれは、互いの味の統合には7年かかりますよと読み替えることも出来ます。
グルメの愕然が初めて作った料理はキャベツの芯のスープでした。小学校時代は学校の図書室にある全ての本を借り出して読んだほどの乱読ですが、中学時代からロシア・東欧・ドイツ諸国の作家に入れあげていました。で、ツルゲーネフだったかドストエフスキーだったか、はたまたゴンチャロフだったかは忘れましたがある作品にキャベツの芯で作るスープの話があり、自分も作ってみようと思ったのがクッキングのきっかけでした。大正5年生まれの母からは、男子厨房に入るべからずと言われましたが。
父親は禅坊主でしたから何でも器用にこなしました。おせち料理も、その味付けは父がしていた記憶があります。ところでおせちの中で、火加減・味加減が最も難しいのが田作(ゴマメ)です。田舎にあった我が家では、竈に鉄鍋を乗せて加熱しておき、田作を放り込んでしゃもじでかき混ぜて軽く煎ります。煎るときは田作の表面を見ながら堅過ぎず焼き過ぎず、これがまた難しいのですが頃合いで拡げた新聞紙の上に拡げて一旦熱を冷まし、鉄鍋にみりん・醤油・酒・タカノツメのだし汁を放り込み、直後、先に冷ましたておいた田作を放り込んでしゃもじでかき混ぜ味をしみこますのが手順でした。ここでのポイントは煎り加減、つまりは鉄鍋の火加減です。
我が家は今でもこのやり方で田作を料理していますが、火口にセンサーが着いた最近では空の鍋を熱することがなかなか難しいのです。空だき防止ですぐに火力が弱まってしまいますから、鍋を加熱するのに一苦労。火が弱まる度に再点火をして熱し、そこに田作を放り込んでかき混ぜる必要があり、私がかき混ぜ役、お年寄り様が点火役と二人がかりなのです。トラ姫様は「大儀である」と、配膳カウンターの上でご覧になっていますが。
田作はこのように手間がかかるおせちですが、時間がかかるのがコンニャクです。コンニャクは一枚を半分に切りそれを更に短冊に、一枚を大体12~14切れにします。今年はコンニャクは五枚と、それこそ客が多かった時代の半分にまで減らしましたが、大きな鍋に油を入れて表面が白くなり、泡がぶくぶく出てキュキュと鳴き始めるまでかき混ぜます。客が多いときは10枚のコンニャクを炒めましたので、30分がここまでの時間の目安でしたが5枚の今年は20分程度でした。
その後はだし汁(前夜から水に浸けておくいりこ、利尻昆布、削り節)、酒とみりん、砂糖に醤油(2種類)、秋田のしょっつるで味付けをしてタカノツメを加え、約30分煮込みます。ポイントは白い泡が出てくるまで油で炒めること。こうすると、コンニャクの別名は山フグですが、その名のとおり歯触りがプリプリしてフグに似た食感になります。是非、お試し下さい。
堀川ゴボウは京都以外では手に入らないと思いますので作り方は解説しませんが、棒鱈の甘辛煮もおせちのメニューで重要な役割です。棒鱈は全国どこでも手に入る食材だと思いますので、料理前のポイントだけ。要は水を頻繁に替えて臭いをとることに尽きます。鱈は乾燥素材ではなく、お店で売っている水で戻したものを買っていますが、料理の前日から水を替える度に、そうですね、10回位は洗います。そうすると臭いも全くなくなり、美味しく炊きあがります。
笑いが入る余地のない、ハウ・ツーものになってしまいました。仕方がないから自分で笑っておくか。ワハハハハ!
(小正月前日、1月14日)
「目出度さは皆無なりけりおらが春」
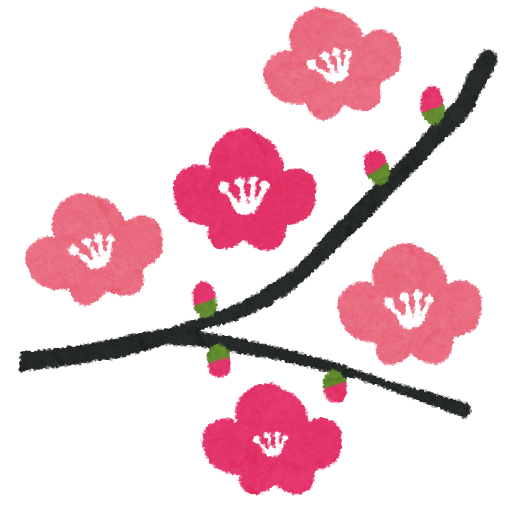
「目出度さもちう位也おらが春」は一茶57歳の時に詠んだ句とのことですが、ウクライナでは今もロシアによる社会インフラの破壊が続いていますし、真偽は判然としませんが後述するように日本も、ロシアからの侵略にヒヤリ・ハットであったとか。加えてロシアは天然資源や食料などを戦略物質として戦術的に利用していますので、世界各地でインフレの昂進が顕著で、これを抑制するためにアメリカは高金利政策を採り続けています。
そのため日米金利差で円安が止まらず、10月21日は151円91銭まで下落。さすがたまらずの黒田総裁の日銀公定歩合操作で、10年物国債利回りを0.5%にしたことでやや持ち直していますが(現在132円07銭)、円安=輸入物価高騰ですので11月の労働者実質賃金は-3.8%であったとか。
日本の近隣も相変わらずきな臭いです。隣国、北朝鮮は自国民の生活をないがしろにしてミサイルばかり打ち上げていますし、戦狼外交の中国はゼロコロナから突然with coronaに政策変更をして、中国からの入国者にPCR検査及び陰性証明の提出を求める諸国に対し、“科学的”に対処しろと恫喝を加えています。死体の焼却が間に合わず、火葬場に門前市が出来ているにもかかわらずです。さすが白髪三千丈の国ですね。中国政府発表によるとコロナによる死者は昨年12月以来今日まで、わずか22名なのだそうです。
ということで愕然にとっての今年は表題通り、「目出度さは皆無なりけりおらが春」、です。
ま、それはどうでもいいのですが「やはり変だよ、日本列島。北は大雪・南は暖冬」というか、世界各地は例によって異常気象。ウクライナのキーウでは桜が開花しているとか。これもいつどう変化するかわかりませんが、今年の暖冬はロシアによる徹底したインフラ破壊の渦中で暖がとれない戦場にある身にとっては有り難いと、報道1930のインタビュー場面でウクライナ側の指揮官が話していました(2023/01/05、報道1930、TBS)。プーチンはロシア正教のクリスマスにあわせた休戦を申し入れたそうですが、36時間だけであるとしてもウクライナの市民の上にミサイルが落とされませんように!
ところで、皆さんご存じでしたか?昨年11月25日版ニューズ・ウィークによると、真偽は定かではありませんがロシア連邦保安庁内部告発者から得られた情報として、プーチンはその当初、日本を侵略目標としていたのだとか。以前使いましたが映画評論家の故淀川長治さんの決まり文句、「怖いですねぇ、恐ろしいですねぇ、もしそうだったならばもう皆さんとはホントに、さよなら、さよなら、さよなら、ですねぇ」が現実のものになっていたかも。
でもどうしてこのような侵略や恫喝の思想がロシアや中国に根付くのか,お爺さんなりに考えて見ました。お爺さんのたどり着く結論に対しては恐らく両国共に、昔お前の国が侵略をしてきたではないかとおっしゃるに決まっていますが、そのfactは否定しませんし、深くお詫びします。しかし現況としてのfactは何が原因であるかを思索してたどり着いた結論は、ロシアではツアーリの専制政治が何百年も(イヴァン雷帝、1480年)、中国では皇帝の専制政治が2000年以上に亘り行われていた(秦の建国、紀元前260年)ということでした。
ロシアにはヨーロッパ諸国同様封土をもった貴族がいて、それぞれの領地を支配する封建制の側面もありましたが、ツアーリを筆頭とする貴族や裕福な市民、聖職者たちが農奴の労働成果を収奪していましたし、農奴は所有者によって売買されていました。また中国は皆さん先刻ご存じの通り、その3000年の歴史の中で、隋の時代に始まった科挙制度によって選抜された官僚が皇帝の命令を実行する中央集権国家でした。今の中国共産党も習近平しか見ていないという話ですが、自分が階段を上ることしか考えていない官僚が農民を収奪する社会が、随からですから1500年以上続いた国です。ですから愕然は、ロシアや中国の人々はプーチンや習近平という専政者に対して、さほどの違和感がないのだろうと思っています。
これに対してヨーロッパ及び日本の政治体制は近代まで封建制を採用しており、皆様ご存じのように封建領主が治める地方分権制度を基礎としていました。つまりヨーロッパでは国王が、日本では幕府が、自治を認めている諸侯・諸藩の内治に介入することが出来ない制度だったのです。私は歴史家ではないので詳細な議論はできませんが、個人的にはこの地方分権制度が日本の近代化に際して大きな力になったと思っています。
平たく言うならば、それぞれの地方に商人階級というほどほどの富を蓄えた市民が存在したこと、また武士という、利よりも義を重視した階級が一定程度存在したことが、近代の産業資本社会への移行を容易にしたと思うのです。英語でin-divi-dual(分割できない)と表記される近代を担った個人は日本でも、神という絶対者がいるヨーロッパとは異なる形で、封建制度の中で準備されていったのでしょう。この問題は改めて論じます。
また難しい話になってしまいました。年末におせち料理の話をしましたので我が家のお正月の話を書こうと思っていたのですが、書き出しを一茶の「おらが春」にしたところ、中どころかまったく目出度くないやないかと、いつの間にかこんな話になりました。次回こそクスリと笑って頂ける話にしたいと思います。メンゴメンゴ!(コミック「ねことじいちゃん」、あるいは死語辞典参照)
(1月7日)
暮らしのパターン

皆さんのお宅もそうでしょうが、私宅の年末・年始の暮らしのパターンはほぼ決まっています。年末は漂泊の俳人、山頭火が愛した川棚温泉の「小天狗」でフグのフルコースを楽しみ、下関の唐戸市場で数の子やごまめといったおせちの素材を購入しますが、今年も23・24で行ってきました。今回の話はその顛末です。
私ども夫婦は未だにガラケーですので、皆さんのようにスマホで情報を検索することが出来ません。ですから旅行に出る前は、乗り物の発着時間やどこに立ち寄るかなど、かなり綿密な計画を立て手帳にメモをしておくのですが、なにせ私は筋金入りの注意欠如型ADHD。京都駅までのバスの中で手帳を忘れてきたことを思い出しましたが後の祭り。まぁ大体は頭の中に入っていますのでそれを頼りの出発になりました。
京都駅には予定通り11時40分過ぎに到着しましたがここで最初のトラブルが。私は普段EXカードで乗車していますが、お年寄り様の切符も併せて予約しましたので乗車券の発券を受けなくてはなりません。窓口の混雑は予想していましたので時間に余裕は持たせていましたが、やはり駅はかなりの混雑。烏丸口のみどりの窓口には並ぶこともなく、2階改札横の窓口に並びましたが、列は遅々として動きません。そこでお年寄り様を列に並ばせておき、私は一番人が少ないと思う新幹線改札横の窓口に移動しました。
この読みは当りでしたがお年寄り様を呼ばなくてはなりませんので、「下にいる」と電話しました。しかし、現れません。「話の聞けない男、地図の読めない女」の電話を介しての話ですから通じないのは当たり前・・・? 2階にいた私にとっての「下」とは新幹線乗車口横の1階窓口と告げたつもりなのですが、お年寄り様はこれを烏丸中央の窓口と思われたらしく、ここで最初の行き違いが発生しました。
二度目の行き違いは私に原因があります。当日の二人分乗車券と翌日のお年寄り様乗車券を購入し、発車時刻の7分前くらいに改札を通りましたが、ビールを買って行くので先にホームで待っていてと、お年寄り様に指示したのが東京方面ホーム。缶ビールを買った私も、大きな荷物を持っている外国人観光客の後ろからエスカレーターに乗りましたが、途中で東京方面ホームに向かっていることに気づき、あわてて下りエスカレーターで引き返しました。
皆さんは“あり得ない”と思われるでしょうが、そこが注意欠如型ADHDの特徴なのです。京都駅で博多方面ホームを利用するのは、オコゼを求めての春の倉敷と年末の川棚温泉の2回くらいなので、この時初めて新幹線乗車=東京方面ホームという意識が固定されていることに気づきました。意識の切り替えが出来ないのは老化の進行もあるでしょうが、とにかく反対側ホームに向かっていると気づいた時は、発車時間も迫っていましたので焦りました。
すぐにお年寄り様に電話しましたが携帯をハンドバッグに収納しているからでしょう、お出になりません。とにかく博多方面ホームに上がったらお年寄り様が歩いていらしゃいましたので安心しましたが、実にヒヤヒヤものでした。地図の読めないお年寄り様ですが字は読めますので、おかしいことに気づき移動したとのことで、自分のミスは棚に上げておき、“良かった”、やれやれの顛末でした。
このようにかなりのドタバタで出発しましたが、これに天候が輪をかけます。23日は広島方面の雪で新幹線は遅れましたし、山陰線では強風のため安岡駅で20分程停車を余儀なくされました。安岡駅を出るとすぐに玄界灘に面した大荒れの海が出迎えてくれますので、なるほどと納得。そうこうして宿に着き、早速お風呂に。川棚温泉はラジウム泉ですが、お湯は真綿で身体が包まれているようなやさしさ。フグとの相乗効果でリピーターになってしまうのです。
翌日は、朝方に雪がチラついていましたが遅れもなしに下関に到着、唐戸市場に向かいました。年末の土曜日ですからごった返しているかと思いましたが、案外すいていたので買いものは楽でした。また前回(2019年)は至る所から韓国語が聞こえてきましたが、今回はあまり聞こえませんでした。まだ訪日客は回復途上のようです。
私はソウルの成均館大学校(1398年創設)の心理学研究室と日韓母子の比較研究をしていましたのでついでに釜山にも何度か足を伸ばしていますが、下関と釜山の市場には何か共通した雰囲気が感じられます。もちろん、狭い歩行者用通路の両側にテント屋台が並ぶ釜山が規模では圧倒していますが、唐戸市場の呼び込みの声は釜山の露店で乾物などを売っているアジュモニたちの呼び込みを思い出させる、なぜか懐かしい雰囲気なのです。そういえば屋台のテントでソジュを一人で傾け、寂しくなるとここへ来て海を見ながら飲むのだと語ってくれたオッパがいたことも思い出しました。一期一会ですね、正に。
ところで下関から小倉に渡るのにはルートが二つあります。フェリーで門司に渡り、門司港駅から小倉までというルートとJRで下関から小倉までというルートです。全ての時間は調べてあったのですが、手帳は書斎に置き忘れていますから結局下関駅までバス。これがなかなか来ないので11時11分発の小倉行きを逃し、31分発に乗り小倉には11時46分着。駅でお弁当を買おうとウロウロしましたがファミマしかなく、諦めて改札内の弁当屋で幕の内を2個買い、新幹線エスカレーター横のちょい飲み店でほろ酔いセット2つを注文。
お年寄り様はコップ一杯しかお飲みになりませんので、私が20分程の間に中瓶2本を飲み干して引き続きキオスクへ。私は六角精児さん同様飲み鉄でもあるのですが、六角さんが銘柄にこだわらないのに対してビールはアサヒにこだわっています。なぜか新幹線車内販売はキリンとサントリーなのです。だからスーパードライのロング缶と350mm各1本を確保して乗り込みました。
京都には14:59分に到着しましたが土曜日ですので観光客の山。MKタクシー乗車の待ち時間が20分程度、道路も混んでいましたので結局自宅まで約1時間かかりました。待ち時間がなければ20分ほどで着くのですが。さて、玄関ドアを開けるとトラ姫様のサビを効かせた「ギニャー」というお声が。普段なら「ニャー」なのですが「ギニャー」ですから、お怒りだったのだろうと思います。
怒っていらっしゃることはリビングに入りよく分かりました。あれ、まぁ、なんということでしょう! 姫様は普段はお年寄り様の布団の中でお休みになられますから、今回もそうだろうと思っていたのですが、どうやら執事の帰宅がすぐに分かるようにとリビングでお過ごしだったようで、長椅子とスツールの間に膝掛けブランケットが落としてあり、寝跡が丸く残っていました。
抱かれるのが大嫌いで感覚過敏という自閉症傾向をお持ちの姫様ですから、当然お食事にもこだわりがあります。主食はカリカリさんですが、トッピングが必要なのです。これが鰹節とタタミイワシ、きざみ海苔ですが、温かいご飯に鰹節をまぶしたネコマンマとフグは別腹。という訳で姫様にはテッサ一皿を召し上がっていただきました。ペロリ、ニャン!
川棚温泉の旅が終わりますといよいよお正月の準備です。野菜など重いものは28日までに、こんにゃくやカマボコ、棒鱈やブリ、エビ、ハマグリなどの魚介類は29・30両日に購入し、31日は朝8時から調理開始です。お昼には調理の合間をぬってローストビーフや蒸し豚など肉系素材を買いに走りますが、夕方5時過ぎまで台所に立ちっぱなしで、3つあるガスバーナーは常に2つがフル回転して夕方には30種類ほどの料理が出来上がります。長くなりますので料理の内容については稿を改めましょう。
では皆様、良いお年をお迎え下さい。
(12月27日)
先ず隗より始めよ

これは中国の『戦国策』に載っている燕の政治家郭隗が、昭王の諮問に答えた言葉として有名ですが、皆さんご存じの通り、遠大なる策を考えるならまず身近なところから始めなさいという意味です。『戦国策』の成立は前漢時代ですから今から2100年ほど前のことになりますね。
言葉の詳細については皆さんのネット検索に譲るとして今回、なぜ私がブログタイトルとしてこの言葉を選んだか、それは12月16日の岸田総理の記者会見についての私見を述べておきたいと思ったからです。
ロシアによるウクライナ侵略を始め、度重なる中国の日本領海・接続水域への侵入や排他的経済水域へのミサイル着弾、2022年度北朝鮮による40回以上の弾道ミサイルの打ち上げなど、日本周辺でも情勢はきな臭くなってきており、真剣に「国防」という問題を考えなければならなくなってきているのは事実です。16日の会見はこの喫緊課題となっている「国防」の財源確保についての説明でした。新聞・テレビなどで報道されているように、今後必要とされる防衛費をまかなうために、法人・所得・たばこの各税を増税するという案です。
確かに全ての施策には裏付けとなる財政確保が必要です。その財源は企業や国民が納める税金や行政事務処理に私たちが払う手数料です。これらの財源だけで足りない場合は、ツケを将来に先送りする赤字国債が発行され、帳尻合わせがされています。しかし、これも何度かぼやきましたように、戦前の日本のように赤字国債が膨れ上がるとやがて償還が出来なくなり、ハイパーインフレでお金の価値がなくなって帳面上、国が発行した国債はチャラになりますが国民は貧乏になります。現代貨幣理論(MMT)が説くところでは、政府は幾らでも紙幣を印刷できるので債務不履行になることはないらしいですのですが。
私は心理学者で経済学者ではありませんから、MMT理論なるものを説明することは出来ませんが、この理論、“ほんまかいな?”と思わざるを得ません。現に、第一次世界大戦で敗北した当時のドイツでは1923年に5兆円マルク紙幣がシュツットガルトで発行されていますし、ベルリンでは5000億マルク紙幣が発行されています。こうなればお金ではなく、子ども銀行のおもちゃの紙ですね。日本における新円切り換えの混乱については7月6日の世相放談#13を参照ください。
でまぁ、何が言いたいのだというと、つけの将来への先送りを避けるためには増税は致し方ないと思うのですが、国民・企業にそれを求める前に国会議員自らが率先して経費削減の努力をして頂きたいのです。具体的には議員定数の削減とか、あるいは議員歳費のカットなど、議員の方々が身を削り、国の財政再建に率先して努力して頂いていることを国民に分かるように見せていただいた後、増税などの議論していただきたいのです。
ご存じでしょうが今の国会議員定員は衆議院が465名、参議院が248名で合計713名です。彼/彼女らに対する歳費は基本給が129万4千円ですがこれに色々つきまして、年間総額が5183万8千円というのが私の調べた結果です。国会に一度も出なくても歳費が保証されている議員もいますし、所属政党には政党交付金が315億円払われています。議員にはこれに加えて政治献金やパーティ券販売による収入などがあり、調べてみると政治家というのは、どうもファミリー・ビジネスなのです。一例として安倍元総理の系譜を書き上げてみましょう。
安倍元総理の父君は安倍晋太郎元自民党幹事長、弟は岸家に養子に入った岸信夫議員、二人の祖父は岸信介で叔父が佐藤栄作、晋太郎氏は阿部寛衆議院議員の長男と、要するに政治家の家系であることは、これも先刻皆さまご承知のこと。岸信夫議員は身体に不調があり、早晩引退してその長男が衆議院選挙に出馬予定とか。
それにしても最近の国会議員はお粗末の一語に尽きる類いが多いと思うのは私の独断と偏見でしょうか?一例が、統一教会の韓鶴子総裁と記念写真を撮りながら「記憶にない」・「覚えていない」を連発した大臣や、元おニャン子クラブの議員候補と一緒に統一教会の支部で挨拶をして、問題になると大臣から党の政調会長に回った議員、統一教会問題にだんまりを決め込む現衆議院議長、18歳の女子大生と飲食を共にし、ホテルで4万円を渡したと報じられたパパ活議員(父親も女性問題で顰蹙をかった元静岡県議会議員、7期)とか、まぁ議員の質の低下には著しいものがあります。そういえば妻を殺した長野県議もいましたね。
長くなりますのでこの辺で終わりますが、江戸っ子ではありませんが三代続けて議員という家系は、別に国会議員に限ったことではなく地方議員も含めてかなりの数になると思います。もしこれが、議員を三代続ければ家産がゼロになるのであれば誰も世襲しないでしょう。富や権力が増すから皆さん、議員の椅子に魅力を感じられるのだろうと思うのは私の邪推でしょうか?
そうではない!万機公論に決すべしであって、自由闊達に議論して日本の進むべき方向を探っていきたいから議員職を続けているのだとおっしゃりたい方がほとんどであると思うので、増税提案の前にまずあなた自身の身を削ってくださいな。それを見て私たちも続きますよ、つまり「先ず隗より始めよ」とお願いするのです。無理な相談でしょうねぇ・・・。
(12月17日)
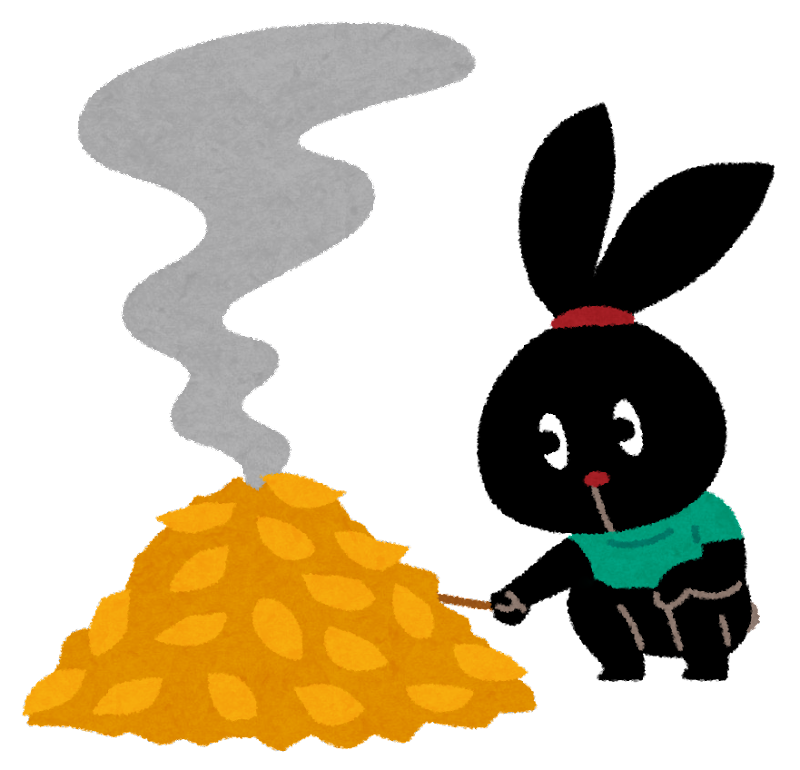
霧立ちぬ
28日に飯田高原の別荘を閉め、迎えの車で帰宅しました。高原でも毎朝、京都同様にTシャツ一枚で約2時間の散歩をしますが、この季節、天竜川の川霧が辺り一面を包み込む光景がほぼ毎日見られ、20m先が見えないほど濃くなったり、かと思うと急に薄くなったりでその変化は「いとおかし」。
飯田は南アルプスの赤石岳や聖岳に面していますが、当然この季節の山は雪をかぶっています。夏には黒かった南アルプスが白に変わると、いよいよ冬が来るなと、何かこう身が引き締まるものがあります。唯物論的にはただ単に山に雪が降っただけなのですが、夏が嫌いで寒いの大好き人間の私は冬の予兆にある種の緊張感、もっと言えば意気軒昂な高揚感を感じるのです。ですから11月に分厚いコートやマフラーで身体を包んでいる人を見ると、気の毒になぁと思ってしまいます。ワハハハハ。
それはそうと別荘を閉める際には庭の落ち葉をある程度、燃やしてしまわねばなりません。春は4月に開けるのですが、いくら冬場いないとはいえお隣さんも裏も定住の方々ですし、南信では南アルプスのように雪がすべてをおおい隠してしまうとはいきません。散歩の時に踏み歩く枯れ葉のカーペットは美しく、カサコソという踏み音は心地よいものですが、道路から家の玄関までの長いアプローチ(14段)に落ち葉が積もっていると、これが醜いのです。出入りする私が踏みつけて濡れ落ち葉状態になっているからでしょうか。
今年は雨が降っていた23日の水曜日に来ましたし、26日土曜日も雨予報でした。ですので落ち葉を燃やす日は金曜日に限定されてしまいました。日差しは木曜と金曜の午前しかなく、程よく乾いた状態とは言い難い条件で濡れ落ち葉を燃やさなければならないのです。これにはテクニックが必要です。
私は子どもの頃の家事手伝いとして、風呂沸かしを担当していました。火をたくとき、最大の火力を引き出すためには薪の間に空気を入れてやることが必要です。濡れ落ち葉を燃やす時も同じことで、まずは落ち葉の下に太めの枯れ木の枝をいれて空気の通り道を確保することが必要です。でも木はすぐに燃えてしまい落ち葉だけになってしまいますので、落ち葉の山に常に空気を補給してやるために火箸で空気を入れてやらねばなりません。こうしてくすぶり燃やしながら別の落ち葉も集めなくてはなりませんので兼ね合いが難しく、朝9時半からの作業開始で終わったのは午後2時半でした。これだけの時間を使って片付いたのは玄関へのアプローチ部分のみ。さほど濡れ落ち葉は厄介なのです。
この濡れ落ち葉の厄介さを揶揄する言葉があります。1989年の流行語大賞、「濡れ落ち葉症候群」あるいは「濡れ落ち葉族」です。これは、会社人間の亭主が定年退職後、趣味もないのですることもなく、おまけに友だちもいないものだから奥方にべったりついて歩いて迷惑がられている様を現しています。男性は女性に比較して社会性が欠けていることも多く、この言葉につながったのでしょう。
私? いいえ、私は原稿書きや講義の準備、友人とのメールのやりとりなどすることが一杯ありますし、トラ姫様のお世話や飯田にでかければ炊事・洗濯はもちろん、買いものや庭仕事などで大忙し。ですからどちらかと言えばこれも1986年流行語大賞の「亭主元気で留守がいい」の部類だろうと、自分では思っています。家にいるときのお昼担当は私ですしね。
このように料理は出来るのですが、部屋の片づけができません。今も机の上にはメモを走り書きした紙やレジ用紙などが6枚、トラの毛をすくブラシ、少ない頭髪をすく私の櫛1つ、朱肉1個、手紙1通、養老さんの「ネコも老人も役立たずでけっこう」1冊、水道使用量のお知らせ、電卓、爪楊枝が3本、Zoom用のマイク1本、USBが2本、ボールペンが4本、鋏が1つ、なぜか花の苗に差し込まれている説明カードが1つとまぁ、雑然としたものが散乱しています。右横の書棚には書き切れないほど色んな物が散乱。
どうしてですかねぇ、庭仕事は出来るのに、掃除はともかく部屋の片づけができないのは。トラ姫様がニャンともおっしゃらないからかなぁ。という訳で今回のブログタイトルは堀辰雄の、愛する人を見送る純愛小説「風立ちぬ」をもじって「霧立ちぬ」とし、きれいにまとめるはずが、「タンスにゴン」の愕然和尚の手にかかるとジタバタ物語になってしまいました。わしゃぁ、虫か?
(11月29日)
我が家の秋の風物詩

京都もやっと、朝晩の気温が10度前後となり、私の好きな季節になりつつあります。ということで、先々週から我が家の軒先には、握りこぶし大の江戸柿が80個ぶら下がりました。日中の温度は高かったですが晴れの日が続いて順調に乾燥が進行し、昨日味見をしてみましたがうまく出来上がりつつあります。いつものことですが干し柿がぶら下がると、秋も深まったなぁと思います。
干し柿作りも80個となるとなかなかの手間です。手順はこうです。まず柿のへたを取り除き、次にこの部分の皮を横に一包丁分むいてからお年寄り様に渡します。そうするとお年寄り様が全体の皮をむき、皿に載せます。4個たまると私がヒモでヘタ部分の芯をしばり、2個ペアを3階の庭(重量鉄骨で建てていますのでサツキを植栽した庭があるのです)に持って上がり、軒先のベンチに結わえたつり棚にぶら下げていきます。一回に4個ですから3階への階段は20回上がり下りする計算になります。結構な運動ですよ、これは。
こうして80個全てをぶら下げようとしますと二日がかりの作業になります。皮は水気を抜くために干しておき、家庭ゴミ収集の時に出しますが、沢庵をつけるならこれは甘味をつけるために必要な素材になります。昔はこうして捨てるところなく全てを有効利用したのですね。だけど青い空を背景に、ぶら下がっている干し柿は絵になりますよ。そう言えば私の叔父は画家でしたが、柿の絵を描くのが好きでした。軒先にぶら下がる干し柿、昭和の風景ですね。
谷内六郎という画家がいました。昭和31年から亡くなる56年まで25年間にわたり、週刊新潮の表紙を描き続けた画家です。尋常高等小学校卒ですから14歳で教育を終え、見習い工員などをしながら独学で絵を学んだ人ですが、どこか懐かしい、昭和の心象風景を描き続けた画家であったと思います。軒先に干し柿を吊す度に、谷内画伯の表紙絵を思い出すのです。
そう言えば「家の光」という月刊誌がありました。一般社団法人家の光協会が発行している雑誌ですが、JA(農協)系の雑誌で、昔は農事に関する記事が中心だったように記憶しています。この稿を書きながら調べたら未だに(失礼!)発行され続けているようで、さすが農協と、シャッポを脱ぎました。この表現、お分かりにならない方々の方が多いと思いますが、今調べたら徳川夢声などという活動弁士の例えが出てきたりして、いやはや昭和は遠くなりにけり。
(11月20日)
深まる秋

京都は今週もまだ20度を超える日が連日続いており、高雄の紅葉がやっと見頃になったとか。しかし、いつも言うことですが夏が暑すぎると葉っぱが枯れてしまい、3~40年前の見事な紅葉は再現されなくなりました。これは八甲田山のような東北でも同様ですし、先日訪ねた黒部もお天気が悪かったせいか、見事な紅葉という印象は受けませんでした。しかしとにかく、秋が深まっていることだけは事実です。
11月3日より奥飛騨、黒部、上高地と“秘湯”巡りの旅をしてきました。奥飛騨は“日本秘湯を守る会”加盟宿に10回宿泊すると、泊まった宿の内で気に入った宿に一泊無料ご招待という特典の宿泊でしたが、残る2軒の宿は一泊5千円の旅行支援付きでした。二人ですから2泊で計2万円の補助金が出ましたし、平日宿泊の宿では一人3千円が、土曜宿泊は1千円が補助されました。また黒部渓谷鉄道も一人1千円の食事券に加え一人2千円のお土産券が出ましたので、合計6千円の補助金を頂きました。しかし黒部ではこの金券が当日しか使えないということで、トロッコ列車が出る30分の間に6千円(2千円は食事限定)を使わなければなりません。わずか30分しかないのに、食事限定2000円の金券及びお土産券を必ず遣ってしまわなければならないという気持ちになるとは、私も卑しい人間に落ちぶれたなぁと思いましたが、何はともあれ食堂へ!
でまぁ、もう車を運転しなくてもいいのでポテトフライをつまみに、中ジョッキ(といっても500ミリ程度でしょう)2杯を15分程で飲み干し、ご老女様は紅茶とケーキセットのご注文。合計2,250円で実費は250円。その後売店でお酒の3合瓶2本(合計4500円で足が出た500円は自己負担)を購入しリュックに収納。トイレを済ませて窓付きのリラックス車に乗り込みました。
当日はあいにくの雨。車窓から撮った写真は帰宅後ほぼ全て、USBから削除しましたがこれも不思議なもので、人間、カメラを持っているとついついシャッターを押してしまいます。私、常日頃はスマホのシャッターを押している人たちを見て、なにもそこまで映像に記録しなくてもと思っているのですが、自分もその人たちと変わらないなぁと後で反省。反省だけならサルでも出来るという名台詞を思い出しています。
終点欅平から名剣温泉までは傘をさして歩き、温泉にトウチャコ。早速露天風呂で1時間半を過ごしました。私の風呂好き、お分かり頂けるかと思います。但し露天風呂が楽しめるのは外の気温が12度以下の場合に限ります。これくらいの外気温だと全身を5分程度外気にさらしますと冷たくなってきて、またお湯の中へ。しかし外気温が15度を超えると身体がなかなか冷えませんので、長湯は出来ません。という訳で今回は、丁度いい温度でお湯が楽しめました。
翌日は上高地の入り口安房トンネルを出てすぐに上の道に(通常、鍵がかかっていて番人の人がいます)入り、10回ほど折れ曲がった急坂を上った中ノ湯に宿泊しました、ここは秘湯の宿加盟店ですが、秘湯らしさはゼロのホテル仕様で部屋は8畳トイレ付きですが、トイレの空間が狭く、壁に鼻突き合わせる状態でしたし、気になるほどではありませんが隣室のいびきも聞こえてきました。正面が穂高岳ですので登山目的ならいいかもしれませんが、温泉好きの方にはお勧めできません。
お年寄り様のお話では、女湯は日帰り入湯の客でごった返しており、広くもない露天には降りて行く気にならなかったとか。ツイッター上では評判がいいとのことらしいのですが、私ども昭和の後期高齢者は静かに温泉に浸かるのが好きなので、お勧めはしません。長野県側に入るとトンネルだらけで走りにくい471号線ですが、奥飛騨側は見事な紅葉でした。
という訳で、トラ姫様にはいつものネコシッターさん(旧・ゼミ学生)を頼み、久しぶりで連泊をしてきました。日曜夕方に帰宅しましたが、姫様は「ニャン」とも仰せになりませんでした。イヌは200語ほどの言葉を理解しているとのことですが、自閉症の姫様なので案外一人も気になさらないのかも知れません。と、ここは留守することに対する合理化をしておきます。荒川さん、いつも有り難うね!
(11月8日)
教育に関する忠告

最近、「非進学校こそ日本の根幹」(日経夕刊/2022/10/12)という意見を読みました。京大人文研の藤原辰史さんの忠告です。幅広い研究・執筆活動をしていらっしゃるので肩書きは歴史学者となっていますが、Wikipediaによると食に関する総合的研究をしている人のようです(こういう調べ事の時、Wikipediaは便利ですね)。
で、要約にもなりませんが彼がこの意見を書いたきっかけが、園芸や造園、生活や福祉といった実習系コースを備えた宇部西高校が生徒募集を停止し、中高一貫の進学校を新たに整備するという情報だったようです。藤原さんの結論は、空飛ぶ車やロケットならどこの国でも作れるが、世界に誇る日本の庭園文化や料理文化、伝統技術といったものは担い手がいなくなると途絶する。だから偏差値のみで生徒や教育内容を切り分けるのは如何なものかという主張です。ごもっともなご意見!
ところで水道料金の自動引き落としを依頼していた信託銀行が今年度一杯でその業務を打ち切るということで、普通銀行にもつ口座に切り替える必要が生じ、ついでに定期預金も解約してきました。今の時代ですから定期預金といえども利子は10円とか5円、期間によっては1円でしかありませんが目を疑ったのは税金としてのマイナス項目が3カ所。合計わずか数十円ですが引かれています。要するにゼロ金利ということは、引き出したときに税金がかかって手取額が減少するということなのでしょう。今回初めて、ゼロ金利のもつ意味を実感することになりました。
この話と藤原さんの意見との接点ですが、三題噺のようなロジックになりますのでご注意を願い、うまく「サゲ」につながりますれば拍手ご喝采を。
政府は28日の臨時閣議において、家庭の光熱費やガソリン代に手厚い補助が必要であるとして29.1兆円の補正予算を組みましたが、補助金つまりばらまきがどうやら円安対策らしいのです。日銀の黒田総裁は就任以来2%の物価上昇を目標としてきましたが、10月の食品店頭物価は前年比4.5%上昇しています。円安で輸入する原材料が値上がりしているからです。しかし日銀は、確かに直近の値上がり率は日銀が目標としてきた2%を上回っているものの、持続的・恒常的な傾向ではないとして利上げには慎重です。つまり、湯水の如く発行してきた国債に利子が付くと、何回も申し上げているように税収の増加がないかぎり、政府財政が破綻してしまうから利上げ自体が出来ないという自己矛盾に陥っているのです。
こうしてビールもおつまみのハム・ソーセージ類も、マヨネーズも唐揚げ用の食用油もパスタも大幅な値上げになりました。確かに米だけは自給できていますが小麦を始めトウモロコシや食用油を絞るウクライナのヒマワリ種、インドネシアのパームヤシも、無論牛肉や豚肉、鶏肉も、とにかく殆どの食料を輸入に頼らざるを得ないのが日本の現状です(食糧自給率:38%)。どうしてこうなったのか、原因は農業自体の衰退です。
昭和の人なら“3ちゃん農業”なる言葉をお聞きの筈ですが、これは父ちゃんが会社や工場にとられてしまい、農業の担い手が「爺ちゃん・婆ちゃん・母ちゃん」になってしまったことを表す、昭和38年の流行語でした。やがてそれが「爺ちゃん・婆ちゃん」の“2ちゃん”になり、いずれか一人だけが従事する“1ちゃん”に、更には耕作を放棄した放棄地に、更には耕作を諦めた荒廃農地へと変わり元の山野に戻っていきました。蛇足ですが、作物を育てるのに必要な化学肥料の自給率はゼロであることもご承知おき下さい。
藤原さんは庭園文化や料理文化などの文化現象を論じて、偏差値重視の現在の日本の教育のあり方は如何なものかという問いかけをなさっていましたが、以上説明してきましたとおり国防はおろか教育や「食」などの国家の基幹においてすら、日本のあり方が脆弱であることがお分かり頂けたかと思います。今私たちは何を考え、どういう対策を講じなければならないのでしょうか。お爺さんには手に余る問いになってしまいました。
「山河荒れ 田畑壊れて 狐狸の国」 徒歩歩老人
(10月30日)
つるべ落としの日本経済

彼岸が過ぎて早一ヶ月、随分と昼間が短くなりました。秋の日はつるべ落としといいますが、この現象が季節だけではなく日本経済にも現れているような気がするのは私だけでしょうか。
今年3月からFRBがゼロ金利政策を中止し利上げを続けた結果日米の金利差が拡大し、10月20日の外為相場では1ドルが150円と、私が初めて在外研究に出た当時(1990年)の円価に戻ってしまいました。但しこの頃のアメリカ経済は弱く、失業率が7%に達しており、ニューヨークに行くと交差点に「失業中」と書いた段ボール札を持った白人が立っていました。日本はまだバブル期の最中で給料はどんどん上がっていましたし、貿易収支の黒字は10兆円を越えておりましたから日米経済の勢いの違いに感慨深かった記憶があります。(参考:日本の貿易黒字最高額は1998年度の13兆9914億円、今年度上半期貿易赤字額は11兆75億円)
日本が貧乏になっている話は何度かしましたが、当時は一億総中流とかいう言葉があったように、社会の経済格差はそれほど目立ちませんでした。しかし失われた20年の間に、これは経済的には弱者の高齢者人口が増えたことと無関係ではないのですが、日本の経済力はすっかり落ち込んでしまい、底辺が拡大して格差社会になったようです。10月末で退任する三村明夫日商会頭が、日銀の金融緩和政策が円安を加速させたと批判していますがその通り。しかし当初は企業も、デフレ日本にインフレを引き起こすためには円安が必要だとしたアベノミクスに賛成していましたし、それにのっかった上流(上級?)国民も多かったと思います。
そうして今となっては日銀がゼロ金利政策を放棄し金利をつけた場合、この間ジャブジャブに発行してきた(日銀引き受け)国債への利払いが発生し、税収の増加無しにはゼロ金利から抜けられない体質になってしまったのではないかと、素人の私は疑っています。日銀の黒田総裁のゼロ金利政策が日本経済を絞め殺したのです。
通貨を自由に発行できる政府はお札をどんどん印刷すればいいので、財政が破綻することはないというのが現代貨幣理論(MMT)らしいですが、それは国民や世界が日本政府を信用しているからの話。イギリスでは減税政策を打ち出したトラス首相が市場に混乱をもたらした責任をとり僅か就任一ヶ月半で退任するとか。日本も今はまだ、過半数の国民が政府を信頼しているように見えますが、安倍元首相の銃撃事件が暴き出した統一教会と自民党の癒着に端を発する政治不信は、いつ政府不信に転移するかわかりません。政府の政策を信用できなくなった国民が円を売ってドルを購入するようになれば、あっという間にスーパーインフレを引き起こすでしょう。通貨は信用で成り立っていることを忘れてはなりません。
食品店頭物価が前年比4.5%上昇し(日経10/21朝刊)、石油や天然ガスを始めとする様々な資源を輸入しなければならない日本の産業構造をみると、三村さんではありませんが円安は決して日本経済のプラスにならないのではと思わざるを得ません。年金以外何の収入もない高齢者にとって銀行預金だけが頼りなのですが、金利を産まない銀行預金は今や、振り込め詐欺集団から狙われる不良資産に成り下がってしまいました。構造改革もイノベーションもしない企業にまで、補助金や助成金として日銀券をばらまいてきた安倍長期政権がもたらしたものは、ばらまいて貰うための忖度文化とそれがもたらす政治・経済の劣化であったような気がします。
日野自動車や三菱電機の品質不正事件が象徴するように、忖度文化は企業をも蝕んでいきました。光り輝いていた東芝も事業再編で分割され、外部資本を受け入れざるを得ないとか。私にはよくわかりませんがどうやら社内はかなり混乱しているようです。日本は一体どこへ向かって行くのでしょうか?
(10月21日)
季節の贈り物

既に10月ですが京都は10月1日から4連続で30度を超え、2日日曜日は31度2分でした。しかし大陸から寒気が流れ込んだ日本列島は木曜日頃から師走の気温で、7日金曜のTV報道では東京の街を行き交う人たちのコート姿が目立ちました。私、実はこれを狙っていたのです。つまりマ・ツ・タ・ケです。
昨年同様今年も夏場、嫌になるほどの雨続きでこういう年は松茸の豊作につながるはずなのですが、今年のように気温が高いと菌が腐ってしまい不作だとか。しかし先週の木曜あたりから急激に温度が下がり、飯田あたりでも最低気温が15度になっていました。実はこの15度というのが、松茸の生育には重要な温度らしいのです。
という訳で例年より一週間遅らせて6日から飯田に行きました。苫屋は当然、朝晩は寒くて石油ストーブ無しでは過ごせませんが、松茸のためなら何を厭わん和尚さん。金曜は一日雨でしたが土曜はお天気。だから日曜朝には昨日採集された松茸が並ぶはずと踏んで、朝9時、豊丘村の松茸専門商店に買いに行きました。そしたらピンポーン、あたり!
商店にはつぼみを中心に取れたてが沢山並んでいました。やや傘が開いたものは6本ありましたが内5本を購入し、2本は友人に送って娘・息子・自宅にはそれぞれ1本づつ。ちなみに100グラムあたりの単価は4,320円でした。
大きく傘を開いたものがありませんでしたが、私は焼き松茸が好物なので開いたものを探そうと、その後豊丘村の森林組合の売店に行きました。9時から販売開始ですが着いたのは9時14分です。ところがさ~て、お立ち会い。なんと4~50人が列を作って並んでいます。列の後ろの方だと売り切れ御免になることもあると聞いていたのでこりゃアカンと、すぐに近くの豊丘マルシェに行き先変更。ここの駐車場もほぼ満車でしたが何とか駐車して店内に。お客さんでごった返していましたがぱっと目についたのが、理由は判然としませんが傘が半分に割れた松茸。一目見てすぐに手に取り、レジの列に並びました。マルシェではこれに加えてポポウと大きなナツメ、それに芹を購入。昨年購入できたヤマゴボウはありませんでしたが、秋の味覚がドッチャリコ。
京都に帰ってから計量しましたが212グラムで、虫は全く入っていませんでした。無論、割れた表面に虫の入っている兆候がなかったから購入したのですが、これがなんと4400円の値札。もし割れていなければ9891円、恐らくキリがいい1万円の品でした。本日はこの残りと自宅に残した95グラムの松茸で再び、土瓶蒸しと松茸ご飯。二日続けて季節の味を満喫します。
本当に信州はいい。合掌!
(10月10日・体育の日)
「国葬」に関する雑感
得度はしておりませんが僧籍にあった身として、故人のご冥福をお祈り致します。
9月27日、安倍元首相の国葬が終わりました。日経新聞が9月におこなった世論調査では、対象となった人の60%が反対(賛成33%)意見だったそうです。全国紙5社による世論調査では反対意見の高い順に産経(62.3%)、毎日(62%)、朝日(56%)、読売(56%)、5紙平均で59.3%と10人中6人が反対意見の中での挙行でした。
今回の国葬は内閣の閣議決定でおこなわれましたが、世界の多くの国々で国葬行為は法律や慣行に従って執り行われています。例えばアメリカでは国家元首を務めた大統領経験者を国葬で送りますし(例外は自ら辞退したニクソン大統領)、イギリスではエリザベス二世のような国家元首、及び戦後はチャーチル元首相ただ一人のみ。フランスでは大統領といえどもドゴール元大統領が辞退して以来、慣例的に辞退するのが普通だとか。まぁ、いろいろな慣例があるようです。しかし国葬という重要儀式を、僅か6日間の政権内密室協議に従い閣議決定するという場当たりな方法で実施する国は、私が調べたかぎりでは日本以外にはありません。日本は“水に流す”文化ですし、9月は台風も多いのでついでにでは困るのですが。
安倍氏同様在職中に急逝された大平正芳元総理の葬儀は「内閣・自民党合同葬」でしたし、急でしたので故人の業績などへの考慮はあまり問題にならなかったように記憶しています。安倍氏の葬儀に関しても、銃撃による死亡という前代未聞の事件でしたので岸田政権は泡を食ったのでしょう。事件の根幹に、韓国起源の旧統一教会という新興宗教が引き起こしている様々な社会問題があることを知りながら、またそれが自民党だけではなく日本の政治家達に深く食い込んでいることも知りながら、熟考すれば岩盤保守の突き上げを喰らうと思ったのか岸田首相は、国民世論を斟酌することなしに国葬を断行しました。浅慮としか言いようがありませんが、これが60%の反対意見につながったと思います。
ところで街頭での、「国葬」に関するTVインタビューを見ていて、私にはカチンときたことがあります。もちろんインタビューは賛成・反対・中立的立場それぞれの意見が反映されるように構成されていました。チャンネルは忘れましたがインタビューで若い女性二人組から得られた意見は、「アベノミクスで日本経済への貢献があったから国葬するのが当然でしょ」、というものでした。しかし聞いているかぎり、恐らくZ世代に分類されると思われるお二人からは、アベノミクスの内容を理解した上での発言というニュアンスが感じられず、単に言葉として‘つかってみた’としか思えなかったからです。
私には政治も経済も新聞論調程度の理解しかありませんが、科学者の端くれとしてデータを読むことには慣れています。そこで少しデータ整理をしてみましょう。
アベノミクスという言葉が頻繁に使われ始めたのは第二次安倍政権による2012年11月の衆議院解散前後からですが、この時使われた「三本の矢」という内容は、私は二本しかなかったと思っています。私の理解では、①マイナス金利にまで深掘りした量的な金融緩和、②予算ばらまきのための大量の国債発行です。③成長戦略については、効果的な政策・施策もありませんでしたし結果も残っていませんので、この矢はなかったと思っています。
ところでアベノミクスが始まった2012年、ドル換算した日本の平均賃金は37,739$、同じく$換算した韓国の平均賃金は37,302$で、僅かながら日本が韓国を上回っていました。しかし翌2013年には日本が韓国に逆転され、昨年2021年には日本は40,849$、韓国は44,813$とその差は4000$にまで開いてしまいました。日本が10年かけて3500$を増やしたのに対して韓国は7500$、日本の2.15倍ほどの速度で経済成長を遂げていることがわかります。
またOECD平均賃金では2021年の日本は34カ国中24位、最近の円安換算(1$=145円)で再計算すれば順位は更に下がり28位となるようですが、これがアベノミクスが日本にもたらした結果なのです。日本は相対的にですが、世界における経済的地位を下げ続けていることがわかります。こういう現状を理解しようともせず、単に聞いたことのある言葉としてアベノミクスを使っている今の若い世代の軽佻浮薄さは、昭和のお爺さんには耐えられないのです。
他にも色々言いたいことはありますが、国家を貧乏にした施策の立案・実行者を国葬で送る国というのは、はて?と考え込まざるを得ません。年代別に見た国葬賛成は、データが読める?Z世代を中心とした20代が最も高く58%、70代は26%だとか(朝日新聞)。Z世代は、2012年12月に1万395円だった日経平均を、退任時2万3千円まで高めた功績を認めており、それが高い支持率になっていると分析する識者?がいるようですが、お人好しもいい加減にしろと後期高齢者のお爺さんは言いたい。仮想通貨は別として、株式投資をしているZ世代は何パーセントおるんじゃ!日本の前途は暗いなぁ、ブツブツ。
とまぁここで一旦筆を置いたのですが、まてよ?と昭和のお爺さん。振り込め詐欺で欺されているのはみ~んな昭和世代だけど、欺す方はZ世代。今はNISAもあるし、従業員持株制度で自社株を保有する人も多いはず。仮想通貨はデジタルネイティブのZ世代にとってはおあつらえ向きの投資手段かも知れないぞと、お爺さんの猜疑心は止めどもなく広がって行きます。
そこで一句 「浜の真砂は尽きるとも 年寄りに妄想の種は尽きまじ」 石川六右衛門
(9月29日)
トラ姫様御入洛

9月17日、台風14号が来る前に京都に帰ってきました。トラ姫様はその2日前、中山道・東海道経由でご入洛されました。恐らく道路に発生する騒音が耳に響くのでしょう、感覚過敏の姫は車がお嫌い。ですから電車を使うのですが、飯田線を使うと豊橋まで特急で2時間40分かかりますし、豊橋-京都間は1時間10分ほど。しかも1時間に1~2本のひかりしか停車しませんので、秘境駅の多い飯田線は敬遠して中山道の中津川宿までは中央高速を利用します。
車内では私以外、誰も聞いていないのですが「拉致された」とまぁうるさいこと。電車は周りに人が少ないグリーン車を利用しますが、特急しなの号では車の中ほどではありませんが、それでもニュァニャァ。名古屋で新幹線に乗り換えますが、しなの号の中よりはニャァの頻度は低下します。最後、京都駅からはタクシー利用ですが、お疲れだったのでしょう20分程の道中一回だけニャン。玄関を入り姫様を御駕籠から解放しますとすぐに二階の寝室に上がられましたが、私は待たせておいたタクシーで京都駅に戻り、飯田に帰宅しました。朝8時45分に別荘出発、伊勢丹で買いものをして午後3時45分には帰宅と、まぁ毎回のことですが忙しい旅でした。
で、翌16日は姫様のトイレ掃除や食器のお片付けなどをして17日朝にゴミを出し、タクシーを呼んで高速バスで名古屋まで、新幹線乗り換えで昼過ぎに帰宅。姫様にご挨拶をと思い、二階にお姿を探しましたがいらっしゃいません。おかしいな?と思ってベッドの下をのぞき込むと、しっかり隠れていらっしゃいました。階段を上る私の足音で、また拉致されたらカニャワンとお思いになられたのでしょう。京都と飯田の往復は9年もしているのですが、なぜか今回のトラウマが一番強かったみたいです。同日、孫達が尋ねてきて姫様にご対面している時はお年寄り様のベッドの上で相手をしていらっしゃいましたが、私が顔を出したとたん、ベッドの下にお隠れになりました。「なんていうネコしょう!」
このように、トラ姫様は非常に個性的なネコなのです。普通、ネコは抱かれるのを嫌がりませんが、感覚過敏があるのでしょう、トラ姫様は抱かれるのが極端にお嫌い。手を離すと抱えられた箇所を入念にグルーミング。またトイレの仕方も雄猫のようにマーキングの姿勢で立ったまま、尻尾を上げてスプレィをなさいます。飯田ではトイレを置く場所が京都より狭いので、トイレ自体小さいものを使っていますのでスプレィされると壁や床が汚れます。ですからお小水が飛び散らないように、段ボールで囲いを作りそこにトイレシートを貼って外に漏れるのを防いでいます。
このように行動が男の子っぽいのですが、くつろいでいるときは必ず左手が前にでます。私の食事中、「ちょうだい」サインをしてくる時も左手が出てきます。人間ならば右脳優位の男性型なのでしょう。以上のような行動から、私は姫の自閉症を疑っているのですが、さて?
9月になりました:Came September

1961年ですから私が中2だった頃の話です。ビリー・ボーン楽団の「9月になれば(Come September)」というタイトルの曲がFM受信機から流れてきて、その軽快なメロディーが耳に焼き付いていますが、2022年75歳の今年も夏が終わり9月になりました。同名の映画はロック・ハドソンとジーナ・ロロブリジーダの共演で1961年に封切られたようですが、14歳の田舎少年には映画館へのアクセス手段はありませんでした。
私が映画に嵌ったのは高校1年の9月、片道40分のバス通学が受験のハンデにならないようにと、両親が綾部高校の裏に新築した家から通学するようになってからですから、「9月になれば」というこの映画は見ていません。しかしまぁ高校時代、さすが3年になると勉強したような気もしますが、出席時間と単位数を計算しながら親心を無視?して映画館に通っていたのですから、いい加減な少年だったわぃと、当時を懐かしく思い出しています。
Wikipediaによると彼女は1971年に女優を休止し、フォト・ジャーナリストや彫刻家として活躍を始めたそうですが、私の記憶にはソフィア・ローレンと共に、グラマーなイタリア女優という印象で残っています。今、95歳で健在なようですが今年9月のイタリア総選挙で上院議員に立候補するとか。よく「天は二物を与えず」とかいいますが、私は才能を持つ人というのは基本的にマルチであると思っています。でもまぁ、そういう人はごく少数だからこそのスターなのでしょうから、大多数は私のように無能・無芸の“一般人”なのでしょう。一般人に幸あれ!
それはともあれ、我が家の夏の終わりは9月、トラ姫様御付きのお年寄り様のご帰京に始まります。トラ姫様には、「暑いの大苦手」な爺やに今しばらくのおつき合い願いをお願いしております。ただ今年の夏、関西はどうだったか知りませんが南信地方は雨続きで、食料の買い出し以外はどこにも出かけない、今年の世界情勢同様、例を見ない暗~い夏でした。
当然、ご承知のように異常気象は世界各地で発生しています。中国やインド亜大陸、ヨーロッパでは大干ばつや熱暑に山火事。日本の東北や北海道、韓国では前線が停滞し大雨。特にソウルでは「パラサイト 半地下の家族」で有名になった半地下構造の住宅に住む家族が、押し寄せてきた水から逃れることができずに溺死したり、車が道路を流されていく始末。50度近い熱波で苦しんだパキスタンでは一転、雨季の洪水で国土の1/3が水面下とのこと。数え上げればきりがありませんが、全ては地球温暖化の副作用でしょう。
世界で発生しているこのような環境変化については以前、SDGsについての雑感を述べた時にも少しお話ししていますが、私たちの生活が便利になるということは、それだけ地球環境が破壊されているのだという事実に思い到ります。一例がプラスチックの使用です。買い物をすればほぼすべての食品がトレーや袋に入っており、これらはプラごみとして捨てなければなりませんし、ペットボトルもおびただしい量になります。
ひるがえって私の子どもの頃を思い起こすと、例えば家ではほとんどゴミが出ませんでした。野菜くずは飼育していたニワトリとヤギの餌になりましたし、ビン類は基本リ・ユース。豆腐は鍋をもって買いに行きましたし魚類は油紙にくるみ、竹の皮やへぎ(木を薄く削ったもの)も包装用でした。これらはすべて燃やすことができますので土に還ります。燃料は山から切り出した薪と炭でしたから、ガスも石油も必要ありませんでした。さすがに昭和30年代にはいると、来客の時は灯油ストーブを使用していたような気もしますが、小学校入学前は囲炉裏端に客が座ったと思います。思えば随分エコな生活をしていた訳です。
小学1年生(昭和28年、1953年)の時に13号台風が近畿地方を通過した時、由良川水系に甚大な被害が発生し、私が住んでいた中上林村も上林川の堤防が決壊し大きな被害が生じましたが、その復興を契機に貨幣経済の波が押し寄せ、村の生活は大きく変わりました。道路も拡張され(当時、新道と呼んでいました)ボンネットバスで綾部市街と結ばれましたが、それ以前の木炭バスがうっすらと記憶にあります(4~5歳)。まぁとにかく移動は基本、徒歩と自転車。村は昭和30年に綾部市に合併されましたが、街に出るのは年に数回だったでしょうか、母親が三ツ丸百貨店に併設されている映画館に映画を見に行く時に連れて行ってくれ、終わった後食堂で、旗のついたお子様ランチを食べさせてもらいました。
(続く) (2022年9月1日)
気候不順の今年

お話ししましたように今年は、6月20日に飯田に到着。翌21日には車を中山道の中津川駅前に駐車しておき、いったん帰宅。トラ姫様をお籠にお乗せして、東海道・中山道(新幹線・中央西線)経由でお国入りをしました。また7月20日には、トラ姫様お付きの御年寄様が同じく中津川経由でお国入り。夏の生活が始まっています。
ところで姫様の前では私は「ぢい」ですが、世間的には「ちゃま」で通っております。それには理由が。
19年前の1月に初孫が生まれた数日後、テレビで「千と千尋の神隠し」が放映されました。孫には千尋という名前がついていましたのでそれを見た時、「そうだ!カマ爺と名乗ろう」と思いついたのです。カマ爺は、千尋を助けてあげる優しく気のいいお爺さん。「貰った!」と思った次第。当時、56歳でまだ若いと思っていたので、「お爺さん」と呼ばれるのに心理的抵抗もありましたしね。
ところがこの子がしゃべるようになり、私を「カマジイ」と呼び捨てにするので親しき中にも礼儀あり。以前に鞍馬寺で小さな女の子が年配者を「おじいさま」と呼んでいたのを思い出し、ここはお上品に「カマジイちゃま」と呼ばせようと思い、彼女が「カマジイ」という度に「ちゃま」と言い加えていたらある日、「カマジイは名字で、名前がちゃま、やなぁ?」とのたもうて、こらアカン!
以来、学生や身内からは「ちゃまさん」と呼ばれています。閑話休題。
飯田では朝2時間ほどの散歩がルーティーンですが、今年は天候が不順で雨が降ることも多く、この原稿を書いている今日も台風8号の影響で散歩の途中から天気が急変し、雨が降り始めました。いつもなら折り畳み傘を持って出るのですが、大丈夫だろうと高をくくっていたものですから大慌て。幸い、雨が強くなる直前に朝のご挨拶を交わした名古屋の方が、ご親切にも車で追いかけてきてくださり、自宅まで送って頂きました。先週お話ししたサイコパスとは反対の共感性豊かな方で、お陰様で助かりました。感謝、ペコリ!
帰宅して地元紙の天気予報欄を見ると19日金曜日まですべて傘マーク。今年は雨が降らなくても曇り空が多く、そういえば庭の芝に水をやったのは一回だけ。夏場に雨が多い年はマツタケが豊作といいますが、雨が多かった去年は確かに豊作で安く買えました。私は焼き松茸が好きなので傘の開いたものを購入するのですが、直径15~6センチのものが5000円ほどで買えたような気がします。松茸は隣の豊丘村の飯伊森林組合に買いに行きますが、今年も豊作でありますように!
ところで雨の降りだす前に、今年初めてツクツクボウシの鳴き声を確認しました。今日は13日ですから後2日でお盆。秋の始まりですが、セミの鳴き声の遷移は適切に季節の移り変わりを示してくれますし、時間も教えてくれます。
朝、夜明けとともに鳴き始めるのはヒグラシですが、8時前にはクマゼミに交代。その後アブラゼミも合流して午前中はこの2種類の合唱。お盆頃からツクツクボウシも合流。午後2時を過ぎるころ今度は再びヒグラシに交代。夕方はヒグラシの絶頂時間帯。まぁ大体こういうところでしょうか。しかし雨が降っているとセミは鳴きません。羽が濡れるのでメスが飛んでこないからです。という訳で本日はセミの休養日、と思っていたら今は太陽が顔を出していますのでセミの大合唱が聞こえます。
別荘では晴耕雨読の生活ですから夜は早く床に就きますが、13日夜9時を過ぎたころに突然、まるで天の底が抜けたかのようなものすごい雨が降り始め、慌てて窓を閉めました。10分くらいで弱まりましたが、雲のどこにそれだけ大量の雨を一気に降らせる要素が隠されているのでしょうねぇ。恐らくは地球温暖化で水の蒸発量が増加し、雲の層が分厚くなっているのだろうとは思いますが。
翌14日朝、5時前に起床してポストの新聞を取りに行った帰り、階段を上がりながらふと下を見ると、あれ!ヘビの抜け殻らが落ちています。上を見ると天井の際に抜け殻がぶら下がっており、途中にはクモの糸に絡まった2センチほどの抜け柄もあります。全部足すと全長は1.5m?どうやら屋根裏に青大将が住み着いている様子で、脱皮しながら電線を伝ってウワミズザクラの枝に乗り移り、どこか食事にでも行ったのでしょう。昔からヘビが宿ると金が溜まるといいますが、宅は年金以外の収入はありませんので収支はトントン。ま、例外もあるのでしょう。
以前は屋根裏にスズメバチが巣を作ったこともありますし、庭にはビッキの大将がいます。そうそう、カナヘビ君もいますよ。2頭その存在を確認しているウリ坊たちも時々、木が生い茂ったため日影になっている庭のコケを鼻でほじくり、ミミズを探して食べている様子。夏の田舎生活はこのように賑やかなのです。やれやれ!
ウクライナからの避難民
飯田市の隣、高森町に空手の「禅道会」という団体があり(総本部・飯田市)、主席師範の小沢隆さんが中心になって高森町の協力の下、同会ウクライナ支部会員の家族4世帯9人の避難が実現しています。この避難者たちが8月1日から道の駅「南信州とよおかマルシェ」(豊丘村)にてキッチンカーでのボルシチ&ピロシキ、コーヒーのセット販売を始めたということで、私も買い物ついでに立ち寄ってみました。
禅道会の方でしょうか、日本人スタッフも二人いらっしゃって買い物はスムーズにできます。二人ですので2セットを購入し、コーヒーは駐車した車の中で飲んでボルシチとピロシキは持ち帰り、お昼に頂きました。ボルシチもピロシキも、私にとっては初めての味でしたが、共に美味しく頂きました。
禅道会では、避難民の人たちの仕事づくりとウクライナ本国支援を目的としたクラウドファンディング『ダニエラ基金』を立ち上げたそうです。詳細は、「https://daniela.fund」にアクセスしてみてください。
ところで鎌倉時代の元寇の役を例外として、四方を海で囲まれているという地理的孤立及び徳川時代の鎖国政策が原因でしょうか、日本は難民認定が最も難しい国と言われています。最近では2021年、名古屋出入国管理局に収容されていたスリランカ人女性のウイシュナ・サンダマリさんの体調が悪化し、食事をとることができなくなったにも関わらず放置し、死亡に至るという悲惨な事件も発生しました。入管職員はサンダマリさんが苦しんでいるのを「仮釈放が目的の詐病」と疑い、必要な医療措置を取らなかったそうですが私はこの話を聞きすぐに、人は誰でもユダヤ人を虐殺したアイヒマンのように冷酷になれることを証明した社会心理学者ミルグラムの、「アイヒマン実験」(Milgram, S., 1963)を思い出しました。実験内容を説明すると長くなりすぎますので詳細についてはネット検索で調べてください。
ミルグラムが実験的に証明したように、確かに人はいくらでも残酷・冷酷になれましょう。しかし同時に、人道的にもなれると私は信じています。中にはサイコパスのように、他者に対する共感能力が欠如している人もいますが、我々がHomo Socius(社会的ヒト)に進化したのはその昔、ヒトの祖先がマカクザルであった時代に脳の下前頭回(F5領域)と下頭頂葉に、相手の行為を「真似る」機能に特化した領域が発達したからです。この部位は“共感”という人の社会性の発達を担保した部位で、ミラーニューロンと命名されています(Rizzolatti G., Craighero L,2004)。興味がおありの方はWikipediaを参照してみて下さい。
まぁミルグラムの話もミラーニューロンの話も、短いブログで正確に要約しきれる内容ではないので端折りますが、言いたいことがあります。それは“組織”という枠組みが、人のもつ共感の働きを壊してしまうことがあるよということです。名古屋入管事件はその一例でしょう。つまり日本社会は未だ“村社会”であり、未熟なcogitoの持ち主が多いということなのかもしれません(17回世相放談参照)。西欧近代の幕を開いたデカルトのCogito、つまり自立した個人の確立は日本社会では“日暮れて道遠し”なのでしょうか。
それにしても悲しいですね、名古屋入管の話は。
(2022年8月10日)
ジムグリとの遭遇
一般社団法人対して課せられる均等割り税金が、法人の収入が少ないため代表理事の個人献金にならざるを得ません。ということで、一般社団法人は先月末で解散しました。私は顧問に退きましたが「愕然和尚の世相放談」は、今月から「保育・子育てアドバイザー協会関西2.0」から発信します。
関西も関東も連日の猛暑日。熱中症警報が出ているようですがここ飯田高原では爽やかな風が谷川から吹き込んできます。8月に入った最近はやっと天候が安定し晴天が続くため、朝の散歩は日影がある山の上の別荘区域をブラブラしていますが、今朝、めずらしい赤色のヘビを見ました。まだコドモのようで長さは25センチ程度で、動きません。ヤマカガシやヒキガエル、モグラの交通事故死は珍しくないので、死んでいるのかと思いそのまま坂を下り、木陰が無くなる野菜農家の手前で折り返してヘビがいた所に戻ってきましたが、見当たりません。
「なんだ、生きていたのか」と連れ合いと話しながら2時間ほどの散歩を終わり帰宅。ネット検索をかけるとどうやら“ジムグリ”という、成体で1m程度の無毒の小型のヘビのようです。地面や石の間に潜るため頭が小さいとのことですが、すらりとしたカッコいい印象を与えるヘビで、普段なかなか目にしないヘビらしく、私も9年いて初めて目にしました。ヒメネズミやアカネズミ、カヤネズミなどのコドモが主食とか。ですからネズミのコドモがいない夏には休眠することもあるとの事です。そういえば別荘の洗濯機の中で、小さなネズミが一匹が干からびていたことがありますので、山には沢山のネズミがいるのでしょう。
爬虫類のヘビの話をしたのですから、ついでに両生類の話もしておかなければ片手落ち?実はアズマヒキガエルが敷地内に棲んでいます。最近はトラ姫様が、毛玉吐き戻しのために笹の葉を食べに庭に降りるのですが、今朝もサンデッキから飛び降りました。そうして笹の葉っぱをかじって(ネコの歯は実に見事に草や笹の葉っぱを切り取ります)階段の方に進んだ時に、突然へっぴり腰になりました。そうしてそろりそろりと後退を始めたので、トラの視線の先を見ると15センチほどのアズマヒキガエルがいたのです。今年初めての目撃でした。
ヒキガエルはああ見えて、結構早く動くことがでるのですが、ただいつ動くか予測が立ちません。そうすると階段への通り道の石の上にヒキガエルが鎮座しているものですから、トラ姫様はその前を通ることができません。縁の下を利用して迂回すれば階段に至るのですが、外歩きを認めたのは今年が最初ですから再び部屋に戻ってもらうためには、ビッキの大将に退散して頂くしか手がありません。そこで庭掃除に使う箕をヒキガエルの前にもってきて、熊手で後ろをチョンと突くと大将がジャンプして箕の中に。通り道から離れた苔の上に置きました。
丁度コケに水をやらなければと思っていたところでしたのでビッキも水は好きだろうと、シャワー放水。すると反応の早いこと早いこと。ピョンピョンとジャンプしてあっという間にアプローチの両側に生えているシダの中に潜り込みました。トラが帰宅する階段付近にいなければいいので、どこに行ったかそれ以上は追及していませんが、去年は二匹確認していますので今年もどこかにいるのでしょう。連中は擬態というか保護色で、枯れ葉や木・岩などに容易に溶け込んでしまいますので、探さないと見つからないのです。
まぁそういう次第で、トラ姫様と御食事係の爺(時には執事、もしくは羊とよばれることもありますが)、それにベッド役兼冬の暖房役を務めている婆の3人?の、夏の生活が続いています。寝室には谷側の網戸越しに風が入ってきますので、朝、目覚めの頃は22度。今日のように下界が36度の時でも29度くらいですから楽です。夏にこういう健康的な生活をしていると長生きしてしまうかも。しかし令和の今は、昭和とはあまりにもすべてが違うので、長生きも困るのですが。 To be, or not to be, that is the question!
うつろいゆく未熟な“私”:Cogito ergo sum
7月26日、秋葉原無差別殺人事件の加藤智大死刑囚の刑が執行されました。事件が起きたのは2008年6月8日です。2019年7月には青葉真司容疑者が京都アニメに放火をして36名の死者、32名の重軽傷者が出ましたし、2021年12月には大阪「北新地クリニック」にてこれをまねたと思われるガソリンを使った放火が発生し27名の犠牲者が出ましたが、容疑者の谷本盛雄も死亡しました。
参議院選挙運動の最中、7月8日には大和西大寺で安倍晋三元首相が山上徹也容疑者によって手製の銃で狙撃され死亡するなど、ここ最近、衝撃的な事件が続発しています。一体何が背景にあるのでしょうか。識者がそれぞれ語っていらっしゃいますが私は、I amのI、つまり思惟及び行為の主体者としての「私」の構造のゆがみが原因ではないかと思っています。
「私」、あるいは「我」、さらには「自己」と様々に表記されるI am ですが、個人を行為の主体者としてとらえる考え方は、デカルトのコギト命題(我思う、故に我あり:Cogito ergo sum)に始まります。これは英語で「I think, therefore I am」と表記されますが、大事なことはこの時代に「私」が登場し、思惟する主体として人々の意識の中に成立したということです。ところが今、この「私」に大きな地殻変動が起きています。
心理学は、ウイルヘルム・ヴントが1879年にライプチッヒ大学に、人が環境から受ける刺激を処理する過程を実験的に検証するための実験室を開設した時を起源としますが、個体と様々な環境との相互作用を読み解く学です。私が人をカタカナ表記で「ヒト」と記載する理由は以前お話ししたと思いますが、ヒトは社会的動物(Homo Socius)ですから当然、行為主体の「私(I)」あるいは「自我/自己(self)」は社会との相互作用で形成されます。
このような「私」を巡る定義として有名なのはアメリカプラグマティズムの流れを引くG. H. Meadのself論です。これを要約すれば、①selfは主我(I)と客我(me)の相互作用で形成される。②その際に、自我の主体である主我よりも他者から見られている部分、つまり客我を意識の中に取り込むことが自我の枠組み形成において重要であるとMeadはいうのです。要するに自分の中に第三者目線をもつことが、主我の確立に必要だということですね。
人と人が地縁や血縁、あるいは契約でつながっている時代は、主我は人から見られている自分を意識することでつくり出されてきました。ところがIT化が進行し人々が実態ではなくバーチャルにつながる今、社会集団はその時々にネットでつくり出されるように変化しました。つまり、従来的な人と人が関わりあって共に暮らす社会がインターネット空間にとって代わられ、LINEやTwitter、Facebook、あるいは写真投稿のInstagram、動画投稿のTikTokやYouTubeでのバーチャルなつながりが、あたかも現実の対人関係と同じであるかのように錯覚させる時代になってしまったのです。
SNSの社会ではタレントの木村花さんが自殺に追い込まれたように、同じような思考や意見をもつ人々が「いいね」でつながり反対意見を受け入れませんし、時に“炎上”します。また、自分が共感できるソースだけにアクセスして、「ほらね!」っと自己満足で完結してしまう特徴をもちます。このような自己中心の狭いワールドが世界であると思っている人たちには地縁・血縁でつながる共同体社会や、意思に基づく利害の打算、合理的な協約や立法に基づく社会のような有機的つながりはなくなってしまうのです。
このような人々は自分の考えのみが正しく、トランプ支持者たちのように集団で意見が共有されることもありますが、それ以外はフェイクであるとして他者の意見を受け入れません。自分に都合のいいものばかり集めて形成された“世間”しか知らない「私」、つまり自分の主観だけで行動する短絡的な「私」が引き起こしているのが、冒頭に列挙した様々な事件ではなかったのかなと、ふと思いました。悲しいですね、こういう「私」が増えることは。
夏の生活
しばらく固い話ばかり続きましたが、ここらで一つ暑さしのぎに山の生活の話をしましょう。別荘の階段を踏み外して転落。グレゴール・ザムザになった心境はお話ししましたが、山にはいろんな虫がいます。かなわないのはブト(ブヨ、ブユともいう)です。ズボンの裾からでも入ってきますのでこれは護りようがありません。刺されたらすぐにステロイド系の軟膏をぬらないと痒くて大変です。その点、山に多いオオクロヤブカは楽なもの。体が大きいし動きも鈍いですから皮膚でもどこでも、止まればエイっと叩き潰せばお終い。幸い、山にはアカイエカはいません。
ところで去る6月25日夜、9時半に布団に横になり電気を消した直後、右耳の中に羽アリが飛び込んできました。鼓膜の横?でブンブン羽ばたくのでうるさいし、不快なことこの上なし。あわてて爪楊枝で掻き出そうとしたのですが無理!幸いお隣さんが天龍村で僻地医療に携わってらっしゃったドクターで、もう往診や夜間診療がしんどくなったとおっしゃって昨年4月から退職・定住生活に入られた方ですが、まだ10時になっていなかったのを幸い?に、無理やり押しかけました。
ただ、まさか耳の中に羽虫が入ったと私が騒ぐとは思ってらっしゃいませんから、そういう際の処置用医療器具は倉庫のどこかに放り込んだままだということで、結局市民病院の救急まで送って頂きました。ドクターを救急車代わりにしてしまったのです。「苦しい時の神頼み」と言いますが、神様は怪しくてもお医者様は本当にオタスケマンだワイと、変な納得で感謝感激雨あられ。以前、頭をスズメバチに刺された時もお世話になりましたし、持つべきものは医者の隣人などと、呑気なことをほざいています。
山にいるのは虫ばかりではありません。数日前朝の散歩で歩いていたら、側溝に大きなモグラが落ちて慌てていました。助けてやろうにも板切れもなにもなかったので、「自力脱出してね」とつぶやいてそのまま散歩を続けましたが、帰りには姿は見えませんでした。側溝下手に落ち葉が溜まって堰(そんな大げさなものではありませんが)になった場所がありましたので、そこまで下がってくれば脱出できたはずです。
同じ日、3時前に温泉に行くために山を下りる途中、サルの親子に遇いました。サルは別荘近辺に2群ほどいるみたいで、よく目にしますし仲間(お母さん?)を呼ぶ「フユィ~」という声も聞きます。入浴を終えて登ってくると今度は、家のすぐ近くでウリ坊に遇いました。自宅から100mほど先の小さな沢に沼田場がありますから、現れても不思議ではありません。このウリ坊はどうやら居ついた様子で、その後は朝の散歩で度々遭遇します。
「お爺さん、肥し撒いといたで」というタヌキ(と思います)は家の芝生に雲鼓をしていきますし、オコジョもいます。人間は背が高すぎますので恐らくオコジョの視線には入っていないのでしょう、すれ違っても案外平気です。今日は夏毛の茶色いオコジョが道を横切っていきました。
野鳥もいろいろいます。中でもシジュウカラやヤマガラ、コガラたちはほんの2m先の木の枝に止まったり、何かをついばんだりしています。カケスやヒヨドリ、セグロセキレイもよく遊びに来ます。時にはコゲラが裏手にある枯れ木を突いていることがありますし、ご近所に軽自動車が駐車した時に限って、サイドミラーに自分の姿を映し遊んでいるコヨシキリ(ではないかと思います)もいます。姿は見せませんがウグイスも常駐です。どうしてでしょうね、私は今までウグイスの姿を見たことがないのです。皆さんも鳴き声はよくお聞きになっていると思いますが、姿を見たことがあるという方はほとんどいらっしゃらないのでは?それくらい姿を確認するのが難しい鳥です。
毎朝2時間ほど散歩するのも日課ですが、途中で4~5羽の雛を連れたコジュケイの家族によく遭遇します。春に雛が孵化するコジュケイですが、夏場にはまだ家族で行動しています。夏には雛たちも飛べるようになりますが、5月頃はまだ飛べないようで、側溝は雛にとってもやっかいな存在。そういう場合は近くに落ちている木の枝を側溝においてやります。帰り道には先日のモグラ同様、姿が見えませんので、木の枝を利用して藪にもぐったなと判断しています。今朝は、雛が大きくなった7羽の家族に会いました。
時には散歩コースを変更して果樹農家や軽費老人ホームのある方向に、坂を下っていくこともあります。このコースでは民話の「桃太郎」に出てくるキジによく遭遇します。「ケ~ン」という鳴き声を聞きながら、キジは昔から人々になじみ深い里の鳥だったのだなぁと、なんとなくほのぼのした気持ちになります。春にはカッコウの声も聞こえます。カッコウも里の鳥なのですね。
そうそう、今年の春には初めてソウシチョウに遇いました。ソウシチョウはいわゆる“籠脱け鳥”で原産地は中国南部~インドシナですが、中国人が神戸に持ってきたものが野鳥化したと言われております。1~3月頃吉田山散歩に行きますと沢山目にします。羽の後ろの方に濃いオレンジ色の模様があり、さらにその真ん中に黄色の〇が入っているきれいな鳥ですが、それが飯田にもいたのです。生息域を広げているのでしょうね。この鳥は特定外来生物に指定されています。
7月に入るとまもなく秋が来るよという信号でしょうか、ヤマザクラやハゼの木に赤くなった葉っぱが、ほんの数枚なのですが混ざり始めます。この頃にはホタルやクロイトトンボが出てきますし、お盆が近くなるとアキアカネやオニヤンマ、シオカラトンボたちが飛び交います。また萩の花が膨らんできて、気の早い枝では花を咲かせるものもあります。
そうそう、セミの話もしておかなければなりませんね。山でよく耳にするのはミンミンゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシです。山梨県ではハルゼミの声も聞きますが、飯田にはいないようです。ミンミンゼミやヒグラシは夏盛り、ツクツクボウシが鳴き始めるとすぐ秋が来るなという想いになります。
嫌な連中もいます。隣村阿智村の園原にはマムシ養殖場がありますが、こんなのがあるくらいですから当然、別荘地にもマムシはいるはずです。ヤマカガシはよく交通事故に遭ってペシャンコに。私の家には、お隣さんがヌシとよんでおられる青大将が住み着いている様子。浄化槽の周辺は大きなものは手のひら大、中心的には握りこぶしサイズの礫石を敷き詰めているのですが、今年はその上で長さ1m23cmの、途中切れることがなく顎から尻尾の先まで完全に揃ったヌケガラを見つけました。昨年、法人関係者が拙宅に集まった時はウワミズザクラの枝に登った青大将の姿を全員が目撃していますし、まぁにぎやかなことです。敷地の西端は谷川ですから、ガマガエルも何匹かは棲みついている様子です。そうそう、サワガニも芝生の上を散歩?していますよ。
今週からは細君も合流しますが、まぁこういう環境で今、隣の椅子の上で寝ているトラと二人?で一か月、「なんにも仙人」修行をしているのです。ワハハハハ。
参議院選挙
安倍元首相が、個人的恨みをもった犯人から銃撃され、死亡するという蛮行が発生した異例の参議院選挙も終わりました。結果は事前予想通り与党の圧勝でしたが、候補者を擁立した各党の公約は大衆迎合主義(ポピュリズム)の“ばらまき”でした。人々の欲求は多様で際限がありませんから、様々なレベルで大衆に迎合しようとすると今回のように15もの政党・政治団体の候補者擁立になるのでしょう。しかしここで、少し辛口の話をしておきましょう。
財務省が5日に発表した2021年度一般会計決算概要によれば、税収は過去最高の67兆円ですがコロナ対策などへの支出が膨らみ、税外収入を合わせても歳出の2/3しか賄えず、残りの1/3は赤字国債の発行で穴埋めとのことです。前回(7月6日)お話ししました現代貨幣理論(MMT)の説くところでは、通貨発行権をもつ政府の破産はないらしいのですが、これを現実に実行した政府は未だ存在しない訳で(疑似モデルは基軸通貨のドルを発行しているアメリカ政府)、私は机上の空論ではないかと疑っています。
世界は貿易でつながっていますので常に決済が必要ですが、それには基軸通貨といわれる米ドルやユーロ、英ポンドや円が使われています。ですから基軸通貨を持たない国は決済手段としてドルやユーロを利用せざるを得ません。ウクライナに侵攻したロシアに対する西側諸国の圧力はまさにそこを狙っているわけですが、ロシアは資源国家ですので抜け道が沢山あります。詳細には調べていませんが、全世界的に見た再生可能自然エネルギー利用は、現時点で恐らく10数パーセントといったところでしょう。後は原子力を含め、様々な化石燃料利用で経済を動かしているわけですから、石油やLNGを始め金やレアメタルなど、鉱物資源を豊富にもつ資源国家ロシアをどこまで追いつめられるかは難しいところだと思います。
ロシアも当然、自国の資源を外交手段として使います。例えば直近、破産宣言を出したスリランカ政府はロシアに対し石油供給を依頼していますし、過去にロシアと強い結びつきがあったインドも中国も、表立ってロシア側に立ってはいませんが石油・ガスが高騰した今、ロシア産資源の割安輸入が可能になってホクホクというところでしょう。ジャーナリスト殺害に関連してサウジアラビアを非難していたバイデンの民主党政府は、過去に目をつむりサウジを訪問して石油増産を要請するとの事。国際政治はそれこそ奇々怪々なのです。
話を元にもどしましょう。今回の選挙ではどの政党も似たり寄ったりで分配重視の姿勢が強かったように思います。中には消費税やガソリン税を廃止し、子育て支援で毎月3万円交付など、極端なばらまき政策で議席を獲得した政党もありますし、Qアノンの陰謀論に似た反ワクチンを主張して議席を獲得した政治団体(この団体は今回の選挙で政党要件を満たしました)もあります。要するに、冒頭に述べた財政赤字をどうするのか、落ち込む一方の日本の経済力を回復させるために必要なイノベーションをどう創発するかなどの重要課題は、争点になっていないのです。
超高齢化社会の日本は、経済成長率だけではなく人口問題でも喫緊の対応をせまられています。2021年度の合計特殊出生率は1.30で、今のまま行けばアガサ・クリスティではありませんが3300年には日本列島に誰もいなくなります(世相放談6月8日参照)。だからといってある政党の公約のように、毎月3万円貰えるから子どもを産み育てようと思う人がいるとは思えません。結婚をしない人を含め、人々から夢を“奪った”結果が1.30という数値なのではないでしょうか。翻って見れば今回の選挙で、未来に夢を持てる政策を語った党や政治団体があったでしょうか。私はなかったと思います。そこで以下、お爺さんの夢物語。
皆さんは“国家百年の計”という言葉をお聞きになったことがあると思います。原典は中国の菅子の一節、「一年之計莫如樹穀 十年之計莫如樹木 終身之計莫如樹人」で、国家を興隆させようと思えば教育を重視しなければならないと説いています。これも以前、どこかでぼやいたような気もしますが、GDP比率でみると日本の教育機関への支出はOECD32か国中最下位で、百年の計を勘案した文教行政であるとは思えません。
各論を展開していると長くなりますのでいきなり結論。大学院も含めてすべての教育を無償化すれば、子育て負担は思いきり軽減されます。貧富による教育格差はゼロにはならないと思いますが、すべての子どもたちにはほぼ平等な機会が保証されます。教育の中身に関してはいずれ稿を改めてぼやくことにしまして、飛び級ありの落第あり、森の幼稚園ならぬ下町の寺子屋から村の鍛冶屋ならぬ各種専修学校。giftedを対象とした超エリートコースや全寮制学校など、家庭の経済状況に関係なく子どもたちの学びたいという気持ちを受け入れられる環境を整備する。このような施策が若い人たちの希望に繋がるのではないかと思いますが、如何?
無論、大学までの教育は終了と卒業に分けられ、今の高校や専修学校以上のコースは終了と国家試験合格を要件とする卒業に分けられ、子どもたちは必要に応じて選ぶことができます。要するにゆりかごから大学卒業まで、国家が面倒を見る訳です。その代わり、食料品・生活必需品以外の物品消費税はとても高くなりますよ。覚悟してネ!
低下する円の価値、高騰する物価、漂流する政治
参議院選挙の真っ最中ですが1$が136円、円安の進行が止まりません。日銀は現在、-0.1%の金利政策を継続していますが、日米金利差の拡大に加え日本のLNG輸入の10%を占めるサハリンからのガス供給が、プーチンの大統領令で打ち切られる可能性が出てきたとか。いやはや、恐ろしい状況になりつつあります。
長野県は内陸県なのでガソリン価格は元々高いのですが、先週満タンに給油したら1万1千円かかりました。今現在、トラと二人?なので買い物は原則2日に一回。しかしその一回で5千円以上かかる時もあります。家計簿をつけているわけではないので具体的に何がどうとは言えませんが、明らかに昨年よりは一回に支払う金額が増えているような気がします。日銀の黒田総裁が6月6日に、家計の値上げ許容度が高まっていると発言し叩かれましたが、一貫して円安を誘導する政策をとってきた政府・日銀の政策は果たして正しかったのでしょうか?
私は経済は門外漢なのでこういう見解が正しいか否かはわかりませんが、今、仮に日銀が金融引き締め(+金利)の方向へ舵を切ったとすると、湯水のように発行してきた国債に金利支払い義務が発生して、政府はその金利を支払うために国債を発行しなければならないというタコ足になるのであろうことは、トラにでもわかります。とにかく政府総債務残高(対GDP比)は2021年度世界第2位(263%)で、アメリカやシンガポールのほぼ倍の赤字財政なのです。ちなみに韓国は119位、対GDP比49.77%で日本と比較すれば健全な財政です。どうしてこういう状況に陥ってしまったのでしょうか。私見ですが、政権与党が国民ではなく企業を見ていたからです。その意味で公明党は、見事に補完役割を果たしました。
2013年から始まったアベノミクスを簡単に要約すると、日銀の異次元金融緩和政策で日銀券をどんどん印刷して円安を誘導し、企業に利益を上げさせ株主に成果を還元するものでした。90円で輸出していたものが120円になると表面上利益は30円増加します。経営者はイノベーションを起こさなくても利益がどんどん増加するわけですから名経営者と評価されますし、株価が上昇することで株主にも恩恵がありました。また、企業利益を税収として回収できるため、政治家もいかにも何か偉大な政策をなしたかのように評価され、そこに“忖度”が発生して至る所で円安現状維持こそが至上命題化してしまいました。こうして日本は変化を嫌う(あるいはしない)国になってしまいました。
確かにMMT(現代貨幣理論)では、政府は財政赤字になってもその分自国通貨を印刷すれば赤字が埋まり、だから理論的には政府の倒産(つまり債務不履行)はあり得ないらしいですが、現実はそううまくはいかないでしょう。例えば日本の食用油脂類の自給率はわずか3%。今、料理に欠かせない食用油類が何度も値上げの対象となっています。マクドのポテトも湖池屋のポテトチップス、その他お菓子類も値上がりがきついですが、それは食用油脂類の値上げが響いてきているからです。
日本の貿易決済は円建てが2割、残る8割はドル建てと考えたらいいでしょう。となると食用油脂類を輸入した場合、基本的にドル決済になっているはずです。今までなら1単位購入で100円払えばよかったものが今では137円になり(6月29日)、年末には150円に、更に次年度には200円になれば1単位購入に2倍のお金を支払わねばならないことになります。これがどんどん進んで行けばあっという間にラーメン一杯が1万円の価格に。要するにハイパーインフレです。日本も戦後1946年に時の幣原内閣によって俗にいう新円切り替えがおこなわれ、それまでの紙幣が使えなくなってしまいました。子どもの頃両親から、新円切り替えで持っていた戦時国債の価値がゼロになった話を聞いたことがありますが、私はハイパーインフレの可能性ゼロではないと思っています。
元首相は日銀は政府の子会社であるといい、自分の名を冠したアベノミクスはまだ道半ばと強弁しているようですが、彼がおこなったことは“ワニの口”を広げただけであると思うのは私一人でしょうか。今月10日投票の参議院選挙には15の政党・政治団体が名を連ねていますが、政党補助金ができてから日本の政治がでたらめになったと思うのは、私一人でしょうか?政党補助金を廃止し、昔のように個人の党費・献金に切り替えたら、少なくともNHK党なんてのはなくなるでしょう。NHKの視聴料と国政課題はどう関係するのでしょうか。馬鹿も休む休みにしろと言いたいです。
という訳で何度も“私一人でしょうか”とつぶやいた愕然和尚は、生まれて初めて投票権を放棄します。やってられん!
ステルス化を進行させる「カオナシ」現象(3):スマホ依存症とシンギュラリティ
マスクが個人のIDを壊し、スマホ依存が人間の考える力を奪っていると思うのは私だけでしょうか。皆さん、先刻ご承知のことと思いますがシンギュラリティという言葉があります。AI(人工知能)が人間の知能を追い越し、人々の生活が一変するであろうことを示唆する言葉で、「技術的特異点」と翻訳されますが時期は2045年と予測されています(Ray Kurzweil, 2005)。実際にはもっと早いという説もありますが、後述する理由で私も早くなる方に一票を投じます。
近代の社会科学は生命が創り出した社会をシステムとしてとらえ、生命同様に進化するとと考える今の思潮は、愕然和尚の禅的発想とは全く相入れないのですが、ま、ここは知能も知性もシステムも、全て一緒くたにしておきます。そこで以下、私の独断と偏見で論を進めます。
誰も言いませんがシンギュラリティとIoT(Internet of Things)は、コインの裏表の関係なのです。今ではスピーカーに話しかけると家電が動いたり、エレベーターボタンに指を近づけるだけで行き先階が指定できたり、レベル3(運転者はそれこそスマホでゲームをしながらハンドフリー)の車が販売されたり(ホンダ、REGEND)しています。確かにインターネットと繋がると人間が現場で対象を操作する必要がなくなるわけで、これからもIoTは進化し続けていくでしょうし、スマホはますます便利になって友や伴侶以上の存在になるのでしょう。友や伴侶とは別れることができますが、スマホをもたなければ生活そのものが成り立たない事態がすぐそこに来ているのです。私は人々のスマホ依存がシンギュラリティ成立の時間を速めていると思います。
手塚治虫先生は好んで時空を超越した世界を描いていましたが、「火の鳥」は圧巻でした。その「復活編」はまさにシンギュラリティ到来後の世界で、人間とロボットが共に働く社会が描かれています。手塚ワールドのロボットは極めて人間的で感情をもっていますが、「復活編」のチヒロという女性名のロボットも、やはり感情をもつ存在として描かれていて、交通事故で死んだのですが蘇生手術で生き返り、脳の大部分をAIに置き換えられたレオナという人間の若者と恋をします。
それはそうとして恋というのは人間の、しかも若い人の特権です。しかし「カオナシ」の時代、しかも社会的距離を保たなければならない今、誰かと恋に落ちることは難しくなっているのではないでしょうか。政治家は、恋に落ちなくても結婚は出来るし手厚い育児休業や手当で子どもが生まれてくると考えているのかも知れませんが、出会いもなく顔も失せてしまった現在、少子化はますます進行していくでしょう。失われた10年にならなければいいのですが。お爺さんの心配の種は尽きません。
ステルス化を進行させる「カオナシ」現象(2):マスクの弊害
2000年2月3日を最後に、私が関係するすべての会議はZoomでおこなわれていましたが、6月9日に2年4か月ぶりで対面での会議があり、上京しました。会場へは東京駅で中央特快に乗り換えが必要で、新幹線改札を出て歩き始めましたが途中で方向がわからなくなり、立ち止まって行き先案内の吊り看板を眺めました。新幹線中央改札口から直進すれば1番線ホームのエスカレーターなのですが、それが思い出せなかったのです。2年半という時間の長さを実感した瞬間でした。
それはさておき、丁度いい機会だから町中のノー・マスクの人数を数えようと思い立ち、朝の京都駅烏丸口からカウント開始。乗車は8時13分ののぞみですから、通勤通学の人たちであふれていますが、京都駅では全部で5名を確認しました。東京着は10:24分。駅構内で中年男性が1名、下車した市ヶ谷駅で若い女性が1名、帰りの中央特快車内で若い男性が1名、東京駅構内で中年男性が1名、下り新幹線ホームで60代の男性が1名の計5名でしたが、この男性は私と同じのぞみに乗車したので、関西人かも知れません。
京都駅には15:08分に着き、再びカウント開始。バスの一番後部座席に座って窓の外を見ながら自転車に乗っている人のノーマスクも含め、色んな年齢の人の観察ができましたが、自宅最寄りの近衛通バス停で下車までの間に28名の確認が出来ました。朝と併せて京都のノー・マスク合計は33名でした。無論、母集団の数が特定できませんので統計的には有意差なしですが、実は密かにホッとしました。京都人は集団の同調圧力に負けていないと思ったからです。
ご承知のように、文化的な社会集団には個人の思惟に重きを置く個人主義と集団の思潮に重きを置く集団主義があり、前者は個人の自由度が高いが後者は制限される傾向があると言われています。アジアの文化、中でも日本人は集団主義的で他者との同調性を重視するとされていますが、私は仮に日本の文化特性が集団主義であるとしても、そこにはかなり地域差があると思っています。
京都には売り上げが一兆円を超す企業が4社(京セラ、日本電産、村田製作所、任天堂)ありますが、生粋の関西弁でお話しされる日本電産の永守重信さんはエジソン同様、失敗することの効用を強調しています。つまり人と違ったことをしなさいというわけで、これは個人の思惟に重きを置く考え方です。最近では松下電器と言っても判らない方が多いでしょうが、パナソニック創業者の松下幸之助さんも、失敗を恐れず何でも「やってみなはれ」だったと伺っています。集団ではなく個人に重きを置く、つまり個性を生かしなさいとの勧めです。
こんな乱暴な仮説はブログだから許されると思いますが、関西人や名古屋圏の人たちには反骨というか自分の価値判断に従って行動する傾向があるような気がします。例えば“大阪のおばちゃん”です。外目には「品がない」という印象を与えるトラ柄のファッション(これには阪神タイガースも絡んでいると思いますが)とか見知らぬ人に飴を配るとか、まぁ自分がいいと思ったことに忠実?なのが大阪人というか関西人。関西人と一括表示すると“着倒れ”の京都人は、大阪のおばちゃんと一緒にせんといておくれやすと心理的抵抗があると思いますが、ここで強調したいことは関西人のもつ自律の精神、あるいは多数に「なびかない」姿勢ですのでお見逃し下さい。
話を元に戻します。私は子どもの頃、先生に反抗して問題児といわれたことがありますが、日本の学校教育では先生のいうことを素直に聞く子が“いい子”だったと思います。ところが最近では子どもがマスク顔になれてしまい、外してもいいよと先生が言っても外さない子どもの方が多いという報道があります。子どもたちの間にはいい子ノルム(規範)ではなく、カオナシ(アノニマス)であることの“楽さ”が意識されているようなのです。
カオナシは『千と千尋の神隠し』のキャラクターですが、宮崎駿監督は「カオナシは誰の心にも存在する」と語ったとか。巷間、これは人間の欲望を象徴したものだと解釈されているようですが、なるほどごもっとも。映画のカオナシはその時々で自分の感情を行為として表しますが、マスクをかけた現代のカオナシたちは目を除いて表情をなくし、感情を隠蔽する手段を手に入れてしまいました。ガソリンを撒いて24名の犠牲者を出した大阪の心療内科放火殺人事件の谷本盛雄容疑者も、当然マスク超しに面接を受けていたはず。こうして心や感情はステルス化されていくのです。
これも今となってはWikipediaを参照して頂くしか方法はありませんが、テレビ朝日の日曜洋画劇場の解説者として32年間活躍した淀川長治さんのセリフ、「怖いですねぇ、恐ろしいですねぇ」で、この項を閉めましょう。
ステルス化を進行させる「カオナシ」現象(1)
5月末から6月にかけて、各地の学校の生徒たちが体育祭の練習中に熱中症で倒れ、集団搬送されたという話がTVで度々報道されました。政府は最近、2m以上の距離がとれる場合や会話をおこなわない屋外ではマスク着用の必要はないと広報していますし、長野県庁はマスク必要なしの通達を全職員に出したそうですが、町を行き交う殆どの人はマスク着用です。私の散歩コースの吉田山緑地公園内でも、皆さんマスクをしていらっしゃいますし、自転車に乗っている場合でもマスク着用スタイルが定着しています。
私は心臓大動脈に90%の血栓が2カ所見つかっていますので、バス車内やお店の中ではマスクをつけますが、外に出たらすぐに外します。要するに路上にいるときはマスクは外しているのです。しかしある調査会社の調べでは、コロナ渦が収まった後もマスクを「必ず」と「できるだけ」使うと回答した人が合計で54%にのぼるとか。不安障害や身体醜形障害、極度に低い自己価値観の持ち主が5割もいるとは思えませんので54%という比率は、ジブリの「千と千尋の神隠し」にでてくる「カオナシ」のように、自分をアノニマス(無名)化してしまいたいと思っている人が多いことを示しています。私はこの現象をステルス化とよんでいます。
SNSの匿名投稿はタレント木村花さんの自殺で問題になり、ひどい誹謗中傷を繰り返した人物が起訴されましたがこれは例外で、要するに自分の存在を明確にしないから何でも言いたい放題で、責任をとろうとはしません。池袋暴走事故で家族を失った松永拓也さんに対してtwitterで誹謗中傷を重ねた人物も特定され、書類送検されたとか。このようにインターネット上の誹謗中傷を匿名でおこなう人たちに対して新しく「侮辱罪」が設けられ、「1年以下の懲役・禁固または30万円以下の罰金」という実刑判決対象とする法律が今国会で成立しました。しかしそもそもそういう行為をおこなう人たちは法律自体を知らなかったり無視する傾向が強いので、学校における人権教育の強化が必須でしょう。この事は新聞論調も含めて誰も言及していませんが。
それにしても今の世の中、Facebookは一応実名発信のようですが、TwitterやLINEを始め動画系のTikTokやYoutubeなど、全て匿名が原則。要するにSNS、つまりソーシャルメディア・ツールではその全ての発信者がハッカー集団同様、アノニマスであることが許されているのです。カリスマ(これもよくわからない言葉です)が、メーカーからギャラを貰って商品販売につなげるInstagramでは本人が顔出しをするようですが、これも絶対に顔を出さなければならないということでもないそうです。
世の中、このような一過性のSNSであふれかえっていますが、未だにガラケーの私はこの中のどれにも縁がありません。孫からデジタル難民といわれているお爺さんはfade awayするのみ。とにかく、もうついて行けません。トラちゃん、仲良くしようね!
そして誰もいなくなった
6月4日土曜日、新聞各紙の一面は厚労省発表の合計計特殊出生率の記事でした。出生率が1.30を割り込む状態が続くと2340年の日本の人口は100万人、2966年10月5日に最後の子どもが産まれ(東北大学子ども人口統計)、3300年には日本列島には誰も住んでいない状態になるそうです。
なぜかこの問題、先読みの鋭いイーロン・マスクが2022年5月9日にツイッターで取り上げていたみたいで、長くなりますがここに引用しておきます。
At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world.
(訳:日経新聞 「当たり前のことをいうようだが、出生率が死亡率を上回るような変化がないかぎり日本はいずれ存在しなくなるだろう。これは世界にとって大きな損失となろう」)
ちなみに彼は韓国についても言及しており、この出生率が続けば3世代内に現在の6%以下の人口に急減し、そのほとんどが60代以上になる(5/25日)とも投稿しています。
政府は2023年に「こども家庭庁」なる組織を立ち上げ、子育て支援を充実させていく方針とのことですが、どんなに手を尽くしても若い人たちに将来の希望を与えることができない限り、事態は統計予測通り進行していくでしょう。未婚女性の4人に1人が「結婚せずに仕事を続ける」、もしくは「結婚しても子どもをもたず仕事を続ける」と答えているのですから(出生動向基本調査、2015年)。
どうしてこのような事態に立ち至ったのでしょうか。識者はいろいろな解説をしますがなんにも仙人は、リアリティがバーチャル空間と一体化したことでリアリズムが崩壊したことが原因と考えています。現実社会で自分の夢を実現させようとすれば様々な困難を乗り越えていかなければなりませんが、アバターに変身可能なバーチャル世界では、条件の操作によっていくらでも未来を変えることが出来ますし、なによりも自分の行為に社会的責任が伴いません。
こんな便利な世界に住んでいる若者(御免なさい。人口問題を論じるので爺婆では話がつながらないのです)に、苦労をして自分の人生を切り開きなさいなどといってみても、効果はないでしょう。それよりも如何にして国の交付金や給付金、あるいは高齢者から金をだまし取るかに注力した方が、スリルと実益が得られると考える若者(だけではありませんが)が増えるのは当たり前。結婚して子どもを育てるというのは地道な努力の積み重ねですし、二人以上の人間関係ではお互いの意図の食い違いや感情摩擦が起こるのは当たり前ですが、バーチャルリアリティではそういう事態は発生しません。繰り返しますが、条件操作をすれば全てが変わるのですから。
地球環境問題もそうですが、私は現世人類は種としての生存の終わりに近づいているのではないかと思っています。どの文献だったか忘れましたが、高等脊椎動物の種としての寿命は500万年説がありました。無論、進化という視点に立てば別の種に置き換わっていくわけですし、子どもは人工子宮で量産されロボットが育児を担当するようになるかも知れません。なにはともあれ家族の中で子どもが産まれ、社会の中で育つという今のあり方の維持が難しくなってきていることだけは事実のようです。
幸いなことに、私個人としての寿命の終わりが近づいていますのをこれ幸い、ノーテンキに余生を送ります。スマホももたない爺さんは、笑うしか手がない。ワハハハハ
京都人は冷たい?
連休中も飯田にいましたが、今週はまた飯田の山の中にいます。こちらに来ると朝2時間くらい散歩をします。連休中には、それぞれのお家の前に各地ナンバーの車が停まりますので、皆さんどこからお越しかがわかりますが、今はすっかり静かになりました。もちろん京都ナンバーは我が家だけ。殆どが東海三県、中でも名古屋・岡崎・尾張小牧・一宮など、愛知県ナンバーが断トツです。
飯田での生活も今年で9年目。かなりの方々と顔見知りになりましたが、散歩の途中で顔を合わせ、初めてお話しする方もまだいらっしゃいます。今年も、車が止まっているのは良く目にするのですが、実際にお会いするのは初めての名古屋の方にお会いしました。私が自宅は京都と自己紹介すると、いいところですが夏はねぇと、京都の夏の暑さはよくご存じ。名古屋も暑いと思いますが海風が入るのでしょうね。
その点京都は盆地で、いわゆるうだるような暑さです。特に祇園祭が終わり本格的な夏に入る1週間、湿気が抜けるまでが大変。私は学生時代、中京区に住みましたが当時はエアコンなどありません。いわゆるパン一で窓を開けて寝ていました。無論、大学が夏休みに入ると即刻、綾部の寺に帰りました。
その方とお話をしていると、東京の知り合いが京都に憧れ、20年ほど前に移住したが伊豆に転居した由。理由は、京都の街はいいが、人が冷たいから住みにくいとのこと。以前勤務していた大学の同僚から、京都人というのは西陣を中心に下京・中京・上京に生まれ三代土着した人をいうのであって、丹後・丹波生まれなどは馬の骨といわれたことがありますが、それは納得。ところで良くいわれるのが、“ぶぶ漬けでも食べといやす”という京都の言葉の裏に“早く帰れ”という皮肉が隠されているという京都人“いけず”説ですが、私は鈍感なのでしょうね。そう言われたら、“おおきに、ほな頂きまひょ”という質ですから、冷たいと思ったことはありません。
そういう次第ですので、同志社大学学長や総長を歴任された故・松山義則先生のお宅を始め、様々なご家庭に随分ご迷惑をかけました。反省だけならサルでも出来る!ごもっとも。
追記:4月16日に松山先生の奥様の納骨がおこなわれました。ご遺族の方から連絡を頂きまして立ち合いましたが、その折に奥様に改めてお詫びとお礼を申し上げておきました。
SDGs
最近、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)という言葉をよく耳にします。目標の中には地球環境や自然環境に対する配慮が含まれていますが、今、シベリアでは“ゾンビ火災”と言われる自然発火の火災が広がり、凍土が溶けて大量のメタンガスが大気中に放出されているようです。
例年だとこのような火災には軍が対応しているそうですが、ウクライナ侵略に動員されている今年は燃えるがまま。緑が燃えてしまうと大気中の二酸化炭素の吸収源がなくなりますので地球の温暖化が加速します。またシベリアの火災では凍土が溶けてメタンガスが大気中に放出されますし、北極圏の氷の溶解が進み、ホッキョクグマは絶滅の危機に直面。SDGsもヘチマもなくなりそうです。
今年はブラジル大統領選挙の年。ボルソナロ大統領の施策はアマゾンの熱帯雨林を破壊してきましたが、返り咲きを狙っている左派のルーラ元大統領時代にも熱帯雨林は大量に破壊されました。特にルーラ氏が大統領に就任した2003年には25,396平方キロ、翌2004年には27,772平方キロと、群を抜いた面積が焼失しています。日本との比較でいえば2年間で、岩手・福島・長野・新潟4県分が失われた計算になりますが、貧しい人たちのアマゾン入植を積極的に進めた結果、熱帯雨林破壊に繋がったというわけでしょう。
インドネシアやマレーシア、タイなどのASEAN諸国の熱帯雨林も破壊され続けています。ボルネオ島のオランウータンも生息域が分断され、個体数は80%減。これらはすべてパーム椰子栽培のためです。極端な表現をすれば、湖池屋のポテトチップスが東南アジアの熱帯雨林を破壊しているのです。
インドでは、122年前に記録を取り始めて以来初めてとなる熱波の襲来を受け、連日50度を越す高温が続き、降水量は前年比99%減というすさまじさ。シベリアの火災は偏西風によってアメリカ大陸に影響を与えますから、今夏は再び、西海岸で大規模森林火災が発生するでしょう。私たちが爪に火をともすように環境への配慮を払ったとしても、このように地球規模の環境破壊は『どうにもとまらない』。だからリンダ、『こまっちゃうナ』。(平成以後にお生まれの方はWikipediaをご参照下さい)
妥協ということ
今年の連休は飯田にいます。26日からの大雨で上高地では土砂崩れが発生しましたが、伊那谷は無事でした。地球温暖化は大気の循環を増幅させ台風が大型化し、あるいは低気圧が線状降水帯をつくり出して、自然災害は増加の一途です。大規模災害はいつどこでどのように発生するかわかりませんので、いざという場合に備え生活拠点を2か所持つことが必要なのかもしれません。
それはそうとこの原稿を執筆しているのは5月2日21時。夕方5時からストーブを焚いていますが室温は19度以上に上がりません。先週は全国各地で夏日だったのが嘘のようです。草取りや花壇の植栽、庭木の手入れとかいろんな作業がありますので、寒いのが好きな私にとっては好都合ですが。
ところで皆さんはダケカンバやシラカバの花の形、ご存じでしょうか。私、初めて見たときは毛虫と見間違いました。動きませんから毛虫でないことはすぐに分かりますが、薄茶色で長細くて不気味な形。これらを含め、斜面や芝生の庭に落ちる花の軸などは手で拾うより仕方なく、庭先に一本生えている自己主張の強い杉の落ち葉と一緒に燃やします。ヒノキはさほどでもありませんが、杉の葉は存在感が強いと思うのは私だけでしょうか?
6月半ばから9月末までは飯田に常駐(?)しますが、それ以外は京都といったり来たり。苫屋を半月も空けると雑草は、生き生きとその存在を主張しています。雨の降った翌日の早朝など、太陽の光が当たって水滴がキラキラ光り、ダイヤモンドの輝きを見せます。生きていることは雑草であろうとも、かくも素晴らしいことなのです。逆に落ち葉や枯れ枝は「美」とは反対で、輝きを無くした「醜」の存在。だから禅は、死を「無」と教えるのでしょう。色即是空空即是色で「無」は「有」でもあるのですが、それは修行で得られる境地。
せいぜいが300坪ほどの庭なのですが、そういう訳で禅寺の庭に比較すると乱雑なことこの上なし。「にわにはにわにわとりが」ではありませんが、雑草や落ち葉を取り除いたと思ってもまた別の落ち葉や雑草が。どこかで妥協せざるを得ません。まるでわが人生のようだわぃと、ため息一つ。
“法~ぉ”(雲水の托鉢時の声です)
行雲流水
今、世界は全体主義国家と民主主義国家の2つのグループに分かれ、それぞれが衛星的に小国家を引きつけ、二つの価値観が相克しています。特定の個人や党派によって支配される全体主義は、各論や異論を認めない、国家による情報の一元的統制を一つの特徴とします。国民全体を一つの方向にもっていくためには、個人の自由意志は邪魔だからです。
折しも、人口2500万人の中国上海において、ゼロコロナ政策を貫徹するために都市封鎖がおこなわれていると報道されています。政権トップの面子のためには市民の自由意志は無視しても全く差し支えなく、官僚や軍・警察などの権力維持機構の面々はトップの気持ちを忖度し、羊を追い立てる牧羊犬のように人々を追い立てる、そういう国には住みたくないなと思います。ロシアや中国ほどひどくはないものの、日本も一時、忖度でやりきれない思いをしたことがありましたが、権力は周辺にそういう人たちを集めるのでしょう。
私は仏教徒として育ちました。父からは、生きとし生けるものはそのすべてが仏性をもっており、死ねば皆仏と教えられてきました。子ども心に「仏」というのは便利な言葉だと思いましたが、禅では天国も地獄もなく悉皆成仏、つまり「死」は「無」に帰することであると教えるのです。正確には輪廻からの解放と涅槃の世界を示していますが、煩悩をもっているとそれに惑わされるのでこれを捨て、身軽になって旅立ちましょうと教えます。また、生産に携わっていない私たちが生きていられるのはお仏飯のお陰なので、檀家の方々を含め有縁無縁の人々に常に感謝しなさいとも教えられました。
「宇宙無双日 乾坤只一人」という禅語があります。太陽が一つであるように、天地の間にはわれ一人があるよと教えます。人間はかけがえのない存在だと教える禅には、権力者の意図が忖度される全体主義やQアノンのような陰謀論が存在する余地はありません。精神は自由なのです。私の反権力、長いもの嫌い、少数派尊重、多様性容認の考え方はこうして形成されてきました。
私の煩悩からの解放、涅槃への旅立ちもあと少しの時間です。合掌
ストックホルム症候群
ウクライナのマリウポリが、今日明日にも陥落しそうです。ロシアは投降すれば命は保証するといっているようですが、保証はありません。キーウ近郊のブチャでは多数の民間人の遺体が見つかり、国際刑事裁判所(ICC)がジェノサイド疑惑で捜査を始めたそうですが、仮にそれが立証されたとしてもロシアは非加盟国なので罰則を適用することは出来ません。また、ロシアのウクライナ侵略に「ノー」を突きつけている国は世界人口の1/3、中立が1/3、侵略の口実に賛成する国の人口も1/3とのこと。世界は複雑ですね。
ただ、マリウポリが陥落するとドネツク全体がロシアの支配下にはいり、住民たちは全体主義国家の管理下に置かれます。全体主義で欠落しているのは個人の自由意志の尊重。占領地では既に、住民のスマホの履歴を調べて親露・反露の選別をしている(らしい)との話も聞こえてきます。反露勢力との接触があればすぐに徴兵され、訓練もなしに前線に送られるとか極東に移送されるとか?ロシア側にいわせればこういう情報は。西側のつくり出したフェイクであるということになるのでしょうが。
タイトルのストックホルム症候群というのは、1973年にストックホルムでおきた銀行強盗人質立てこもり事件で、被害者である人質が犯人に協力する行動をとり、解放後も犯人を庇い警察に非協力的であった事例から名づけられたもので、いつの間にか被害者が加害者に共感してしまう現象をいいます。情報が国家統制され、一方的な情報しか与えられていないロシア国民は、いつの間にかプーチンに強く親しみを感じているようです。それが83%という世論調査の支持率です。情報統制というのはそこまで効果的で、人の自由意志を破壊します。
孫に言わせると、lineもSNSもYou TubuもTwitterも利用せず、スマホも使わない私は生きた化石らしいですが、自分の自由意志を最優先に、情報に接するようにしています。このブログは事務委託先に依頼して配信して貰っていますが、皆さんの意志決定に介入する気は毛頭ありませんので、着信拒否もありです。よろしゅうに!
いそがしい仙人
私が時に愕然和尚と称することは先回お話ししましたが、「なんにも仙人」と名乗ることもあります(12月1日ブログ参照)。飯田の山中(標高900m)の“ネコと爺ちゃん”暮らしを自虐的に表現した(と、本人は思っています)ものです。苫屋は中央高速飯田インターを降りてすぐに山の方へルートをとり、10分も走れば到着する至便な場所なので定住の方々も結構いらっしゃって、田舎暮らしが楽しめます。
今年は飯田高原も雪が多くて道路には1m程の雪の壁が出来たそうですが、11日に来たときにはさすがに融雪していました。雪が溶ければ出てくるのがスミレや雑草。特にスミレが悩みの種です。こう言うと、“かわいい花なのに”という答えが返ってきますが、それは小川の隅にある場合。元々は緩斜面だったところに土を入れ、芝生を植えましたのでその中に点在するスミレは自己主張が強く、目障りなことこの上なし。私にとってはウクライナにおけるロシア軍のようなものなのです。ゲリラ戦に出てくるのはスミレの方ですが。
もう一つ厄介なのが「ミチタネツケバナ」という早春の雑草。スミレの種もはじけて遠くに飛びますが、タネツケバナも触った途端にはじけて飛びます。ですからそうならない前に抜いてしまわないと手に負えなくなります。苔も厄介者です。小さな谷川を挟んで西に杉林がある芝生の庭は、夏でも3時には日が陰ります。西日が入らない環境が購入を決めた動機ですが、これは苔には絶好の環境。という訳で、芝生に撒く肥料を糧にいつの間にか居着いてしまいました。
こういう環境ですから午前中は草引きでスクワット。草引きや掃除は、禅宗では作務といいますが、修行の一つと考えられています。無心になれるからです。根おこし片手にスミレやハルジオン、ミチタネツケバナや苔を引き抜いている時はウクライナの悲劇を忘れることが出来ますが、日暮れて道遠し。悟りには行き着きそうにありません。 犠牲者に 合掌!
【4月になりました】
私は極端な汗かきなので夏は大の苦手ですが、もう一つ苦手な季節があります。3月~4月、花粉の飛ぶ季節です。2020年春、日本におけるCOVID-19流行の初期、乗り物の中で立て続けにクシャミが出たときの用意に、「花粉症です」と書いたA4版のラミネートフィルムをリュックに忍ばせていました。知人に見せたら笑われましたが。
花粉症は60歳を過ぎてから始まりました。老化による免疫機能低下(Immunosenescence)が原因でしょう。幸い私の場合、ネコはアレルゲンではなく、スギ・ヒノキ・カモガヤ花粉への反応なので、膝の上で寝ているトラは無実。信州飯田の苫屋の隣は杉林ですし、敷地内にはヒノキも3本ありますが出かけるのは4月始め。都会のコンクリートジャングルのように、常に花粉が舞い上がっていることもないのでしょう。飯田では治まります。
ところで私、実家が寺でしたので学生時代、本山の南禅寺でおこなわれる安居会(あんごえ:集団修行)に3年間通い、僧職に就く為に必要な最下級の資格を取得しました。寺を継ごうと思えば最低でも1年間僧堂で修行する必要がありましたが、取りあえずということでした。ですから舜哉(しゅんさい)和尚でもあったのです。しかし父が隠居をして後任の住職に入山して貰った時に、資格を本山に返納し還俗しましたので今ではただの人です。が、時に愕然和尚と名乗ることがあります。
この、冗談法名には理由があります。今回のロシアによるウクライナ侵略もそうですが、とにかく世の中には唖然としたり呆然となったり、はたまたあまりの驚きに愕然とすることが多く、最後の強く驚くというニュアンスの愕然を借りた次第。
という訳で協会HPに連載していたこのブログ、今回からは、「愕然和尚の世相放談」のコーナーに掲載します。無論、発達相談に関する短いエッセーは従来通り「あゆむ」の枠で掲載します。協会の活動内容をお知り合いの方々にもご紹介いただき、講座への参加や様々な発達相談を寄せていただければ有り難いなと思っています。お恥ずかしいことですが、寄ってくるのは貧乏神ばかりで協会の財政は火の車。個人寄付で運営していますので、ニッチモ&サッチモなのです。所詮、聖者も坊主も金には縁がありません。ワハハハハ。
(2022年4月掲載分)
